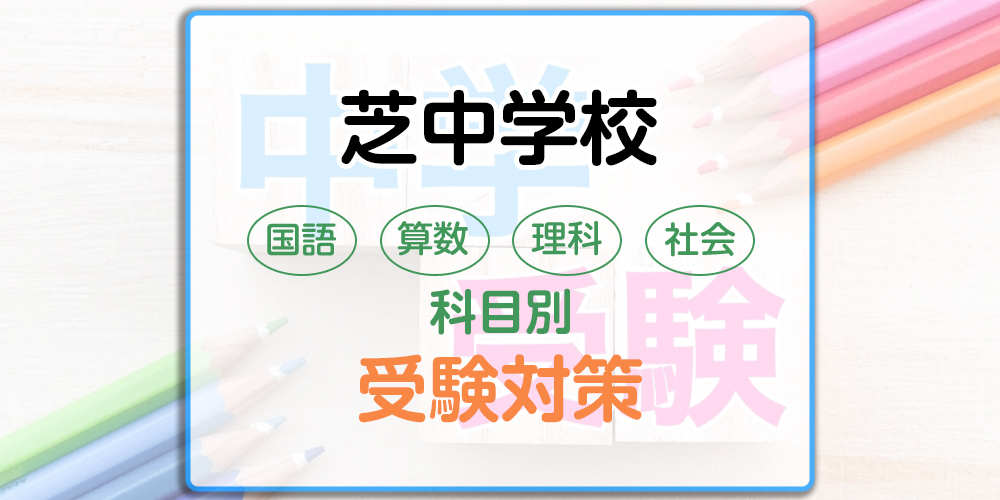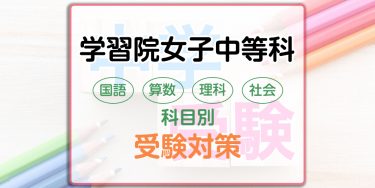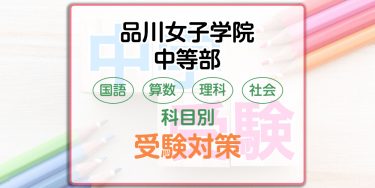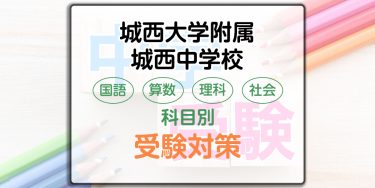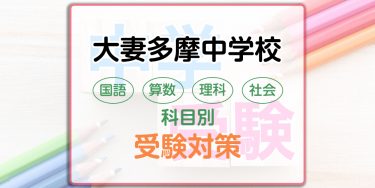芝中学校は歴史ある進学校として知られている学校です。この記事では芝中学校を目指す家庭に向けて、各科目の出題傾向と勉強法を紹介します。
そもそも芝中学校ってどんな学校?

芝中学校は、1887年に設立された浄土宗学東京支校が前身です。学校理念として「遵法自治」と「共生」を掲げています。
校舎は地上八階、地下一階と非常に大きく、広々としたスペースが生徒に提供されています。校舎のコンセプトは以下の三点です。「校訓である遵法自治の精神を醸成する明るく開かれた空間の構築」「生徒と教員、生徒同士のみでなくPTA・同窓会を含めた交流の場の設定」「多様化する新時代に対応しうる、技術的・創造的な教育施設の設置」。
校舎の中心部分は、地上六階から地下一階に至る吹き抜けになっていて開放的です。二階には職員室に接する場所にふれあいコーナーが設けられ、地下には生徒ロビーがあります。教育施設として化学実験室、生物実験室、物理実験室、マルチメディア教室、図書室、進学指導室、相談室など、スペースの広さを生かしたさまざまな設備が用意されています。
中学から高校まで学年ごとの進路指導が充実しているのが特徴です。進学実績として、2025年度は国公立大学に132名(内現役99名)、医歯薬獣医学部に96名(内現役65名)、私立大学に832名(内現役649名)という結果になっています。国公立大学の一例を挙げると、東京大学には18名(内現役16名)、京都大学には4名(内現役3名)、一橋大学には5名(内現役4名)、北海道大学には22名(内19名)、東北大学10名(内現役5名)他といった内訳です。医歯薬獣医学部の中で、医学部は64名(現役37名)でした。私立大学では東京理科大学125名(現役88名)明治大学96名(内76名)が目立って多かったです。
芝中学校の入試概要
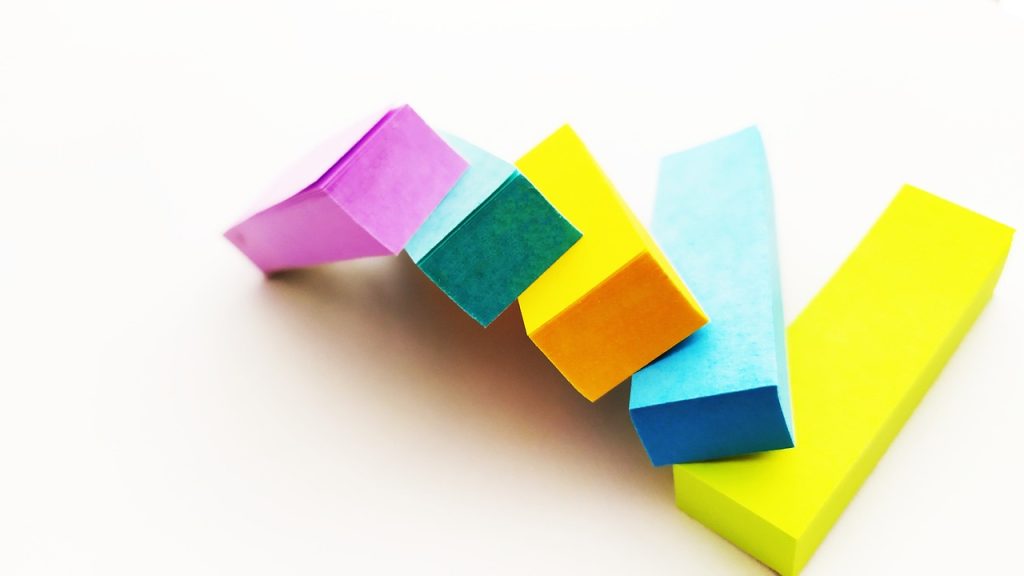
芝中学校の入試概要を見ていきましょう。
2025年度の入試
第一回は2月1日土曜日で150名募集、第二回は2月4日火曜日130名募集です。受験料は30,000円。出願期間は第一回が1月10日金曜日9時から1月26日(日)12時まで、第二回が2月4日21時から2月6日12時まででした。
2025年度の倍率
第一回の受験者数は476名、合格者数は192名、実質倍率は約2.5倍、第二回の受験者数は775名、合格者数は273名、実質倍率は約2.8倍です。合格者平均点は350点中第一回が196.6点、第二回が220.8点です。なお、実質倍率は小数点第二位以下を四捨五入しています。
| 入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 第一回 | 476名 | 192名 | 約2.5倍 |
| 第二回 | 775名 | 273名 | 約2.8倍 |
芝中学校における国語・算数・理科・社会の出題傾向

芝中学校の入試における出題傾向は以下のとおりです。
国語は記述が多く知識問題も出題される
国語の試験時間は50分で配点は100点、大問は四つです。大問一では漢字、大問二では慣用句、大問三・四で論説文と物語文がひとつずつ出る構成となっています。
大問一が漢字の書き取り、大問二が慣用句の知識と漢字の書き取りを兼ねた問題です。大問三は論説文、大問四は物語文で、読解問題はすべてが記述問題なので、かなり時間を要します。十五字程度の短い記述から100字程度の長い記述まで幅広い出題です。
算数は大問の数が多い
算数は試験時間50分で配点は100点、大問は八つほどです。大問一では計算問題が出題されます。大問二以降は単元別の出題で、大問ひとつにつき、小問が二三問です。
速さや割合、平面図形、場合の数といった単元がよく出ます。大問数が多く、限られた時間内に素早く処理していくことが求められる分量です。全体的に難易度自体はそこまで難しいわけではありません。ただし、場合の数の問題は比較的ひねりのきいたやや難しめの問題が多いです。平面図形は問題によって難易度に開きがあります。
理科は問題数が多くスピードを要する
理科は試験時間40分で配点は75点、大問は五つです。大問一が総合問題で、大問二以降は各分野からの出題となっています。
難易度は大問によって標準レベルとやや難しい問題に分かれている印象です。実験や観察の問題が多く、解くのに時間がかかります。問題が提示する資料にも目を通さなければなりません。一問当たりに割ける時間は単純計算で一分強であり、時間的にはタイトと言わざるを得ません。
長文を読ませる社会
社会は試験時間40分で配点は75点、大問は五つです。大問一は総合問題で、大問二以降は各分野からという理科と同じ構成になっています。
出題形式としては用語記入や記号選択が多く、最後に100字程度の記述が出ます。5000字以上のリード文を読ませる年度もあるので、国語のように速読が前提となる試験です。資料を用いた問題が多く、40分で解くにはボリュームたっぷりといえます。
- 国語は記述問題と知識問題が多く、算数は大問数が多く速さや割合などが頻出
- 理科は実験や観察の問題数が多く時間配分が重要であり、社会は長文読解と資料問題が多く時間がタイト
芝中学校に合格したい。どんな勉強が効果的?

芝中学校に合格するためには、どういう勉強をするべきなのでしょうか。科目別に見ていきましょう。
国語の勉強法
国語にはどう取り組めばよいのでしょうか。
漢字の書き取りは丁寧に
漢字の書き取りで点を落とさないよう、一字一字丁寧に書く習慣を身につけましょう。とめはねはらいができていなかったり、筆圧が弱かったりすると、減点されかねないので注意したいところです。
また、大問二では書き取りをする漢字が慣用句の一部として出題されるので、漢字力と合わせて語彙力アップを図ることをおすすめします。
速読が必須
読解文をふたつ読み終えた上で、時間のかかる記述問題を数多くこなさなければならないため、速読は欠かせません。記述問題を解ききるのにどのぐらい時間が必要かについては、個人差が大きいです。
タイマーをかけて過去問を解いてみて、読むのと解くのにそれぞれどのぐらい時間をかけているかを把握しましょう。その上で、必要な速さがどの程度かを分析し、スピーディーに読み込む力を身につけましょう。
記述問題ばかりが出題
大問三以降からは記述問題ばかりが出題されます。短いものから長いものまで、字数指定に合わせて問われている内容を的確に書き出せる力が必要です。時間内にたくさんの記述問題をこなさなければならないので、素早く書けるようにしてください。
特に100字程度の記述では苦戦する子供が多いです。長い記述ならではの書き方をあらかじめ身につけておく必要があります。
点差は六点程度に留まる
2024~2025年度の受験者平均点と合格者平均点を見比べると点差はだいたい六点程度に留まっています。比較的、点差がつきづらい科目といえるでしょう。そのため、国語が苦手なのであれば、受験者平均点あたりを目標にし、他の科目で差をつける作戦も有効です。
- 漢字の書き取りでは書き順や筆圧に注意して丁寧に練習し、慣用句の漢字が出題されるため語彙力も強化する
- 読解問題を効率的に進めるためには速読が欠かせず、タイマーを使って過去問を解いて読解と記述にかかる時間を把握して必要な速さを身につける
- 100字程度の記述に苦戦しがちなので長文の書き方を事前に練習しておく
算数の勉強法
算数にはどう取り組めばよいのでしょうか。
計算問題は確実に解こう
小数と分数が入り混じった計算が出題されます。計算ミスしやすいので、途中式のメモは読みやすく書いてください。計算ミスが続くようであれば、そもそも計算力が定着化していない可能性があります。日々、繰り返し取り組むとよいでしょう。
受験者平均点と合格者平均点が大差
算数は受験者平均点と合格者平均点に大きな差が出る教科で2024~2025年度の結果を見ると、だいたい10~15点差がつきます。そのため、できるだけ算数ではリードしておきたいところです。特に序盤の簡単な問題での失点を減らしましょう。
平面図形の問題も頻出
平面図形は年度によって難易度の差が大きいです。基本から応用まで対応できるようにしてください。相似、面積比の問題や、補助線を引いて解く問題などが出ます。
グラフを使用した問題も頻出
速度も頻出単元のひとつです。グラフと組み合わせて出題される問題をはじめ、比較的難易度が高めになる年度が多いです。応用問題まで解けるようなやり込みが欠かせません。受験問題集をやり込んでおきましょう。
- 途中式を読みやすく書き、計算力が定着していない場合は繰り返し練習しておく
- 相似や面積比、補助線を使う問題などに対応できるよう、基本から応用まで練習しておく
理科の勉強法
理科にはどう取り組めばよいのでしょうか。
難易度の高い年度も
2024年度の第一回の受験者平均点は75点満点中30.9点、合格者平均点は36.7点です。これはここ数年でも顕著に低い点数でした。ちなみに2024年度の第二回の受験者平均点は41.4点で、合格者平均点は47.9点、2025年度の第一回の受験者平均点は37.2点で合格者平均点は42.3点、第二回の受験者平均点は42.8点で、合格者平均点は48.6点。
つまり、合格したいなら六、七割とるのが基本で、たまに五割程度でも合格ラインに到達できる年度があるということです。難易度が高い場合は、特に物理や化学の問題で得点できないケースが多いので、苦手意識がある場合は繰り返し該当の単元をやり込んでおいてください。
計算問題を解けるように
化学分野、物理分野から計算がよく出題されます。計算は図表やグラフと共に出題されるケースも多く、必要なデータを読み取って解かなければなりません。テストや模試、あるいは自分で過去問を解いたときに正答を出せていないのであれば、すらすら自力で解けるようになるまで類題も含めてやり込むのがよいでしょう。
時間がタイトなので優先順位をつけて
理科は一問にかけられる時間がだいたい一分程度です。そのため、スピーディーに解かないと最後までたどり着けない危険性があります。自分が苦手な問題は後回しにし、解けるところから解いていってください。
計算問題は見直しに回す時間がほとんどとれない可能性が高いので、途中式をぐちゃぐちゃに書かないなど、ケアレスミスが生まれない工夫をしましょう。
- 理科は難易度が高い年度があり、特に物理や化学で得点できないことが多いため、苦手な単元を繰り返しやり込んでおく
- 計算問題が頻出で、図表やグラフから必要なデータを読み取って解く力が求められるため、過去問を繰り返し解いて自力で解けるようになるまで練習する
社会の勉強法
社会にはどう取り組めばよいのでしょうか。
ラストの記述を除いて記号問題と語句
社会は近年、ラストの記述を除いて記号選択と語句の問題のみで構成されています。記述がひとつだけとはいえ、問題数が多い上リード文も長いため、どうしても時間がタイトになりがちです。テンポよく解いていかなければなりません。そのためには速読が必須です。
記述問題を攻略するには読む力が大切
例年、社会問題を扱った記述問題が出題されています。長い文章を書くのに苦手意識がある子供は戸惑うかもしれませんが、文章をよく読めば非常に国語的な出題だということがよくわかります。社会の知識が問われるというよりも、設問の意図を汲み、文意を読み取る力が求められているのです。
たとえば、2024年度は文章の中にある「駅伝を走る選手がタスキを受け継いでいくように」という比喩を通してなにを伝えようとしているのかを問う問題でした。文中の二重線で示した箇所を複数のキーワードを使って答えよ、という出題形式がここ数年定着化しています。指定字数は年度によって増減が見られるようです。2024年度は100字以内ですが、2023年度は80字以内でした。
点と点ではなくつながりで
語句や選択問題が中心と聞くと、一問一答で覚えれば対応できそうな気がするものです。しかし、実際の問題を見ると、そう単純ではありません。選択問題は細部まで理解していないと間違えるようにできていますし、歴史では時代の並べ替えの問題も出題されるため、点と点ではなくつながりで覚えておきたいものです。単元ごとに流れを説明できるようにしておきましょう。
- 社会は記号選択と語句の問題が中心で、記述問題はひとつのみなので、速読でテンポよく解き進めることが重要
- 社会の語句や選択問題は細部まで理解していないと正解できないため、単元ごとの流れを理解し、点と点ではなくつながりで覚えておく
芝中学校は時間がタイトな科目が多い

芝中学校の入試では、問題数が多かったり手間のかかる問題が出たりして、時間的にタイトになる科目が多いです。
国語では読解文で記述問題ばかりが出題されるため、素早く読み込む能力と素早く書き出す能力の両方が必要となります。記述が苦手な子供は早めの対策を心がけましょう。記述問題は自己採点せず、必ず塾の先生や家庭教師に添削してもらってください。
算数では大問が八つと多いため、標準レベルの問題は確実に解き、時間内に合格ラインに到達できるようにしなければなりません。序盤の簡単な問題で失点しないようにしてください。
理科は問題数が多い上、難しい計算問題も混ざっているため、時間ギリギリになるでしょう。物理・化学の計算問題をスムーズに解けるよう仕上げておきたいところです。
社会はリード文が長く、最後には100字程度の記述も出題されます。社会の知識はもちろんのこと、国語力も求められる内容です。
過去問をやり込んで、各科目の出題傾向を把握し、適切な時間配分ができるようにしましょう。タイムロスしそうな問題があれば、該当の問題を飛ばして、時間内に解ききれるよう優先順位を検討してください。