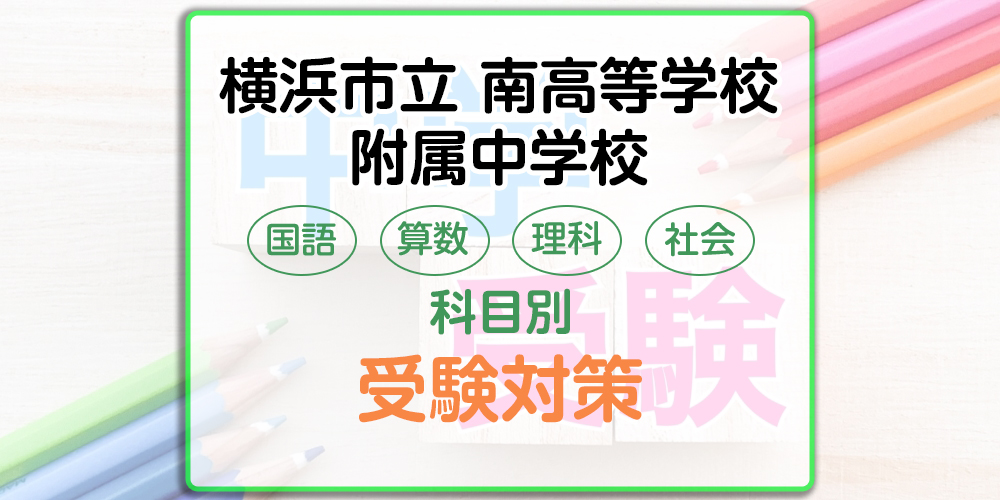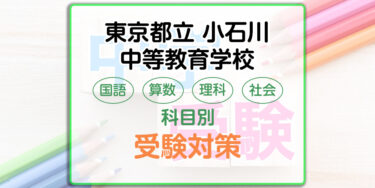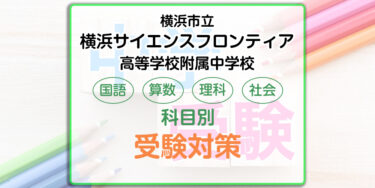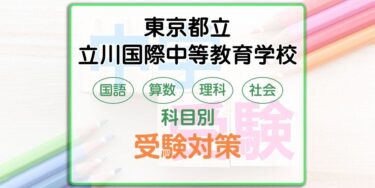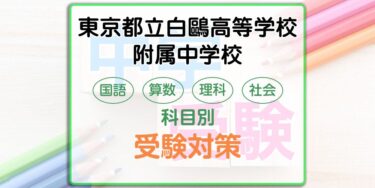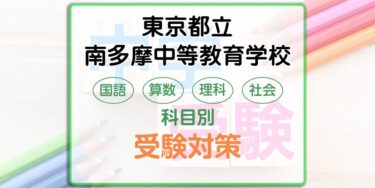横浜市立南高等学校附属中学校は「知性」「自主自立」「創造」を教育理念として掲げる中高一貫校です。この記事では、横浜市立南高等学校附属中学校を目指す家庭に向けて、適性検査の出題傾向と勉強法を紹介します。
そもそも横浜市立南高等学校附属中学校ってどんな学校?

横浜市立南高等学校附属中学校は横浜市にある中高一貫校で、文理融合の横断的なカリキュラムを採用している学校です。6年間をかけて、国際社会および日本における課題の発見、解決ができるグローバル人材としての力を養っていきます。
総合的な探究学習の時間「TRY&ACT」でグローバルリーダーシッププログラムを採用しているのもこの学校の特徴です。「EGG期」と「実践期」のふたつに分けて、さまざまな取り組みを行っています。たとえば、国際交流であったり探究学習のゼミであったり専門家を招いての講演会であったりと、催しは多角的です。
市立校と聞くと、設備が充実しているイメージはないかもしれません。しかし、横浜市立南高等学校附属中学校には、トレーニングルーム、食堂、体育館、ホール、プラネタリウム、ハンドボールコート、テニスコート、グラウンド、柔道場、野球場、理科実験室、書道室、図書館など、多種多様な設備が整っています。
進学においても一定の結果を出していて、難関国公立大学(東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、東京科学大学、一橋大学、名古屋大学、大阪大学、神戸大学、広島大学、九州大学、国公立医学部)のいずれかへ進んだ生徒は、2025年度だと現役24名、既卒2名です。
なお、2026年度からは附属中学校からのみの募集となり、高校からの募集はなくなると発表されています。
横浜市立南高等学校附属中学校の入試概要
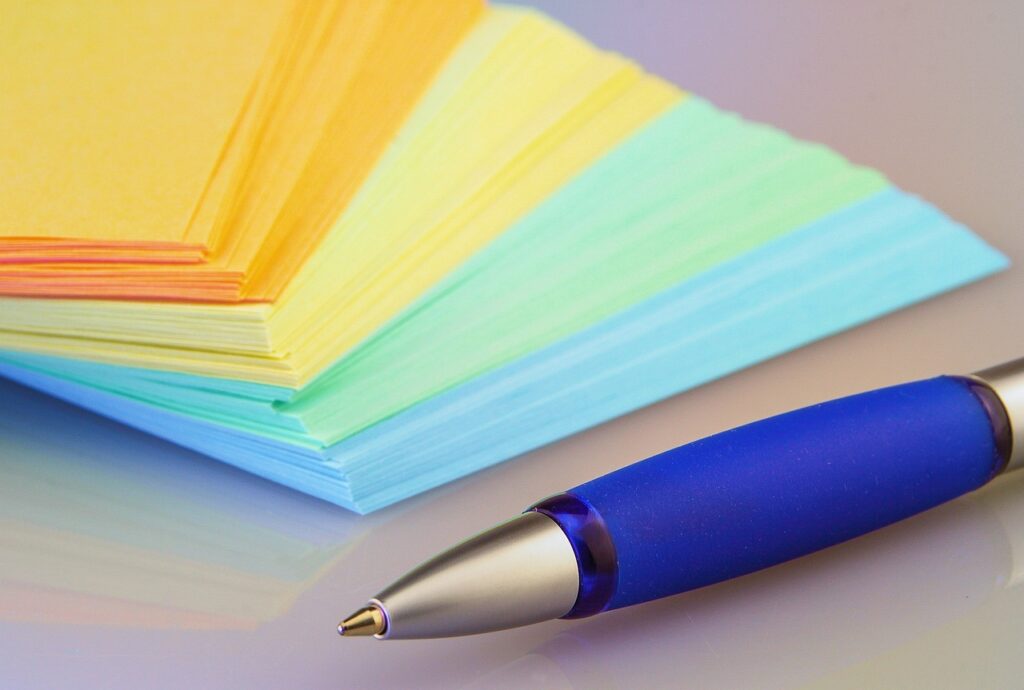
横浜市立南高等学校附属中学校の入試について見ていきましょう。
2025年度の入試
2025年度の募集人数は160名で、2月3日の実施でした。ウェブサイトによる出願期間は2024年12月23日月曜日から2025年1月6日まで。出願書類の提出期間は2025年1月7日から1月9日までに設定されていました。
2025年度の入試倍率
2025年度は、受検者数755名、合格者数160名で実質倍率は4.7倍でした。 2024年度は受検者数667名、合格者数160名で実質倍率は約4.2倍でしたので、前年度に比べて上がっています。なお、実質倍率の小数点第二位以下は四捨五入しています。
| 入試年度 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 755名 | 160名 | 4.7倍 |
| 2024年度 | 667名 | 160名 | 約4.2倍 |
横浜市立南高等学校附属中学校における適性検査の出題傾向
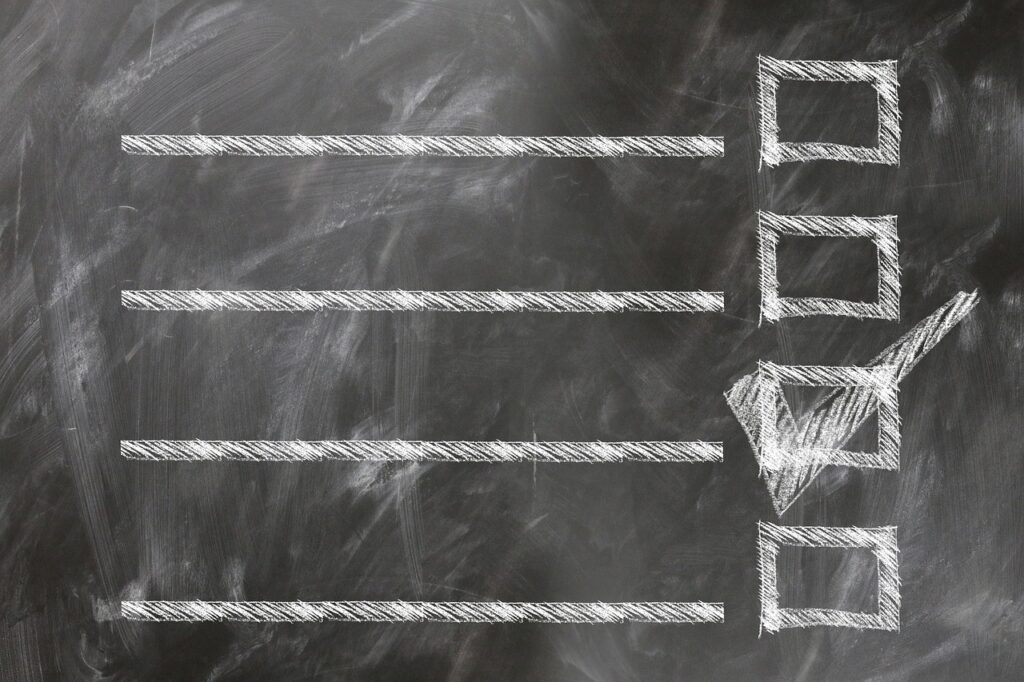
横浜市立南高等学校附属中学校の適性検査における出題傾向は以下のとおりです。
資料から情報を読み取る力が求められる適性検査Ⅰ
適性検査Ⅰの制限時間は45分で、配点が100点、大問が二つです。2025年度の適性検査Ⅰは社会がメインで、みなみさんとフランスからの留学生であるポールさんの会話形式で出題されました。歴史の分量が多めで、現代社会や地理の問題も出題されています。問題の中にたくさん資料が組み込まれていて、資料から必要な情報を読み取る力があるかどうかや思考力が問われます。最後の二問は170字以上200字以内の記述で、文章の要点をまとめる能力が求められました。
適性検査Ⅱは問題数が多くスピードが必須
適性検査Ⅱは制限時間が45分で、配点が100点、大問は四つです。適性検査Ⅰに比べると設問を理解し処理する力が求められます。適性検査Ⅰが社会や国語なら、適性検査Ⅱは算数や理科に近いといえるでしょう。小問の数は20問で、解答欄の数だと32個なので、スピーディーに解かなければ終わりません。処理能力といっても、素早さだけで勝負できるような単純な問題ではないので、一問一問ミスしないように解いていく姿勢が必須です。
- 適性検査Ⅰでは思考力が問われ、適性検査Ⅱではスピードが求められる
横浜市立南高等学校附属中学校に合格したい。どんな勉強が効果的?

横浜市立南高等学校附属中学校に合格するためには、どういう勉強をするべきなのでしょうか。科目別に見ていきましょう。
国語の勉強法
国語にはどう取り組めばよいのでしょうか。
文章を読み飛ばさないようにしよう
長い設問ばかりなので、文章を読み飛ばさない練習をしておきましょう。特に本番は気が焦ってしまうため、問題文の斜め読みをしてしまう子供が出てきます。そうすると、設定された条件を見落としてしまったり、設問の意図を早合点してしまったりといったミスが起きます。
文章を要約する力を身につけて
文章の大切なポイントを拾い上げる作業が苦手な子供はたくさんいます。なにを言いたい文章なのかを見抜く目が必要です。
問題集で読解文が出てきたら最初に要約をする時間を設けてみてください。10分以内に文章をまとめる練習です。
いきなり「さあこの文章の要約をしなさい」と言われてできる子供はあまりいないので、形式段落に番号を打ち、各段落の要点をまとめるところから取り組んでみるとよいでしょう。次に意味段落ごとに分ける練習をします。それから、要約をするようにするとスムーズです。
文章の添削は専門家にお願いしよう
記述問題を自己採点していると、意外と見落としがあります。本番で失点につながりかねないので、記述問題は専門家に採点してもらったほうがよいです。特に字数が多い記述問題は、そのつもりがなくても冗長な文章になっているケースが多くあります。また、キーワードが拾えているか、「てにをは」が正確か、文末表現が適切かなど、チェックするべきポイントはたくさんあります。自身の解答が、基準をクリアしているかどうか模範解答だけを見て判断するのはおすすめできません。
適性検査Ⅰに出る記述で得点できるように
点差がつきやすいのは、なんといっても適性検査Ⅰに出題される記述問題です。2025年度は170字以上200字以内が二問、2024年度は340字以上400字以内が一問でした。まとまった字数で文章を書かなければならないので、読解力や要約力、記述力が必要です。
この長さの文章を過不足なく書ければ、配点が高い分かなり有利に働くので、しっかり対策しておきましょう。
記述にかかる時間を読めるようにしよう
長めの記述問題は点差がつきやすいにもかかわらず、最後に出題されています。そのため、自分が該当の字数の記述に、どのぐらいの時間を使うかを把握していないと時間配分を間違えてしまいかねません。配点が大きい問題で解ききれないまま終わってしまうわけにはいかないので、過去問をはじめ類題で練習してください。
- 日頃から文章を読み飛ばさない習慣をつける
- 記述問題の解答は必ず添削してもらう
- 過去問を解いて時間配分を身につけておく
算数の勉強法
算数にはどう取り組めばよいのでしょうか。
各単元を解くための基礎を固めよう
私立中学の入試とは異なり、難問が出題されるわけではありません。まずは学校で習う各単元の内容を確実に理解することが必要です。学校で算数を習っていると、子供がつまずきやすい単元がいくつかあります。それは大きな数であったり割合であったりします。四則計算も複雑なものにはつまずきやすいです。図形問題も苦手な子供が多い単元だといえるでしょう。特に立体図形は解き慣れていないと、なかなかイメージを描くことができません。
集中的に問題をこなして実力をつけることは大切ですが、時間が経つと忘れてしまうため、復習もまた欠かせません。何度でも頭に入れ直すようにしましょう。
時間を意識して解くことが大切
どの科目もそうですが、とりわけ算数では時間を意識して解くことが大切です。ゆっくり時間をかければ多くの問題は解けますが、本番の限られた時間内では通用しません。常に本番の制限時間内でも解けるのかどうかの視点を持つようにしましょう。
問題文が長い問題に慣れよう
問題文が長いものが多いです。たとえば、2024年度の問題では十進法について出題されています。会話文形式の導入を読み込んだ上で、問題を解くという構成でした。じっくり読まずに、これまでの経験則で反射的に解いてしまう子供は一定数います。長い問題文を見るとそれだけで混乱してしまい、落ち着いて解けなくなる子供もいます。最後まで問題文を読み込む習慣を身につけなければなりません。
- 学校で習う内容を確実に理解しておく
- スピード感を持って解き進める練習をする
- 問題文を最後までしっかりと読む習慣をつける
理科の勉強法
理科にはどう取り組めばよいのでしょうか。
各単元の基礎知識を定着化させよう
全体的に奇をてらうような問題は出ません。基本的な知識を理解した上で解く問題ばかりです。問題文が長いため、難しく見えるかもしれませんが、問われている内容は平易なので、確実に解けるだけの知識をとりこぼしなく身につけておくことが大切です。
実験の問題が多数出題
理科は実験の問題が多数出題されています。実験の内容や図表が提示されるので、情報を追いかけながら、整理していってください。
たとえば、複数の物質の反応を比較するといった問題が、過去には出題されています。図表などで条件を整理してくれている問題も多いですが、文章だけだとどれがどれだったかわからなくなり、混乱することもあるでしょう。焦らずに読み込んで解いていきたいところです。
できるだけたくさんの実験問題を解いて基礎となるパターンをインプットしておきましょう。
計算が必要な実験も
計算をして答えを出すタイプの問題もよく出ます。四捨五入をはじめ、各問題で設定されている条件を確認し、正確な答えを書くようにしましょう。
- 基礎知識を確実に定着させておく
- 実験の問題を多くこなしてパターンを頭に入れておく
社会の勉強法
社会にはどう取り組めばよいのでしょうか。
知識を問う問題では失点しない
基本的な知識を問う問題も出題されます。そうした問題では正答率が高いと予想されるので、失点してしまうと大きく差がついてしまいます。教科書を通して習った内容を覚えておきましょう。
思考力を問う問題のほうが多い
全体的には知識を問う問題よりも思考力を問うタイプの問題のほうが多いです。問題文の中にさまざまな情報が落とし込まれていて、地図やグラフ、図表などが出題されます。設問を読み込むことで情報を整理して、答えていくタイプの問題です。問題の中に手がかりが隠れているので、ひとつひとつを洗い出していかなければなりません。
また、提示される情報が多く処理するのに時間がかかる分、自信がないとなんとなく解けない気分に陥ってしまいがちです。簡単なことを聞かれているのに、混乱してどの情報を拾い上げて考えればよいのかがわからなくなります。似たような形式の問題を解いて、成功体験を積み重ねていくのも大切なプロセスです。
歴史の知識や地図の知識
歴史の問題はよく出題されます。複数の選択肢の中から適切なものを選ぶ問題が頻出なので、基本的な知識を固めて受検本番まで抜けがないようにしておきましょう。どの時代にどういう出来事があったのかを、前後のつながりとともに頭に入れておいてください。忘れていそうな単元があれば、その都度覚え直していきましょう。
また、条件に該当する県名を問うといった地図に関連する問題も出題されています。地図は地理の基礎ですから、県名や県庁所在地、山脈や盆地の名前などの基礎知識は頭に入れておいてください。
グラフや図表を読めるようにしておこう
雨温図をはじめ、さまざまなグラフや図表が出題されています。グラフや図表の見方に慣れておきましょう。
- 教科書をしっかりと読み込み知識を入れておく
- 過去問を通して問題分の中からヒントを見つける練習をする
- 歴史は前後関係を意識した覚え方をする
長い問題文や資料の多い問題をたくさんこなそう
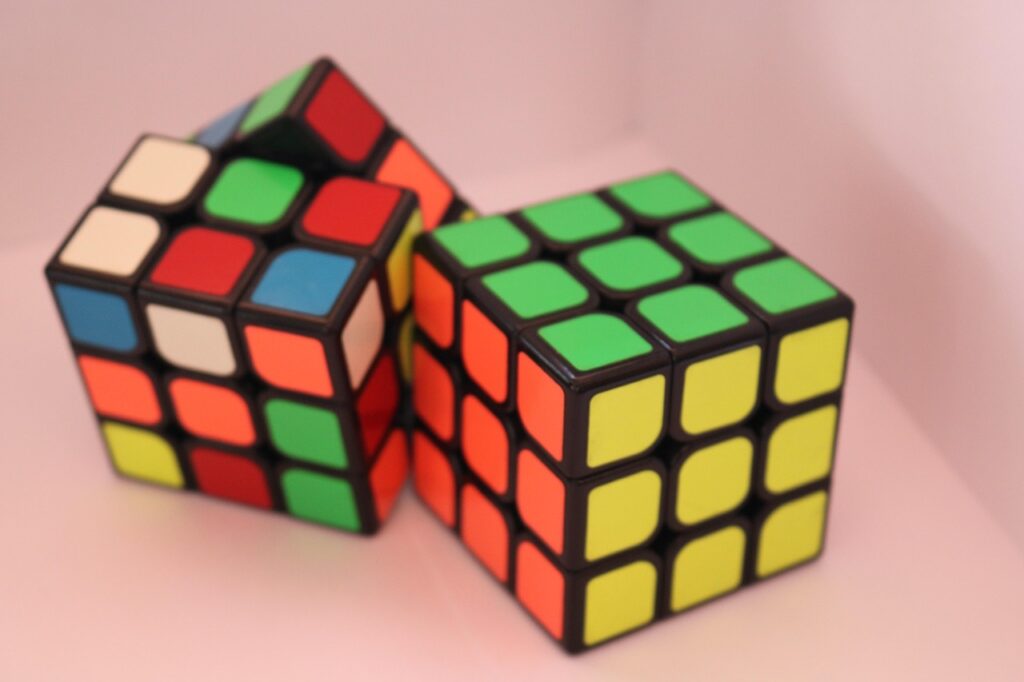
問題文や資料が多いので、圧倒されないように類似する出題形式に慣れておきましょう。思考力を問うタイプの問題が多く、見慣れないテーマも少なくありませんが、問題文をしっかり読み込めば解くためのヒントを見つけられるはずです。
公立中高一貫校の問題らしく、記述力を問われる問題が多く出ます。特に、適性検査Ⅰでは長い記述問題が出るので、設定された字数に対しどのように文章を展開すればよいのかを知っておくことが大切です。多くの子供は字数が増えるほど要点とはずれた文章を入れてしまう傾向があります。また、句読点を使うタイミングを間違えて、不自然なほど一文がダラダラと長くなってしまうこともよくあります。ぜひ塾講師や家庭教師に添削してもらってください。記述問題は自己採点だと問題点を見つけきれないことが多いです。
適性検査Ⅱでは限られた時間内での作業処理能力や思考力が求められます。冷静に問題を読むことができれば、持っている知識と文中のヒントで解ける問題が多いです。問題数が多いと、焦りから文章を読み飛ばしやすいので、ケアレスミスをしないよう注意しましょう。