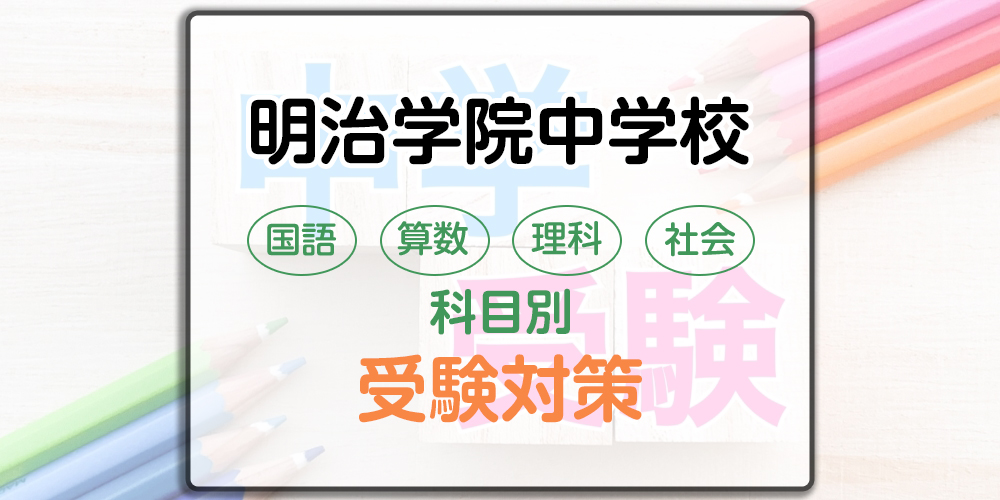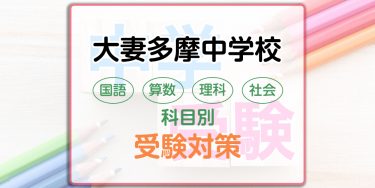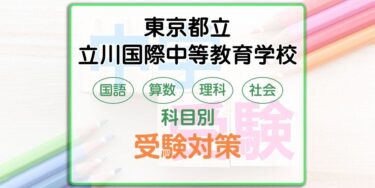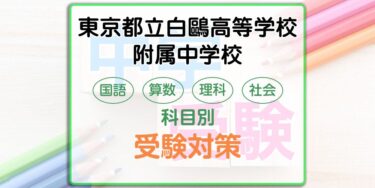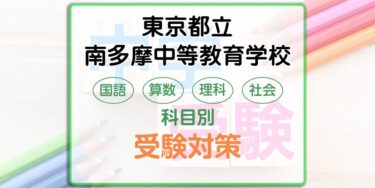明治学院中学校は英語に注力していることで知られる、キリスト教による人格教育を理念とする共学校です。この記事では明治学院中学校を目指す家庭に向けて、各科目の出題傾向と勉強法を紹介します。
そもそも明治学院中学校ってどんな学校?

明治学院中学校は学校法人明治学院が運営しています。学校法人明治学院が運営している学校は全部で四つあり、明治学院中学校の内部進学先である明治学院東村山高等学校。それから、白金にある明治学院高等学校。どちらの高等学校からも内部進学できる明治学院大学があります。中学・高校・大学までの一貫教育が特徴です。ちなみに、明治学院中学校から明治学院高等学校には内部進学できません。
2025年は115人が明治学院大学に推薦で進学しています。なお、2024年は132人が内部進学を選んでいました。内部進学以外では、2025年は中央大学、法政大学、日本大学、学習院大学、成蹊大学などへの進学率が高めです。
キリスト教の学校だけあって、キリスト教教育、英語教育、国際交流にも力を入れているのが特徴といえます。英語では、全学年で週六回、英語の授業が行われています。スピーチやエッセイライティング、英語劇なども行われていて、多角的な英語力育成を目指しています。ホームステイやウインターイングリッシュプログラム、進級予約留学制度といったさまざまな国際交流が用意されていて、国際感覚を育むことが可能です。
上から抑えつけるのではなく話し合いを重視した校風で、生徒の主体性を育んでいます。明るく伸び伸びと生徒が過ごせる環境です。土曜日は授業を行っていて、日曜日は部活等もありません。男女両方のカウンセラーが週四日、カウンセラー室を開いているため、メンタル面でのサポートも手厚いといえます。中学は1学年につき4クラス、1クラスは36人程度です。なお、高校は1学年につき6クラス、1クラスは43人程度で構成されています。移行生の男子25%、女子25%、新入生の男子25%、女子25%、計100%となるよう構成し、移行生と新入生が混ざり合う環境です。高2から文系コース、理系コース、高3から受験コース(理系)、受験コース(文系)、推薦コースに分かれています。施設としては6万冊以上の蔵書を誇る図書館があります。
明治学院中学校の入試概要
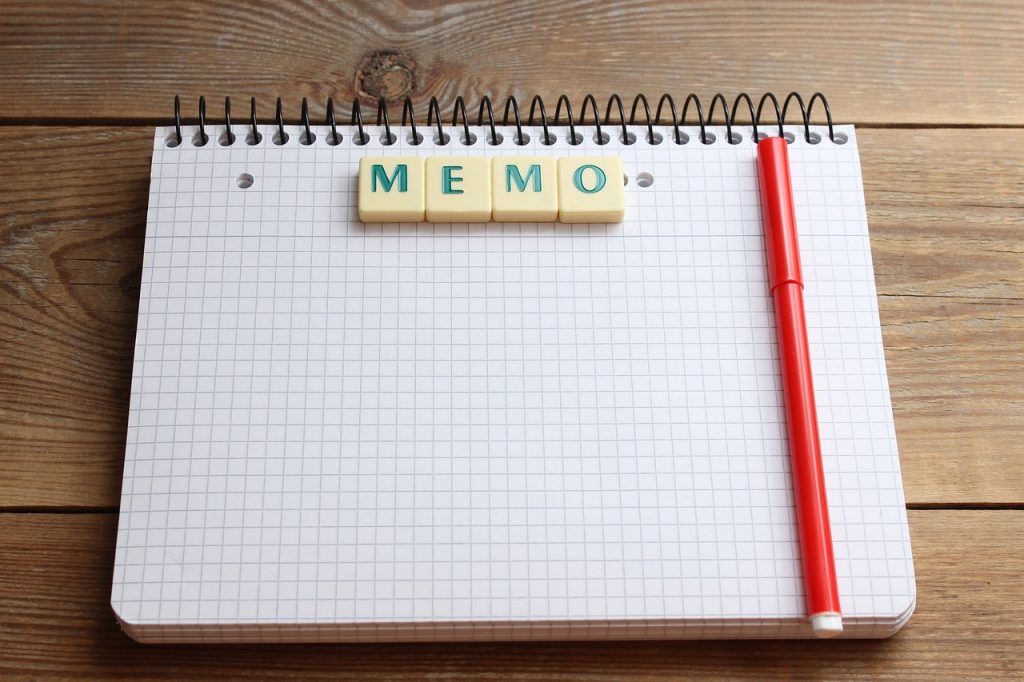
明治学院中学校の入試について見ていきましょう。
2026年度の入試
2026年度の入試は第一回が2月1日午後で男女合わせて約60名、第二回が2月2日午前で男女合わせて約60名、第三回は2月4日午前で男女合わせて約20名です。出願期間はどの回も2026年1月10日土曜日9時から開始。締め切りは第一回が2026年1月31日土曜日23時59分まで、第二回は2月2日月曜日7時まで、第三回は2月4日水曜日7時までに設定されています。第一回は国語と算数の二科目、第二回と第三回は四科目です。
2025年度入試との違いとして、募集人数の設定の仕方が挙げられます。2025年度は第一回から第三回まで、男女をそれぞれ半分ずつで人数設定されていました。しかし、2026年度は男女合わせた数しか設定されていません。なお、複数回分を一括出願した場合は、第一志望だとみなされ、繰り上げ合格で有利になります。受験料は一回なら25,000円ですが、二回分一括なら35,000円、3回分一括なら40,000円です。
2025年度の入試倍率
2025年度の入試は第一回の受験者が449名で合格者183名、実質倍率は約2.5倍、第二回の受験者が246名で合格者80名、実質倍率は約3倍、第三回の受験者が155名で合格者38名、実質倍率は約4倍です。
| 入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 第一回 | 449名 | 183名 | 約2.5倍 |
| 第二回 | 246名 | 80名 | 約3倍 |
| 第三回 | 155名 | 38名 | 約4倍 |
明治学院中学校における国語・算数・理科・社会の出題傾向
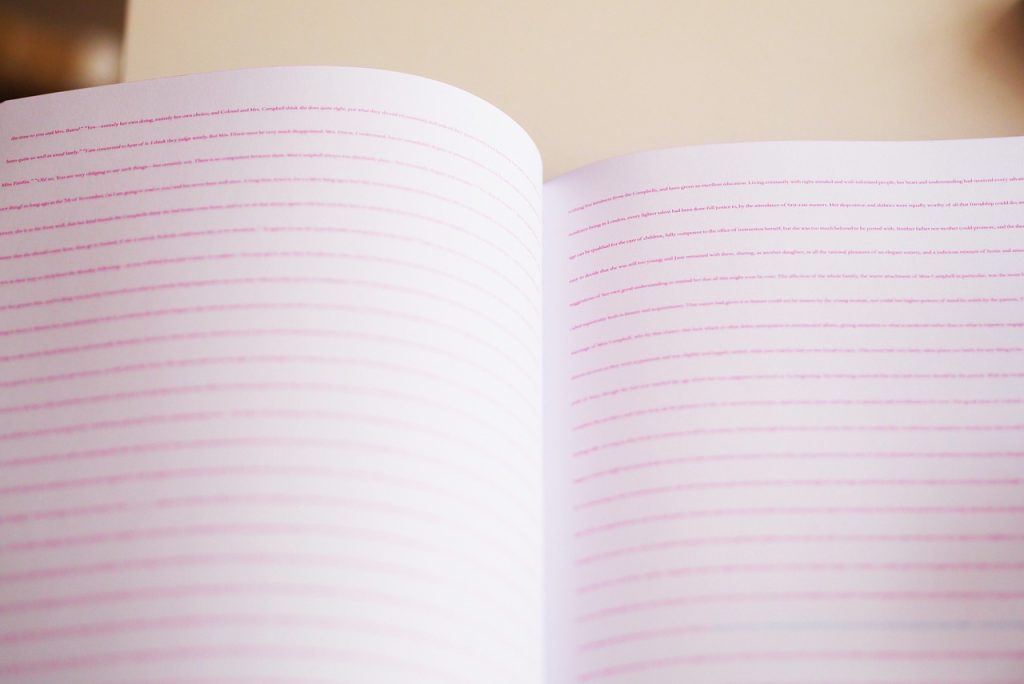
明治学院中学校における国語・算数・理科・社会の四科目受験の出題傾向を紹介します。
国語は選択問題がメイン
国語は試験時間が50分で配点が100点、大問は六つほどです。物語文や説明文、短歌や俳句と幅広い読解問題が出題されます。基本的に選択問題がメインです。書き抜きもあり、たとえば指示語がなにを指しているかであったり、ある一文を具体的に説明している箇所を抜粋する問題であったりが出ます。短歌や俳句も出題されるため、対策ができていないなら早めに取り掛かるとよいでしょう。知識問題も出題され、文法や漢字の読み書きなどの力が問われます。
算数は平易な問題が多め
算数は試験時間が50分で配点が100点、大問は六つほどです。算数の大問一は小問集合、大問二以下はテーマ別の出題となっています。一つの大問につき2.3問の小問が出題されます。頻出単元としては、四則計算、図形などが挙げられます。特に、図形は作図の問題が含まれるのが特徴です。大問一の小問集合では、計算問題が多く出ます。問題のレベルは標準的で問題文もけっして長くありません。
理科は図表・グラフが頻出
理科は試験時間が30分で配点が60点、小問によって構成されます。理科は各分野からの出題で、形式としては選択問題や適語補充などが多く出題されます。基礎知識を中心に問われることが多く、難易度が高いわけではありません。図表やグラフ、絵を見ながら解くような実験・観察の問題も多いです。化学や物理を中心に計算問題も出題されます。一問一分ぐらいの速度で解く問題数です。
社会は各分野からの出題
社会は試験時間が30分で配点が60点、大問は五つほどです。社会は各分野からの出題で、地理では地図や地形図、グラフなどがよく出ます。写真などの資料もあります。出題形式としては適語補充や正誤判定などがメインです。時事問題も出題されます。基礎知識を問う問題が多いので、全体的に難易度は低めです。分野を横断する問題も出題されます。社会は問題文が比較的長めで、ひとつのテーマに基づいた文章や、会話文形式などさまざまなタイプの問題文があります。
- 全体的に標準的な難易度の問題が多いが、国語の短歌・俳句は早めに対策をしておく必要がある
- 算数は作図の問題が含まれ、理科・社会は一問一問にかけられる時間が少ない
明治学院中学校に合格したい。どんな勉強が効果的?
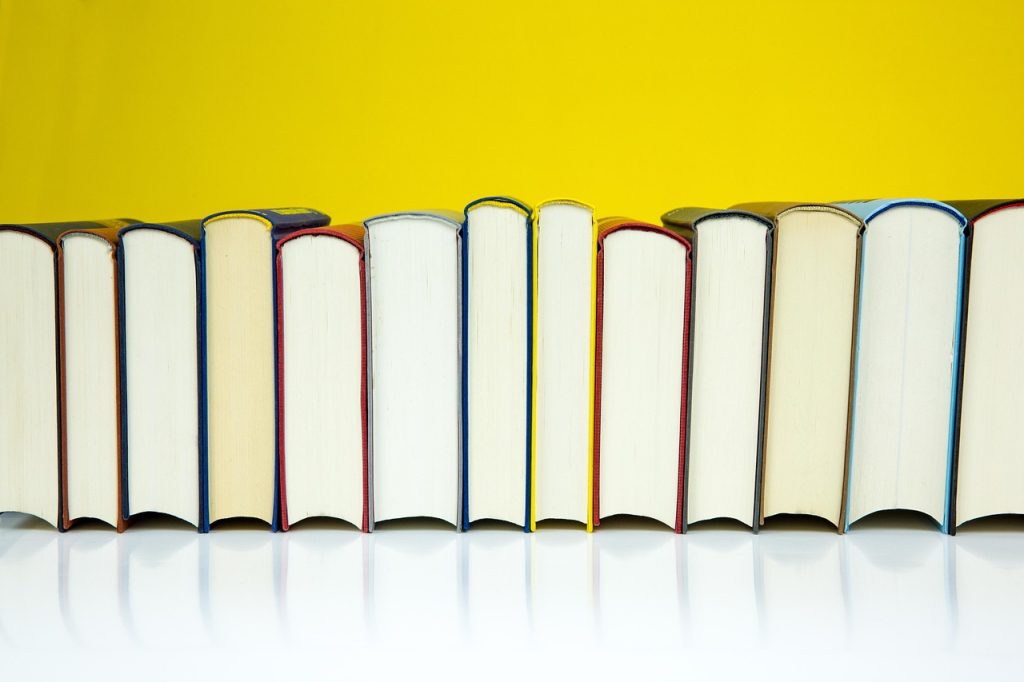
明治学院中学校に合格するためには、どういう勉強をするべきなのでしょうか。科目別に見ていきましょう。
国語の勉強法
国語にはどう取り組めばよいのでしょうか。
国語は韻文まで対策しておこう
読解文というと、どの学校も説明文や物語文からの出題が多いため、韻文の対策は疎かになりがちです。しかし、明治学院中学校では出題されるので、きちんと対策して臨みましょう。韻文では韻文そのものではなく、韻文の感想を読んで解く問題も出題されています。たとえば、いくつかの感想の中から詩の読み取り方が間違っているものを選べといった内容です、
漢字の読み書き対策もしておこう
漢字の読み書きが出題されるので、できるようにしておきましょう。書く際には、「とめ」「はね」「はらい」まで丁寧に仕上げてください。筆圧が弱い子供は、日頃から濃く書く練習をしておくことをおすすめします。漢字は子供自身は書けているつもりで間違っていることがよくあります。そのため、大人の目でチェックすることが欠かせません。
筆圧が弱い子供の中には一画一画をきちんと書かず、線と線を崩し字のようにつなげてしまうタイプも少なからずいます。そうした書き方で失点してしまってはもったいないので、早いうちから改めるよう指導しましょう。減点されてしまうような癖は早めに修正させたほうがよいです。字は言葉で伝えて即座に直るものではないため注意が必要となります。
読解を通して知識問題も出題される
読解問題の中にも、語彙をはじめとした知識問題が出題されます。適切なことわざ・慣用句を選ぶ問題や語彙の正しい意味を選ぶ問題などさまざまです。文中にふさわしい言葉を選ぶ問題も、言葉の意味が理解できていなければ解けません。
- 韻文が出題されるため対策が必須となる
- 漢字の読み書きは必ず大人がチェックするようにする
算数の勉強法
算数にはどう取り組めばよいのでしょうか。
四則計算をスムーズに解けるように
整数・分数・小数など、計算力を問う問題が出題されます。計算問題は六つ程度です。あくまで基本的な計算力が問われます。簡単な問題ばかりですが、式自体は長めなので、途中で計算ミスをしないよう気をつけるようにしましょう。
図形問題は作図できるように
作図含めて、図形問題は頻出なので、必ず解けるようにしましょう。過去には「長方形の周りを移動する円の中心が通ったあと」や「円の接線を複数書き、接点を結んで三角形を作る」といった問題が出題されました。基本的な作図について勉強しておくことをおすすめします。
場合の数や数の規則性の問題に対応できるように
場合の数や数の規則性の問題も出題されています。標準レベルの問題が解ける実力があるかどうかを問う問題が多いです。そのため、受験問題集の標準レベルまで解けるようにしておいてください。
速度の定番の問題に慣れておこう
速度の問題では、途中で速度を変える問題や、あとから先に出た人を追いかける問題などが出題されています。受験問題集の定番の問題で解けないものがあれば、自力で解けるまで解き直しておいてください。
- 基本的な作図を確実に解けるようにしておく
- 速度は定番の問題が解けるように問題集で慣れておく
理科の勉強法
理科にはどう取り組めばよいでしょうか。
問題文の条件を押さえて
理科では観察や実験の問題がよく出るため、計算問題も解けるようにしなければなりません。計算問題の中では小数の答えになる問題も多く、「小数点第一位で四捨五入」といった条件が提示されているケースもあります。条件を確認して計算問題を解くようにしましょう。
計算問題は作業的に解けるように
計算問題は標準的な問題が出題されるので、解けるようにしておいてください。たとえば、熱平衡の問題や、音の速さの問題、ばねの計算、水の温度変化の問題などが出題されています。
問題数に対応できるようにしよう
理科は小問で二十問ほど、解答欄で三十問ほど出題されることがあります。時間的には単純計算で一問一分ですから、スムーズに解けるようにしましょう。選択問題や適語補充がメインなので、時間のかかる問題は基本的には計算問題ぐらいです。
- 時間がタイトになるため計算問題をスムーズに解けるように標準レベルの問題を多くこなしておく
社会の勉強法
社会にはどう取り組めばよいのでしょうか。
ひとつのテーマに基づいて考える
公民分野ではたとえば、「税金」といったようにひとつのテーマに基づいて考えさせることが多いです。知識を問う問題、消費税を計算させる問題、テーマと関連づけて憲法について問う問題などさまざまな問題が出題されました。
思考力を問われる記述問題も答えられるように
記述問題の中には、思考力を問うような問題もあります。たとえば、「小学生以下にだけ消費税があったと仮定してどのような問題が起こり得るか」を書かせる問題が過去にはありました。もしこうだったら、と想像力をたくましくする力が求められます。
地理はデータを頭に入れて
地理は、各地域の農産物や特産物や工業などのデータを頭に入れておく必要があります。雨温図をはじめ土地ごとの特徴への理解を深めておきましょう。
地図や地形図と関連づけた出題
地図や地形図と関連づけた問題などが出題されています。地図は県や市、代表的な地名が頭に入っていることが前提の問題です。地形図は、等高線や土地の利用のされ方について答えたりします。地形図を正確に読めるようにしておきましょう。
- 思考力を問う問題も出るため仮定の話を想像してみる習慣を付ける
- 土地ごとの特徴や代表的な地名は必ず覚えておく
明治学院中学校の入試では標準的な問題で失点しないように

明治学院中学校では奇をてらったような問題や、難問は基本的に出題されません。いかに中学受験テキストに載っているような問題を解けるかが問われます。
国語では物語文や説明文、韻文など読解文が出題されます。韻文は出題される学校が限られるので、対策しておいてください。漢字の読み書きをはじめ知識問題もたくさん出題されるので、対応できるようにしておきましょう。
算数は基本的な四則計算にはじまり、各単元での標準的な問題が出題されます。問題自体の難易度がそれほど高くない分、一問一問、時間内に確実に解かなければなりません。
理科は観察・実験を中心に各分野の問題が出題されます。計算問題も多く出題され、スピーディーかつ確実に解くことが必要です。一問あたり一分程度で解かなければならないので、ケアレスミスなく解けるよう問題に解き慣れておいてください。
社会は設定されているさまざまなテーマに基づいて考えます。中には思考力を問われるような問題も出題されるので、過去問に取り組んで慣れておいてください。日頃から物事の背景を考えられるとよいです。地図や地形図は読めるようにし、資料集にも目を通して知識を増やしておいてください。