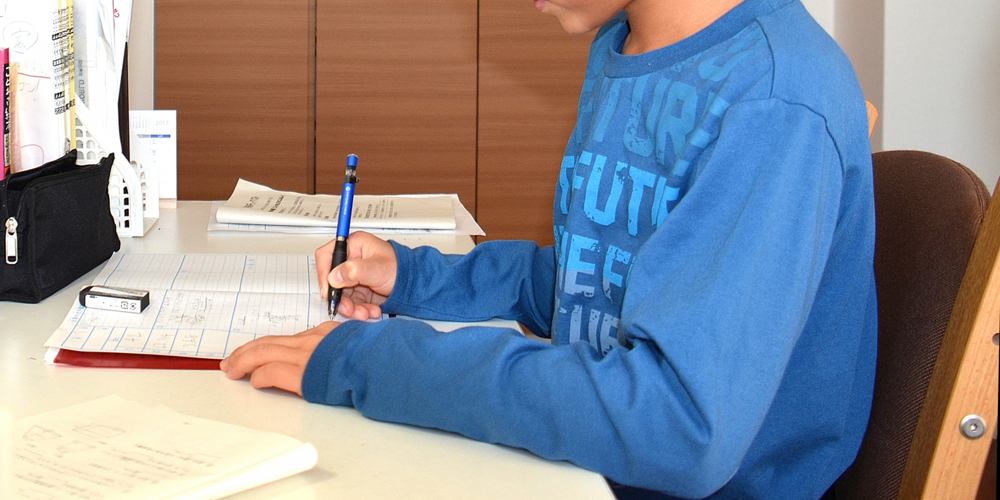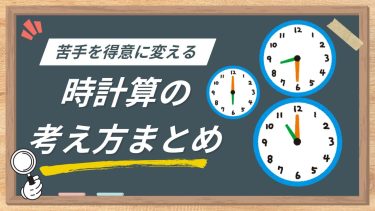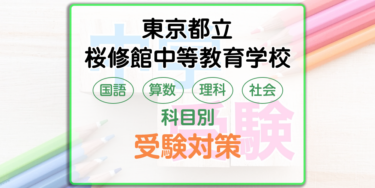中学受験対策において、多くの子供たちが秋頃から過去問に取り組み始めます。実際やってみて、思った以上に点数がとれずびっくりする家庭も多いのではないでしょうか。この記事では、中学受験本番直前になっても点数がとれず、悩んでいる家庭に向けて対処法を紹介します。
そもそも、過去問はいつ頃から始めるのが正解なの?

基本的には10月頃から始めます。ただし、夏ごろから始めている子供も少なくありません。夏は夏期講習のカリキュラムを理解するのが最優先なので、基本的には過去問は秋スタートで大丈夫です。しかし、夏休みに子供の気の緩みが目立つようであれば、あえて第一志望校の過去問を解かせてみるのもよいでしょう。よほど余裕のある子供を除いて、合格ラインとはほど遠い点数が出るはずです。気を引き締めるための一助となります。
過去問に初めて挑戦する際に気をつけるべきこと
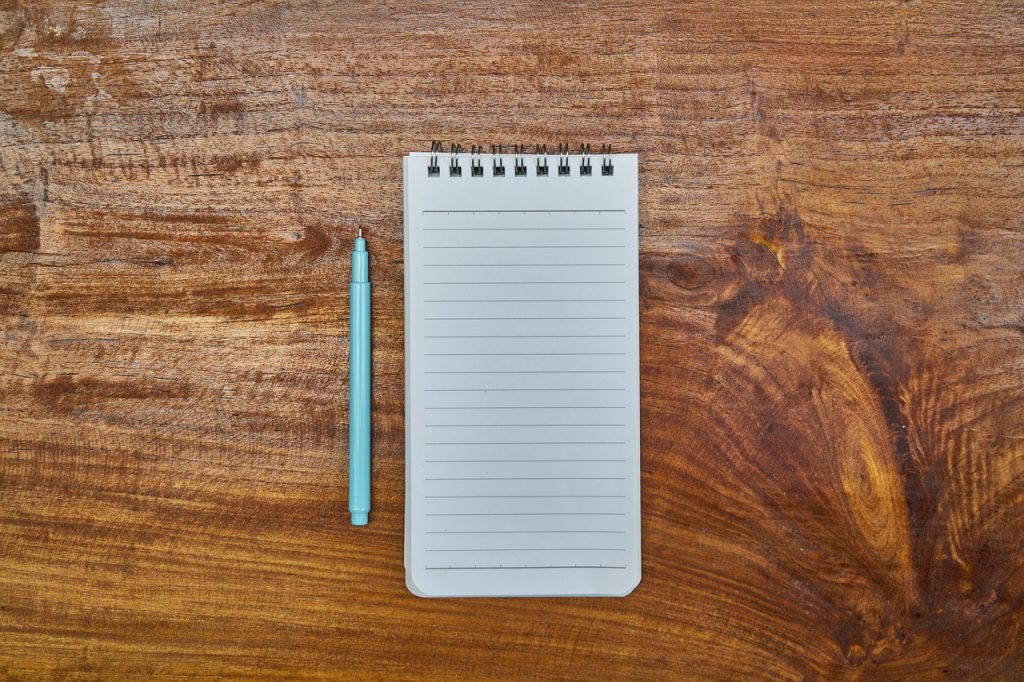
当日と同じ制限時間で解くことが大切です。タイマーをかけておき、時間厳守で問題を解きます。採点が終わった後は、間に合わなかった問題およびミスした問題を全て解き直してください。ミスした問題に関してはミスの原因を分析し、他の問題集から類題を探して解いてみるとよいでしょう。ミスした箇所には日付を入れておくと見直しのときに便利です。
10月の段階であれば、おそらく合格ラインの半分も点をとれていないケースが少なくないでしょう。現実を直視し対策を練る必要があります。なお、この時期に過去問の点数が悪いのは当然のことなので、わが子の点数が悪くても動揺せずに、「他の子もこの時期はこんなものだよ」と温かく声をかけてあげるとよいでしょう。
冬になっても過去問の点数がとれない!志望校は大丈夫?

12月時点ではどの程度、過去問が解ければよいのでしょうか。点数があまりに低い場合の対処法とあわせて紹介します。
12月における過去問の出来の目安
10月に過去問の点数がとれないのは仕方ありません。しかし、12月時点では合格ラインにこそ届かなくてもある程度の点数をとれるようにしたいものです。具体的には合格ラインの7~8割が目安です。7~8割とれていない子供は、過去問でミスした問題をきっちりやり直せていない可能性があります。解答を読んでわかったつもりになってしまったのかもしれません。自力で解けるレベルに再度仕上げてから類題にも挑みましょう。自力で類題を解けて初めて本当の意味で理解できたといえます。
12月からの過去問の勉強法
12月からは合格ライン到達に向けて、よりポイントを絞って勉強を進めていかなければなりません。一番に優先すべきは第一志望の過去問でつまずいた問題です。しかし、ミスの解き直しを指示された子供は「やり直しても、同じ問題はぜったいに出ないよね。無駄じゃない?」と怪訝な顔をよくします。同じ問題が二年連続出るわけではないのはそのとおりですが、似た傾向の問題が出る可能性はありますし、他の受験校で出題される可能性もあります。過去問への取り組みを自己満足で終わらせずに、着実に実力アップへつなげることが大切です。
解く時間は足りなくて当たり前
とりわけ、算数で顕著ですが、受験問題を解いていると時間が足りなくなりがちです。それもそのはずで、そもそも全問解き終わることを想定して問題が作られていません。つまり、確実に点数をとるためには「どの問題を捨てるか」の判断が重要になります。正答率が低く時間がかかる問題がどういうものなのか、あらかじめ知っておきましょう。いわゆる「捨て問」です。捨て問は学校ごとの傾向がありますから、例年どのレベルの問題がどのあたりで出題されているかを確認してください。
過去問で点数を落としやすいポイントって?各教科の対策は

過去問をやる上で、点数を落としやすい教科別のポイントは以下のとおりです。
国語はコツを学んで挑むべき
国語では点数をとるためのコツを学ぶ必要があります。以下紹介します。
国語の記述問題は減点ポイントを知っておこう
過去問を通して記述問題が、どのぐらい出題されるかを知っておきましょう。配点が高いにもかかわらず記述問題が苦手な子供は多いです。基本的なルールが守れていないため、細かく減点されるケースがよくあります。
たとえば、理由を問われているのに、記述問題の文末が「から」や「ため」で終わっていない答案はNGです。「〇文字以下で述べよ」とあった場合、やたらと短くまとめてしまう子供がいますが、これも減点対象。指定された枠の最後の行まで書くつもりで臨みましょう。
文体も大切です。敬体と常体が混ざっていたり、句点が何度もはさまれて文意のとりづらい文章は減点対象になります。また、比喩法を用いて「ように」を連発している解答も減点対象です。「この」「その」「あれ」など不必要な指示語を多用している文章も減点されます。記述問題に取り組む際は、採点者の目線を意識してみてください。一読してわかりやすいかどうかを考えなければなりません。
国語では傍線を引くクセをつけて失点を防ぐ
記述問題だけではなく選択問題でも油断は禁物です。たとえば「正しいものを選べ」「間違っているものを選べ」といった出題の意図を真逆に取り違えて、ミスするケースがよくあります。
だいたいの子供は「本当はわかっていたんだけど、うっかりしていた」と言うのですが、こうしたケアレスミスが一度限りで終わることはまずありません。ミスを減らすための具体的な努力が必要です。おすすめなのは、解きながら問題文に線を引くクセをつけるやり方でしょう。先ほど挙げた例であれば、「正しい」「間違っている」のところに傍線を引くだけでミスはぐっと減ります。ささやかな工夫ですが、一問一問丁寧に取り組む姿勢がミスを減らし、合否を分ける一点につながるのです。
これは問題文だけではなく本文においても必要な取り組みです。物語文を読んでいるのであれば、登場人物の気持ちを表すワードに傍線を引くようにしましょう。論説文であれば、冒頭部の問題提起、本文中の具体例、結論部分に傍線を引きます。それだけで内容への理解が深まりますし、問題を解く際に読み返す量がぐっと減ります。時間切れや見直し時間の不足を防ぐ効果的な手段といえるでしょう。
傍線を引くやり方は文章を読むのが苦手な子供にも最適です。読むのが苦手な子供は、目で文字を追えても情報を頭で理解するところまでなかなか持っていけないものです。線を引くと、少なくとも該当の部分だけは頭に残ります。
問題数の多い算数では注意深さと素早さの両立を
問題数の多い算数では、注意深さと素早さの両方が要求されます。
計算問題ではケアレスミスをいかに防ぐかがポイント
計算問題は配点が低いですが、得点しやすい問題です。それだけに確実に点をとれるかどうかが合否の分かれ目になります。
計算問題でミスをする子供に共通する特徴は、急ぐあまり途中式を省いたり、乱雑に書きなぐったりする傾向にあるということです。また、計算式をあちこちに書き散らすうちに順番がよくわからなくなっているケースも多く見られます。
受験では制限時間がありますから、気が焦るのは当然です。いちいち途中式を書いていたらタイムロスにつながり、時間内に終わらせることができなくなると考える向きもあるでしょう。それでも、自分の計算力を振り返って、最低限必要な式は書き出しておくことをおすすめします。なお、途中式を書いておけば見直しにかかる時間は短くなるはずです。
図形の問題で歯が立たない子供が多い
中学受験の算数において、平面図形や立体図形の問題はだいたいどの学校でも出題されます。しかし、図形の単元を苦手とする子供は非常に多いです。覚えなければいけない公式が多く、出題パターンも複雑。とりわけ立体図形はある程度問題に慣れていないと、上手く想像を膨らませることができません。
平面図形や立体図形の応用レベルの問題が出題されると、解法を見つけるだけでも時間がかかります。答えを出すまでの計算も複雑である問題が多く、たとえ問題自体を理解できていても途中でケアレスミスをする可能性が高くなります。
そのため、図形問題を制限時間内に解くにはいろんな問題を経験し、速やかに正しい解法に至る力を養わなければなりません。計算力も身に着けて確実に点をとる必要があるのです。
本来なら、図形の問題が苦手なのであれば、早めの克服が必要となります。中学受験本番間際に「図形が苦手だから今から復習するか」と取りかかることはハードルの高い挑戦と言わざるを得ません。
おまけに、図形問題の比重はどの学校でも高く、単元ごと捨てることはできません。いくら中学受験本番が近いといっても「図形は解けなくてもよい」と割り切るには、他で相当点数を取る必要があり現実的ではないでしょう。
図形とひと口に言っても広範ですから、満遍なくやり込むのは無理かもしれません。その場合、塾講師や家庭教師に、過去どういう図形問題が出題されているのかを分析してもらい、ヤマを張ってある程度解けるようにしておく必要があります。他の単元である程度点数がとれるなら、比較的簡単な問題だけでもよいので、受験までの残り日数を考えて取り組むべき問題を絞り込みましょう。
社会の過去問では、問題を解くためのヒントの出し方に注目
社会の仕上げは受験直前までかかる子供がほとんどでしょう。本番までに間に合えばよいのですが、スケジュールを組み間違えて、準備が追い付かない子供は毎年一定数います。
テキストを満遍なくやり込むのが難しくても、せめて頻出単元だけは終えるようにしましょう。よくテキストの最初から最後まで通しで見直している子供がいますが、前から順に進めていく必要はありません。塾講師や家庭教師に優先すべき単元を確認してください。
社会は、単元ごとの知識は頭に入っているけれど、横断的に考えることのできない子供が多く見られる教科です。しかし、中学受験に挑む上では、単元ごとの内容を線で結んで理解しなければなりません。
一例を挙げて考えてみましょう。ある地域について扱った問題が出題されたとします。国語のテストかと思うような長さの説明文で、文中の空欄を埋めていくスタイルです。まずは、気候や地形についての説明があり、説明されている地域がどこであるか推測しなければなりません。地域を特定したら、次に該当の地域の名産品や農作物、工業について答えていく流れです。社会科のテキストでは気候、地形、名産品、農作物、工業はそれぞれ別の単元扱いでした。しかし、受験問題は、各単元で習った内容をつなぎ合わせて考えなければ解けないのです。
過去問をやる際には、その学校のヒントの出し方を分析しましょう。たとえば、先ほど例に挙げた問題だと、気候や地形の理解を深めることが問題を解く上での第一歩になるといえます。問題を解くヒントになりやすい単元は優先的に固めておきましょう。
理科は出題傾向が比較的分析しやすい。単元を絞って追い込みを
理科は地学、生物、化学、物理と大きく四つのジャンルに分かれるため、子供によって「ここが苦手!」という箇所がはっきりしています。加えて、中学受験ではこの四つのジャンルから満遍なく出題する傾向にあるため、ひとつでも苦手なジャンルがあると大きく失点してしまいがちです。ただし、ジャンルとしては包括的でも、学校ごとによく出る単元には傾向があります。算数と並んで理科は傾向が把握しやすい教科です。すべてを固めるのが時間的に難しければ、よく出る単元のみに注力しましょう。
- 国語は問題文に傍線を引くクセをつける
- 算数の計算問題では必要最低限の計算式を書くクセを付ける
- 算数の図形問題は早めの克服が重要だが間に合わない場合は受験までの残り日数を考えてヤマを張る
- 社会は頻出単元を優先的に固めておく
- 理科は受験校の傾向を把握してよく出る単元に注力する
過去問で点数をとれないときは、焦る前に失点の理由を探そう

志望校の過去問で点数をとれないと、だいたいの子供がパニックになります。今まで勉強を頑張ってきたのに、「合格できないラインにいる」と数字で突きつけられてしまい、自信を失ってしまうのです。「こんなに点数がとれないなら、もういいや」と嘆いて問題を放り出してしまう子供も珍しくありません。
しかし、失点の理由を分析しないなら、過去問に取り組む意味はほとんどなくなってしまいます。ぜひ合格するにはなにが足りないのか、本番までにどこまで解けるようにすれば合格できるのかを考えてみてください。記事でまとめた対策ポイントを押さえ、自分に必要な要素はなにかを考えて、確実に点がとれるよう仕上げていきましょう。