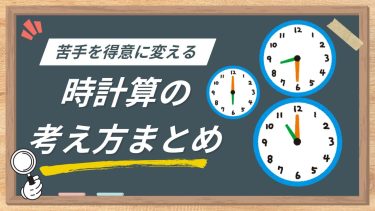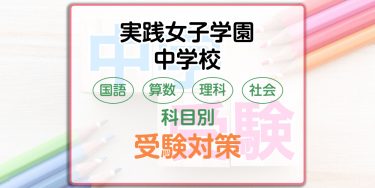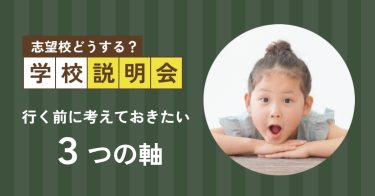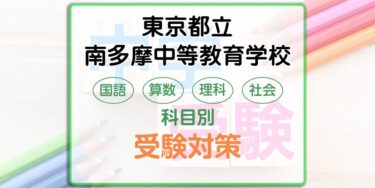志望校を決めるのは難しいものです。いざ入学したあとに後悔するケースもよくあります。この記事では、志望校を決めるにあたり、重要な3つの軸を紹介します。
志望校の決め方で多いパターンは

志望校の決め方で最も多いのは、偏差値から決めるパターンです。一番レベルの高い学校を第一志望に据え、第二志望以下は日程と偏差値のバランスで決めていきます。
この場合、第一志望を決める主体は保護者であることが多いです。子供自身が、「〇〇中学校に行きたい!」と積極的に意思表明するケースは少数派でしょう。
POINT!!
保護者主導の決め方では、校風やカリキュラムが合っているかどうかはあまり検討されていないという問題があります
出願校・受験校の平均は何校ぐらい?

出願校・受験校の平均数については、調査によって結果に開きがあります。地域や偏差値によっても差があるため、一概に「このぐらい」とは言えません。小・中・高学費ナビによると、サピックスでは2025年度の平均出願校数は8.9校、平均受験校数は6.2校です。おそらく「予想より多い」と感じる家庭のほうが多数派でしょう。出願校・受験校ともにサピックスの半分程度のケースも珍しくありません。特に、地方では首都圏のように選択肢が多くないため、もっと少ない数になります。
第一志望と併願校の選定はどうするの?

第一志望と併願校の選定はどのようにすればよいのでしょうか。
受かっても行かない学校は選択肢から外す
第一志望は本当に行きたい学校を選びます。自分のレベルより高くても問題ありません。挑戦するつもりで設定しましょう。併願校は、塾や家庭教師の先生に相談し、滑り止めを設定します。ただし、行きたくない学校を無理やり受ける必要はありません。受かっても地元の学校を選ぶのであれば、意味がないためです。極端な例を挙げるなら、子供が「第一志望に落ちたのなら地元の学校に行かせる」と決めていて、親子間で同意しているのであれば、第一志望だけの受験でよいでしょう。ただし、第一志望の前に一校、練習で受けておいたほうが試験慣れできます。
併願校の決め方
第一志望はややレベルの高い学校、第二志望は実力相応の学校、第三志望以下が安全校というのが基本的な決め方です。安全校は複数設定するのが一般的で、なにかあった場合に備えます。
全落ちを避ける
中学受験を目指す子供の中には、当然全落ちするケースも出てきます。しかし、全落ちはどの家庭もなるべく避けたいところでしょう。全落ちを避けるために大切なのが、併願校選びです。塾や家庭教師の先生からアドバイスをもらって、確実に受かる安全校を複数組み込んでください。体調不良や問題との相性で合格圏内でも落ちるケースはあるので、確実な滑り止めを複数用意します。
全落ちが子供に与える影響って?
全落ちを経験した子供の中には、強い挫折感や無力感に打ちのめされてしまうケースもあります。長い期間、引きずってしまう子供も珍しくありません。子供の心理的負担の大きさを考えると、回避するのが望ましいでしょう。
家庭の方針として、あえてレベルの高い併願校だけ受けさせる場合は、地元の公立校に行く可能性のある旨を子供とあらかじめ共有しておいてださい。
POINT!!
「地元の公立校へ行くのも選択肢のひとつ」なのだとしっかり伝えておくとよいですよ。
学校説明会に行く前に3つの軸を設定しよう

志望校を決める際に参考になるのが学校説明会です。なるべく多く参加したほうが情報が得られてよいのですが、親も多忙であり、手当たり次第参加するのは現実的ではありません。学校説明会に行く前には3つの軸を設定して候補を絞り込んでみましょう。
6年間を見据えて別学(男子校・女子校)・共学の選択を
別学・共学にはそれぞれの魅力があります。わが子がどういう環境で学びたいと考えているのか、またそれはどういう理由によるものなのかを確認しておきましょう。中高一貫校であれば6年間同じ環境に身を置くわけですから、話し合いは大切です。
保護者の多くは「とにかく受かった中で、一番偏差値の高いところに入れよう」と結論づけています。しかし、「別学か共学か」は、志望校を選ぶ上で子供にもわかりやすいポイントです。子供自身が「こうしたい」という希望を持っているケースも多いので、親だけで決めるのではなく子供の意見も聞き、そう考えるに至った背景を共有しておきたいところです。
学校説明会では各学校の校風について説明がありますから、改めてどういう学校がわが子に向いているのかを考えたいところです。
POINT!!
別学か共学かは校風にも大きな影響を与えます
自主自立タイプか、面倒見のよいタイプか
学校の校風において、学業成績に大きく関係するのが「自主自立タイプ」なのか、「面倒見のよいタイプ」なのかという点です。学校側は学習に対しどういうスタンスなのかを確認するようにしましょう。どちらがよいということではなく、わが子にはどちらが向いているかということです。
面倒見のよい学校では、小テストや補習授業が充実しています。塾に通う必要がまったくないぐらい、手厚く学校で面倒を見てくれるところも少なくありません。中には、手厚いというより厳しいと感じるレベルの学校もあります。
一方、自主自立を重んじる学校には大きく分けてふたつのタイプがあります。ひとつは、生徒の側が求めれば様々な選択肢を提供するタイプ。もうひとつは、完全に放任主義なタイプです。放任主義と聞くと無責任に聞こえるかもしれませんが、生徒を信頼し、その判断に任せる部分が大きいため、自由で風通しのよい学校が多いです。
中学受験をした子供は、塾や家庭教師の管理下で、カリキュラムをこなしてきたケースが多く、いざ「自分で考えて自分で勉強して」と言われるとうまく対応できないこともあります。その場合、「生徒を信頼し、その判断に任せる部分が大きい」学校では、自分だけの力ではうまく学習習慣を定着できないケースも少なくありません。だからといって、ガチガチに縛り付ける学校では楽しく通えない子供もいます。
この辺りの「合う・合わない」の見極めは家庭だけでは難しいので、塾や家庭教師にアドバイスを求めたほうがよいでしょう。
通いやすさ、行事、特別科目など、多角的な魅力をチェック
通いやすい立地であるかどうかも含めた、その学校の持つ勉強面以外の魅力にも注目しておきたいところです。まず、通学時間が長い学校は、どうしても子供にとって負担が大きくなります。「通うだけで疲れてしまう」と家庭学習に注力できない子供もいます。乗り継ぎがスムーズかどうかや、道中が安全であるかどうかも大切なポイントです。
また、部活や行事のラインナップもチェックしておきましょう。子供がしたい活動に参加できる環境かどうかを確かめます。部活の種類や設備について知りたいことをまとめておくとよいです。
一般的な勉強以外の、その学校ならではの特別科目にも注目です。学校によっては宗教関連の授業であったり、礼節や作法の授業であったりが用意されています。興味のある内容に注力している学校を選びたいものです。
3つの軸から考えるこんな志望校選びはNG!

上記の3つの軸から考えて、NGな志望校はどんな学校でしょうか。具体例を見ていきましょう。
放任主義の学校なのに、帰りに塾に寄れない
生徒の自主自立を重んじ、学業に関しては放任主義の学校に通う場合、塾などのサポートが必要なケースも多いです。しかし、学校が辺鄙な場所だと、帰り道に塾を組み込むのも難しい場合があります。学校の校風と立地、登下校ルートはチェックしておきましょう。
男女間でのコートの使用調整で、練習量が制限される
共学の場合、男女別に同じ運動部があると、コートなどの設備をどちらが使用するかで調整するケースも多いです。結果、コートを使って活動できる時間が少なくなります。別学であればそうした心配はありません。部活に注力したい子供のいる家庭は、運用がどうなっているのかは、学校説明会で確認しておきたいところです。もちろん、学校の設備が充実していて、男女それぞれにコートを用意している学校もあります。
合わない特別科目が多い
私立の中学校では、その学校の宗教に関連する特別科目があったり、あるいは学校の教育方針によっては礼節・作法などに関連する特別科目があったりします。中には、そうした科目に苦手意識がある子供もいるでしょう。特別科目は、学校の教育方針と強く結びついていることが多いです。学校ごとの個性はその学校の魅力でもあります。自分に合う魅力を持った学校を選びたいものです。事前に学校のカリキュラムはよく確認しておきましょう。
志望校について、親子での話し合いのポイントは
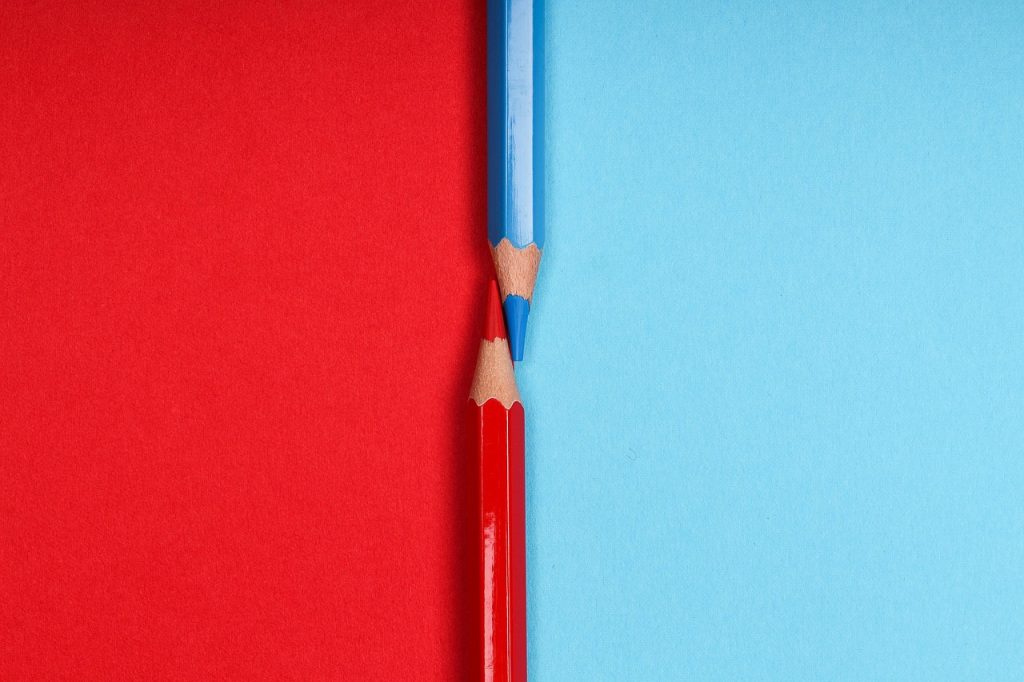
志望校について親子で話し合う際のポイントを見ていきましょう。
結論を親だけで出さない
中学受験は親主導になるのが一般的です。子供はまだ年齢的に進路を冷静に判断できないことが多く、どうしても親が旗振り役となります。だからといって、親だけですべてを決めてしまうのはNGで、受験においてはその都度、親子で話し合う姿勢が重要になります。
たとえば、親が「受験させるならA校に行かせたい」と考えていたとします。しかし、子供は「塾の友達がB校を目指しているから、B校がいい」と主張しました。自分の学力レベルやカリキュラムではなく、友達がいるかどうかだけでの判断です。そういう場合でも、親は子供の意見を一蹴してはいけません。子供の意見を受け止めた上で、B校にはないA校のメリットをプレゼンしてみてください。
子供が納得していなくても、親だけで無理を通すことはできます。しかし、親だけで進めてしまうと、子供との信頼関係にヒビが入ってしまいますし、受験へのモチベーションの維持が難しいです。
受験校の情報を多く共有しておく
受験は長期戦なので、「親にやらされている」という認識では最後までモチベーションを維持するのは難しいです。どうしても途中でだれてしまいます。勉強に気乗りしていない子供に、親が発破をかけざるを得ない場面は多くの家庭で嫌というほどあります。
しかし、その状態が固定化すると、「言われるからやる」だけになってしまいます。子供が自ら勉強に取り組むように促すためには、「その学校に行きたい」という動機が必要です。なるべく、子供に学校の情報を多く与えて、自分がそこに通う姿を想像させてください。そのためには、文化祭やオープンスクールへの参加もおすすめです。
子供にやる気がない場合は撤退も
受験をやめる決断は早ければ早いほうがよいでしょう。受験に向けた勉強は大変ですし、本人の負担を軽減する意味で、可能であれば小学6年生の夏休み前までには結論を出したいところです。撤退する際も、親が先走らないようにします。親の独断で決めてしまうと、子供に落ちたのと同様の挫折感を与えかねません。
進学後の選択肢についても話しておこう
行きたい学校の進学実績をチェックしておき、将来どういう道に進みたいのかを話し合うとよいでしょう。行きたい大学や学部があれば、過去どういう実績を出しているのかを必ず確認しておいてください。
たとえば、子供が「医者になる。〇〇大学の医学部に行く」という目標を持っていて、受験校がその夢をかなえるに足る進学実績を誇る場合は親子間でその情報を共有してください。中学受験に向けて、子供のモチベーションアップにつながります。
説明会に向けた絞り込みをしよう

基本的に、説明会は出願校の数より多めに参加するものです。ですから、「別学か共学か」「自主自立タイプか面倒見のよいタイプか」「その学校の多角的な魅力」の三つの軸を念頭に志望校を絞り込むのは大切ですが、多少条件と食い違うからといって説明会自体への参加をやめる必要はありません。時間が許すのであれば、一度話だけでも聞きに行くのがよいでしょう。もちろん、大きく条件から外れる学校はあらかじめ弾いておきます。
第一志望校と併願校はチャレンジ校から安全校までバランスよく揃えます。安全校は複数用意して、全落ちしないよう備えておくことが大切です。
どの年度にも一定数全落ちする子供は出てきますが、受けるショックは大きいものです。挫折感や無力感を長い期間引きずってしまう子供もいます。そうならないためにも、志望校の検討は、塾や家庭教師の先生との綿密な連携が欠かせません。子供に本当に合う学校を探してみましょう。