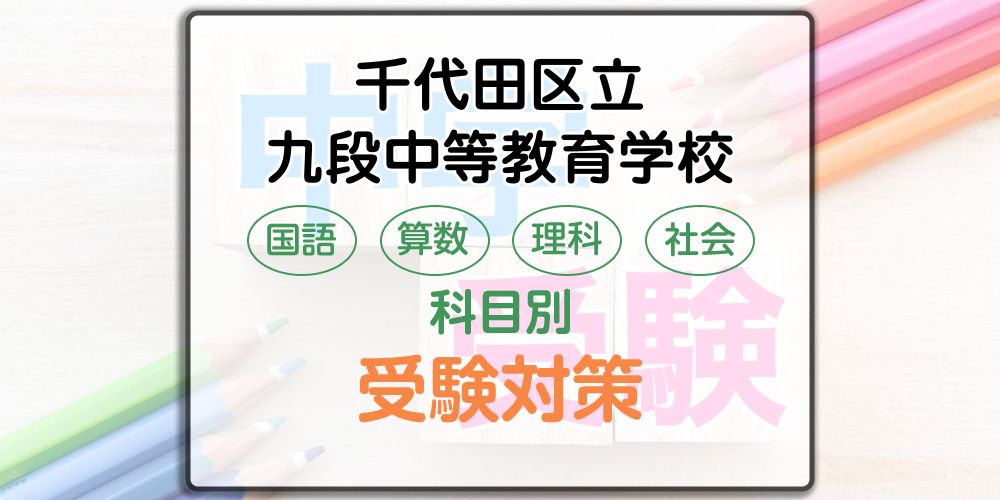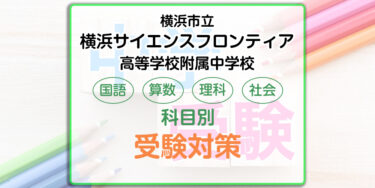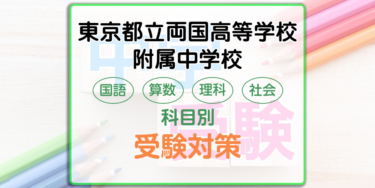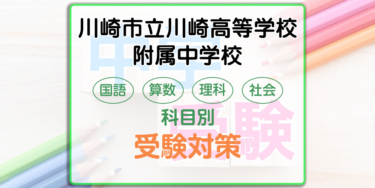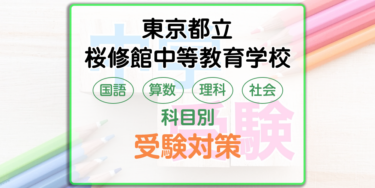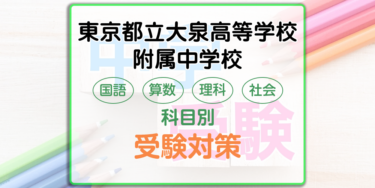千代田区立九段中等教育学校は、六年間を通して創造的、意欲的な生徒を育成している学校です。体験に重きを置き、本物から得られる学びを大切にしています。この記事では九段中等教育学校を受検する家庭に向けて、適性検査の出題傾向と勉強法を紹介します。
そもそも千代田区立九段中等教育学校ってどんな学校?
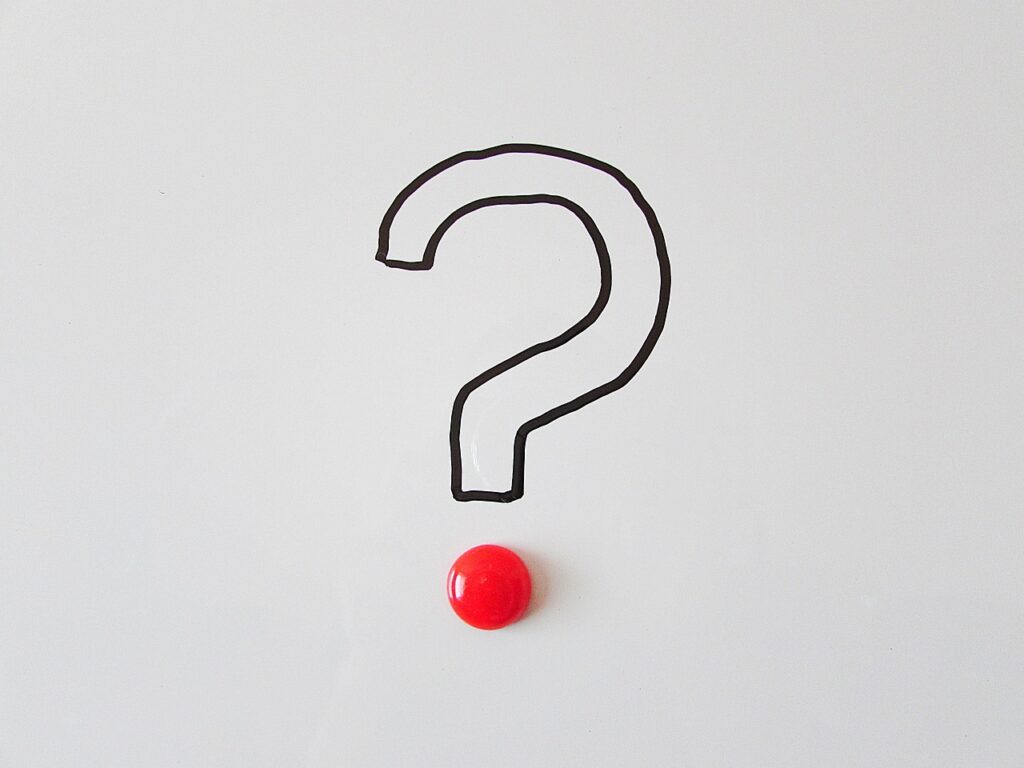
千代田区立九段中等教育学校は都会にありながら、緑にも恵まれた六年制の学校です。校舎は、一年生から四年生が生活する九段校舎と、五年生から六年生が生活する富士見校舎の二つに分かれ、充実した設備を備えています。体験を重視した授業を行っていて、生徒の発達段階に応じたカリキュラムを提供しています。
授業は月から金まで六時間、土曜日は四時間授業です。英語と数学では全学年で少人数指導およびチームティーチングを採用。生徒一人ひとりの学習進捗に合わせて細やかな指導を行っています。
課外活動では、文化部にも運動部にも注力しています。学外に参加者を募る催しも行っていて、年10回の天体観望会もそのひとつです。九段中等教育学校に関心がある人は、学校説明会はもちろん、こうしたイベントにも参加してみるとよいでしょう。
卒業後の進路としては、2025年度は国公立大学への合格者が47名(現役44名・既卒3名)で、私立大学が567名(現役531名・既卒36名)です。なお、医学部医学科だけを挙げると合計13名(現役10名・既卒3名)となっています。
千代田区立九段中等教育学校の入試概要
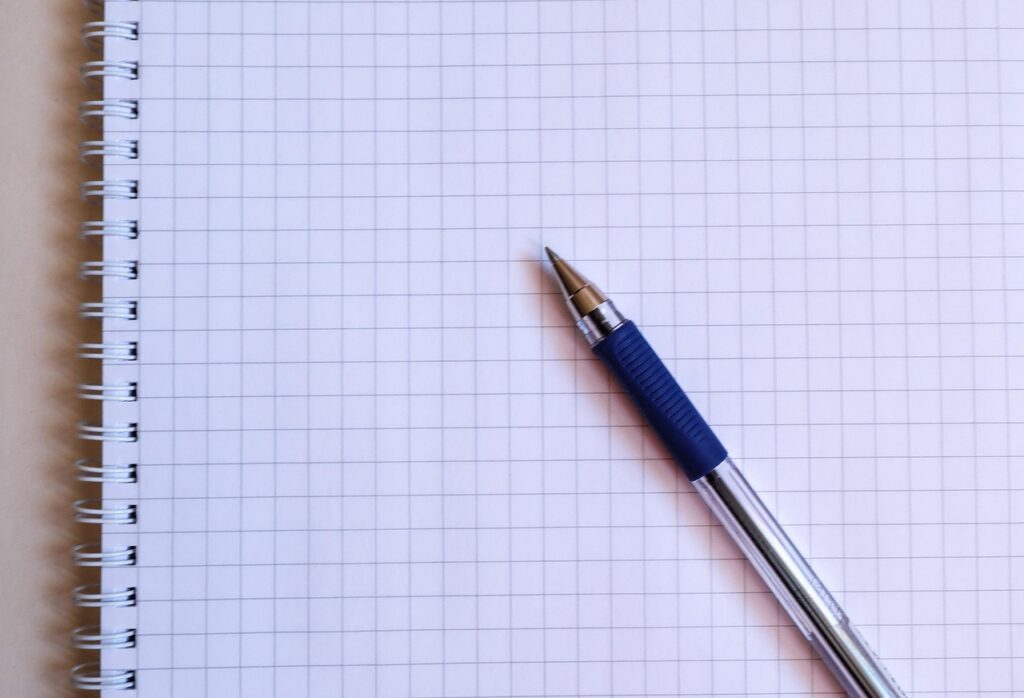
千代田区立九段中等教育学校の入試について見ていきましょう。
2025年度の入試倍率
千代田区立九段中等教育学校の受検は区分Aと区分Bに分かれています。区分Aは千代田区在住者、区分Bは都内在住者を対象としたものです。2025年度の受検は区分A、Bともに募集人数は80名ずつでした。区分Aの受検者は188名で合格者数80名、実質倍率は約2.4倍。区分Bの受検者は291名で合格者80名、実質倍率は約3.6倍という結果でした。
| 区分 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 区分A | 188名 | 80名 | 約2.4倍 |
| 区分B | 291名 | 80名 | 約3.6倍 |
2026年度の入試
2026年度の入試は、2026年2月3日に行われます。インターネット出願が2025年12月18日から2026年1月16日まで。書類提出期間は2026年1月9日から2026年1月16日までに設定されています。なお、インターネット出願と書類提出の両方が必要です。募集人数は区分A・Bそれぞれ76名ずつで、合計152名を募集しています。
千代田区立九段中等教育学校の特徴は学校でオリジナルの受検問題を作成している点です。そのため、対策をするには過去の出題傾向をよく把握しておかなければなりません。基本的には、報告書と適性検査と志願者カードによって合否が決まります。例年の傾向として、報告書は200点の配点が目安です。
千代田区立九段中等教育学校における適性検査の出題傾向

千代田区立九段中等教育学校の適性検査における出題傾向は以下のとおりです。
適性検査1は文章読解の問題が多い
例年どおりであれば、適性検査1の制限時間は45分で、大問は二つ、配点は200点が目安です。文章による穴埋めや記述問題が出題されます。一般的には、国語に分類される内容で構成されていて、読解力・記述力・表現力が問われます。題材は物語文と説明文です。
適性検査1の中で最も特徴的なのは、作文形式の出題がある点です。提示された複数の条件に従い、原稿用紙の正しい使い方で記述することを求められます。他には、抜き出しの記述問題であったり、説明記述であったりが出題されています。全体的に、記述力がなければ得点できない内容です。
適性検査2は分野を横断する出題
例年どおりであれば、適性検査2の制限時間は45分で、大問は三つ、配点は300点が目安です。会話文形式でさまざまなテーマに触れていくタイプの問題で、あらゆるジャンルから出題されます。たとえば、2025年度の問題では、理科や社会、算数などに関連する内容を扱っていました。横断的な出題が特徴です。
また、解答欄を見るとわかるのですが、理由を書かせる問題が多いです。説明記述は、選択問題と組み合わせて出題される傾向にあります。知識、提示された資料から情報を読み取る力、思考力、記述力などが必要です。
適性検査3もあらゆる分野から考える問題
例年どおりであれば、適性検査3の制限時間は45分で、大問は三つ、配点は300点が目安です。適性検査3では、適性検査2と同様に、横断的な出題がされています。算数、理科、社会に関連する問題が多いです。答えを求める過程を記述する問題や、理由を記述する問題など記述力・論述力を試される問題が多く出題されます。資料を読み取る力、条件整理をする力が求められ、問題文のボリュームもあるため、時間内に作業を終わらせる力も欠かせません。適性検査3も会話文形式で展開していきます。
- 適性検査1の中に作文形式の問題があるのが特徴的
- 情報を読み取る力、思考力、記述力が必要になる問題が多い
- 会話文形式で展開される問題が多い
千代田区立九段中等教育学校に合格したい。どんな勉強が効果的?

千代田区立九段中等教育学校に合格するためには、どういう勉強をするべきなのでしょうか。科目別に見ていきましょう。
国語の勉強法
国語にはどう取り組めばよいのでしょうか。
長い文章をスピーディーに読みこなせるように
適性検査1の読解文の長さに対応できるようにする必要があります。読解文だけではなく、設問自体も長いため、すべてをスピーディーに読みこなす能力が欠かせません。適性検査1の文章題のジャンルは年度によって異なりますが、物語文も説明文も出題されています。適性検査2、3では、多様な条件が提示される文章が多く出題されます。複雑な文章でも、整理しながら読みこなせる力が必要です。そのため、なるべく日頃から読解文の問題を多く解くようにしましょう。
文章に慣れ、要領をつかんでおく必要があります。読むのがあまり速くないようであれば、スピードアップを図ってください。適性検査1~3をすべて試験時間どおりに解いて、時間配分に問題がないかを確認します。もし、不足するようであれば、どのぐらいスピードアップすればよいのかを考えます。速読を身につけるために、自分の読む速度が一分あたりどれぐらいか記録をつけてみましょう。
要点を押さえる力を身につけよう
書かれている内容を文中の言葉を使ってまとめるようなタイプの記述問題がよく出ます。そのため、要点ひとつひとつを拾い上げる力が必要です。読解文を解く際には、内容を要約した文章を書いてみてください。文章の要点を押さえる、よい練習になります。
説明文では読むだけで精一杯になってしまい、一文一文のつながりを理解しないまま読み流してしまうケースがよくあります。全体を要約するのが難しければ、ひとつひとつの題材ごとに内容をまとめる練習をすることをおすすめします。
ある二つの題材を比較しながら展開していく文章があったとしましょう。その場合、二つの題材に関連する内容をそれぞれ箇条書きにしてまとめてみるのです。具体的な例を挙げると、ヨーロッパとアジアという概念を比較する文章があったとして、「ヨーロッパとはなにか」「アジアとはなにか」を文中からピックアップしてまとめていきます。こうすることで、とりこぼしなく書かれている内容を拾えるようになっていきます。慣れてきたら、箇条書きにしたものを文章にまとめる練習もしてみましょう。
いきなり、「文章全体を要約しろ」と言われてできる子供はごくわずかなので、段階的にレベルアップしていくとよいです。
原稿用紙の使い方を覚えよう
例年、原稿用紙の使い方に従って記述する問題が適性検査1のラストに出るので、必ずルールを確認しておくようにしましょう。
- 長い文章をスピーディーに読みこなすために速読を身につける
- 日頃から読解文の問題を多く解くようにする
- ひとつひとつの題材ごとに内容をまとめる練習をする
算数の勉強法
算数にはどう取り組めばよいのでしょうか。
規則性や場合の数をやり込もう
条件を整理してパターンを考える問題がよく出題されています。そのため、規則性や場合の数をやり込むことが得点につながるでしょう。解くまでの作業量の多さから、苦手意識を持つ子供も少なからずいます。多様な問題に取り組み、実力をつけておきたいところです。一問一問ボリュームがあるので、スピーディーに解けるようにしておきましょう。
図形の問題をたくさん解こう
千代田区立九段中等教育学校では、図形の問題が頻出です。2024年度の適性検査2では、立体を切断する問題や、立体を平面で表す問題などが出題されました。立体図形は苦手な子供が多い単元で、その中でも特に立体の切断は不得意な子供が多いです。早いうちからさまざまなパターンの問題を解くことをおすすめします。
条件の多い問題を解けるように
算数関連の問題では、問題文が長いものばかりが出題されるため、文章題をやり込んでおくことをおすすめします。
- 規則性や場合の数をやり込む
- 図形の問題は早いうちから取り組み、さまざまなパターンの問題を解く
- 文章題をやり込んで慣れておく
理科の勉強法
理科にはどう取り組めばよいのでしょうか。
基本的な知識はきっちり固めよう
2024年度の中和についての問題や、2025年度の温度変化の問題など、理科に関連する問題はたくさん出題されています。知識よりも文章を読み取って、思考するタイプの問題だといえますが、基本的な知識が身についていたほうがスムーズに解けるのは間違いありません。特に実験に関連する単元の理解を深めておきましょう。
現象の理由を説明できるように
理科関連の問題では、説明記述の問題も多いです。問われた内容の理由や背景が説明できるようにしておきましょう。説明記述は読み手に因果関係が伝わらなければなりません。しかし、具体的な内容を落とし込んだ文章が苦手な子供はたくさんいます。説明記述の問題にたくさん挑戦して慣れておきたいものです。特に実験問題ではなぜそうなるのかについて、言葉で説明できるよう練習しておきましょう。
図表やグラフに慣れておこう
図表やグラフを用いた出題が多いです。段階的に行われる複数の実験について、それぞれの結果を踏まえて考えたり、一連の結果をもとに別の事象について考えてみたりする問題が出題されます。長い問題文と資料の両方を確認して解くタイプの問題なので、時間配分に留意しながら解くようにしましょう。
- 実験に関連する単元の理解を深め、言葉で説明できるよう練習しておく
- 説明記述の問題をたくさんこなして慣れておく
- 過去問を通して時間配分を身につけておく
社会の勉強法
社会にはどう取り組めばよいのでしょうか。
文章や資料から思考する力を
基本的に知識に重きを置く問題は出題されません。長い文章と資料を最後まで読み、思考することで答えを導き出すタイプの問題が出題されます。たとえば、2025年度は群馬県の気温変化と標高の問題や、エコツーリズムに関する問題などが出題されました。これらは教科書で覚えた知識を問う問題ではありません。会話文形式で展開する文章や、グラフや図表を見て思考するという問題でした。過去問で出題傾向を把握し、必要な情報を読み取る力を養いましょう。
何段階かある情報を網羅しよう
社会に限らず、とにかく問題文が長く、何段階かに分けて展開していくのが特徴です。そのため、提示された資料や情報にすべて目を通すだけで、かなりの時間を要します。それでも、算数や理科よりは社会関連の問題のほうがまだコンパクトにまとまっていることが多いので、できるだけ素早く解き進めたいところです。集中力を切らさず、スピーディーに解き進めることを意識しましょう。何ページか遡って資料を確認しなければならないような分量ですので、常に残り時間は意識してください。
- 過去問で出題傾向を把握し、ページを遡って資料を確認する作業に慣れておく
- 文章や資料から情報を読み取る力を養っておく
- 長い問題文で集中力が切れない様に類題で慣れておく
複雑な問題を時間内に処理する力を
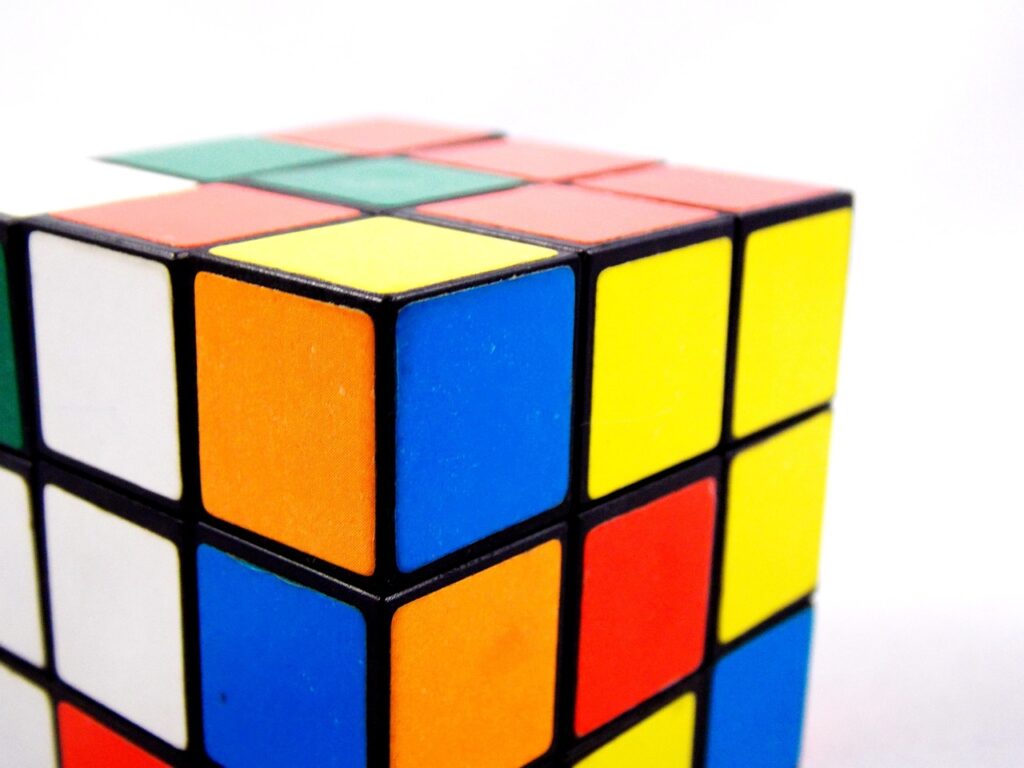
オリジナル問題を学校で作成しているため、都立の一般的な学校よりは出題傾向がつかみづらいといえるでしょう。秋ごろから過去問をやり込んで、特徴を把握しておきたいところです。適性検査1は国語型で、適性検査2と3は分野を横断する出題になります。情報量が多く、たくさんの資料から必要な情報を読み取って、解かなければならないという点では、適性検査らしい適性検査です。そのため、時間があれば、都立の一般的な問題も練習に解いておくことをおすすめします。適性検査ならではのボリュームに慣れておくとよいでしょう。
次々と展開するテーマに対し、たくさんの情報をいかに効率的に適切に捌けるかが問われています。資料と設問を行き来するような出題が多いので、集中力が欠かせません。多くの問題が記述形式なので、思考して表現する力が必要です。相手に伝わるような記述ができているかどうかは、塾や家庭教師の先生にチェックしてもらうとよいでしょう。自己採点だと、意図の伝わる文章が書けているかどうかが客観視できません。