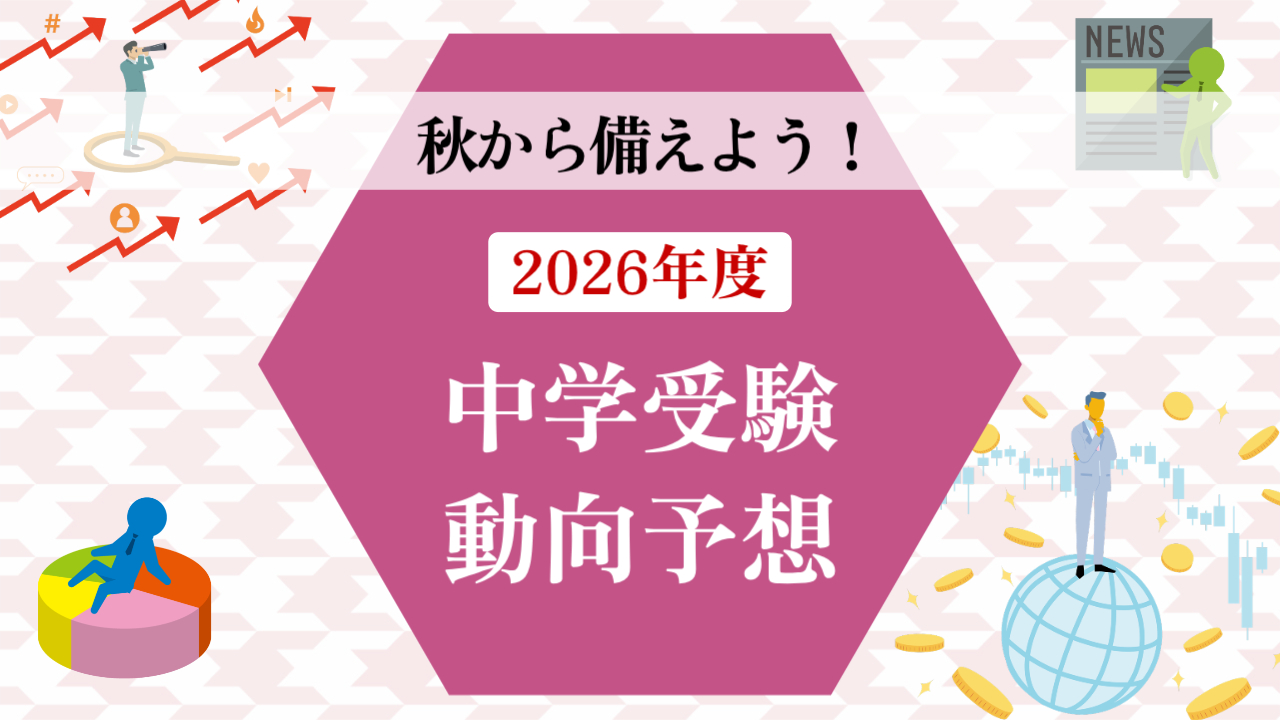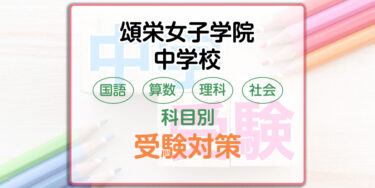秋になるといよいよ中学受験目前です。より効果的な対策が必要となります。この記事では、2026年度の中学受験動向予想について紹介します。
六年生の秋はどんな時期?

六年生の秋は受験本番に向けて、基本的にはどういった備えをする時期なのでしょうか。
過去問のやり込みが本格化
夏休みが終わり、秋に入るといよいよ過去問のやり込みが本格化します。受験範囲の勉強から、志望校別の対策へと特化していく時期です。そのため、学習する内容は受験校によって異なってきます。
志望校の過去問をやっても、同じ問題が出題されるわけではありません。それでも、過去問が重要なのは、その学校の出題傾向が見えてくるためです。大問の構成から、頻出単元、出題形式までを押さえていきます。毎年出題形式が大きく変わる学校はあまりありませんから、過去問を解く作業はイメージトレーニングとして最適です。制限時間内に解いてみることで、本番の時間配分をイメージできるようにしましょう。
志望校の合格ラインに到達するための最適な方法を考え実行する時期が、受験生の秋です。受験勉強における優先順位をはっきりさせることが求められます。
成績が変動しやすく、メンタル面の管理が必要
中学受験においては、「夏休み直後の模試は気にしなくてよい」とよく言います。夏休み後の模試は成績が上下しやすく、安定しないためです。しかし、受験本番が近づいてくる時期でもあるため、深刻に受け止めてしまう家庭も少なくありません。緊張感やプレッシャーとの戦いも本格化する時期です。メンタル面の管理が必要となります。
2026年度の受験動向ってどんな感じ?

六年生の秋に一般的な備えをするのはもちろんですが、その年ならではの備えも必要です。2026年度の受験動向について知り、自分なりの対策を講じましょう。
2月1日日曜日の「サンデーショック」
中学受験の入試日が2月1日の学校は多いです。その2月1日が2026年度は日曜日となっています。日曜日でも入試を行う学校はもちろんたくさんあります。しかし、キリスト教系の学校を中心に行わない学校もあるため、一部の学校のスケジュールが大きく変わる予定です。こうした状況を「サンデーショック」といいます。
人気校の日程が変わると、当然倍率も大きく変わります。たとえば、女子の御三家である女子学院は例年2月1日実施ですが、2026年度は2月2日に変更になるため、おそらく難易度は例年以上に上がります。2月1日に難関校の受験が固まっているため、2月2日にずれたことで併願する人が多くなることが予想されるためです。そのため、秋になり過去問に取り組む際には、合格ラインが上がる可能性を念頭に置くことをおすすめします。他にも立教女学院、東洋英和女学院なども2月2日に変更です。
受験者数の増加と難関校受験者数の減少
日能研の集計によると、2025年の首都圏中学受験者数は6万2,200人で中学受験率は21.5%されています。五人に一人と聞くと多いのがわかります。ただし、これでも近年はやや減少傾向です。
各校の受験者数を見ると、難関校の受験者数は一部を除いて大半が減少傾向にあります。2024年度と2025年度を比較すると、増えているのは女子校なら鷗友学園女子、男子校なら聖光学院、海城などが挙げられます。共学校なら渋谷教育学園渋谷の女子受験者数も増加傾向です。
しかし、大半の難関校では受験者数は減少傾向にあります。おそらく2026年度も日程変更の影響などがある学校以外は、大半が減少傾向になるでしょう。
中堅校の受験方式の多様な展開
中学受験において、中堅校は何種類もの受験方式を採用していて、何日にもわたってさまざまな種類の試験を展開しています。そういうタイプの学校では、一日を午前と午後に分けて、それぞれ試験を実施するやり方が主流です。おまけに、複数回受験すると受験料が割安になるシステムを導入しています。
当然、何度も受験して受かろうとする家庭がたくさん出てきます。そのため、試験回数の少ない難関校と違って、中堅校は受験者を多く獲得しているのが現状です。この傾向は2026年度も続くと予想されます。
また、中堅校以下では、一般入試以外の試験を行う学校が増えています。一教科入試であったり、思考力入試であったり、英語資格を入試の得点に置き換えるタイプの試験であったりと多種多様です。少子化対策も含めて、入試のバリエーションを増やすことで受験者数を増やしている学校では、こうした傾向は今後もより一層強く見られるでしょう。もちろん、一般入試だけではかれる能力は限られているので、さまざまな角度から優れた受験生を求めたいという狙いもあります。
記述問題の傾向に変化も
少しずつですが、出題傾向として「あなたの考えをまとめなさい」といった記述問題が増えてきています。これは2020年に改訂された学習指導要領の影響が大きいです。知識だけではなく考える力を求めるという方針は、大学入試に影響を与えました。遅れて、中学入試でもその傾向は散見されるようになっています。
記述問題といっても国語とは限りません。国語以外にも理科、社会でそういった問題が出ています。知識を蓄えるのはもちろん大切です。しかし、その知識に基づいて自分なりの意見を書き出せる力が欠かせません。過去には、武蔵中学校や、鷗友学園女子などで出題されています。現代社会の課題と絡めた問題の出題も多く、SDGsについて意見を求める問題はさまざまな学校で出題されてきました。
子供が知ったばかりの社会問題について触れたときに、保護者はひと言「よく知っているね。それについてどう思った?」と質問を向けてあげてください。その繰り返しが子供の意見を育てていきます。
説明文を読んで、特定の箇所について自身の考えを述べる問題が出題されることもあります。SDGsのように皆の知るテーマではないので、戸惑うかもしれません。しかし、日頃から自分の意見をまとめる習慣がついていれば問題に立ち向かえます。
時事問題も問題提起の方向へ
最近の受験問題では時事問題を受けて、受験生に問題提起するような内容が出題されています。さまざまなマイノリティの人権について、持続可能な社会について、受験者が考えているかどうかを問うような問題が多いです。2026年度もこの傾向は強まっていくでしょう。とりわけ社会の最後の大問でそうした内容を展開している学校が多いです。
サンデーショックに要注意!!
2026年度は合格ラインが上がることが見込まれるため、判断基準を見誤らないよう塾や家庭教師にしっかりと確認しよう。
2026年度の受験問題で出題されそうなテーマは?

過去の出題傾向から、2026年度の社会もしくは国語の受験問題で出題が予想されるテーマについてまとめました。
排外主義についての出題
2026年度はおそらく排外主義に関する出題があるのではないか、と予想されます。ここ数年、難関校では多様性の観点から、その年に注目を集めたテーマが出題されてきました。特に社会ではジェンダーやアイヌに関する出題がさまざまな学校で見られました。
その点で考えると、今年のテーマは「排外主義」の可能性があります。七月の参院選において一部政党で外国人規制強化が叫ばれたこと、第80回国連総会での総理大臣一般討論演説の結語に「全体主義や無責任なポピュリズムを排し、偏狭なナショナリズムには陥らない。差別や排外主義を許さない」というくだりがあったこと、アメリカでも移民排斥やマイノリティ差別が蔓延している現状などを受けて、受験生に問題提起するような内容が出題される可能性があります。
一冊読んでおくとするなら、安田浩一・金井真紀著「新版 学校では教えてくれない差別と排除の話」がおすすめです。皓星社の本で、2025年9月に加筆された新版が出ているので、「今」のトピックを押さえています。
戦争についての出題
パレスチナとイスラエル、ウクライナとロシアの戦争は続いています。パレスチナとイスラエルに関しては、アメリカという大国の思惑やヨーロッパの対応の変遷の背景など、さまざまな切り口からの出題が予想されます。
ちょうど朝ドラが反戦をテーマに据える「あんぱん」だったこともあり、戦争や虐殺について掘り下げた問題が出る可能性は高いです。おそらく、2026年度に出題されるなら、ガザの惨状を受けた出題があるのではないでしょうか。
親子で読む本としては高橋真樹著の「もしも君の町がガザだったら」がおすすめです。こちらはポプラ社から出版されていて、小学生にもわかるようにというコンセプトで書かれているため読みやすいです。
大河ドラマに絡めて表現規制の出題
大河ドラマに絡めた出題も中学受験ではよく見られます。今年の大河「べらぼう」では、風刺の取り締まりに対する蔦屋重三郎による抵抗が描かれています。昨年の「光る君へ」も社会のテストに絡めて出題する学校がいくつかありました。
権力による言論や表現の取り締まりについては、ここ最近アメリカの動向が特に注目を集めています。
2025年9月、コメディアンにしてテレビ司会者ジミー・キンメルの番組が圧力を受けて停止された件はその最たるものでしょう。奇しくも「べらぼう」の物語で、戯作者たちが抑圧されていく過程が描かれているときでした。きっかけはジミー・キンメルがチャーリー・カーク殺害事件に関して、MAGAを批判したことにあります。ジミー・キンメルの番組が休止させられると、著名人たちは反対の声をあげました。
その後、番組は再開しましたが、トランプは「ABCを試す」と再開を許可したABCテレビへ怒りのコメントをしています。この問題がどういう決着を見るのかは、まだまだ予断を許さない状況です。
気候変動についての問題
社会もしくは理科において、気候変動についての問題が出る可能性もあります。気候変動は今に始まった問題ではありませんが、興味深い調査結果が出たことで話題になりました。世論調査会社イプソス株式会社が2025年4月22日に発表した32か国調査「人類と気候変動レポート 2025」によると、気候変動対策への日本人の意識低下が32か国中最下位だったというものです。
たとえば、気候変動に対する個人の行動が必要だと感じる日本人の割合ですが、2021年の調査時に比べて19ポイントも落ち込んで40%となっています。この質問に「同意する」と答えた人の平均は64%なので、平均を大きく下回っています。一方で、自国で起きている気候変動の影響について「心配している」と答えた人は81%。日本は近年、猛暑に悩まされているため、それ自体は憂えている様子がわかります。
それにもかかわらず、「政府が気候変動対策に取り組まなければ国民の期待を裏切る」に同意した人が42%。「企業が気候変動対策に取り組まなければ従業員や顧客の期待を裏切る」に同意した人は37%。いずれも最下位です。つまり、個人や社会で気候変動について解決を図っていこうという意識は希薄なことがうかがえます。
POINT!!
ここ数年は朝ドラが有効活用できるテーマが増えてるよ。
2026年度の受験動向をチェックして対策をしよう
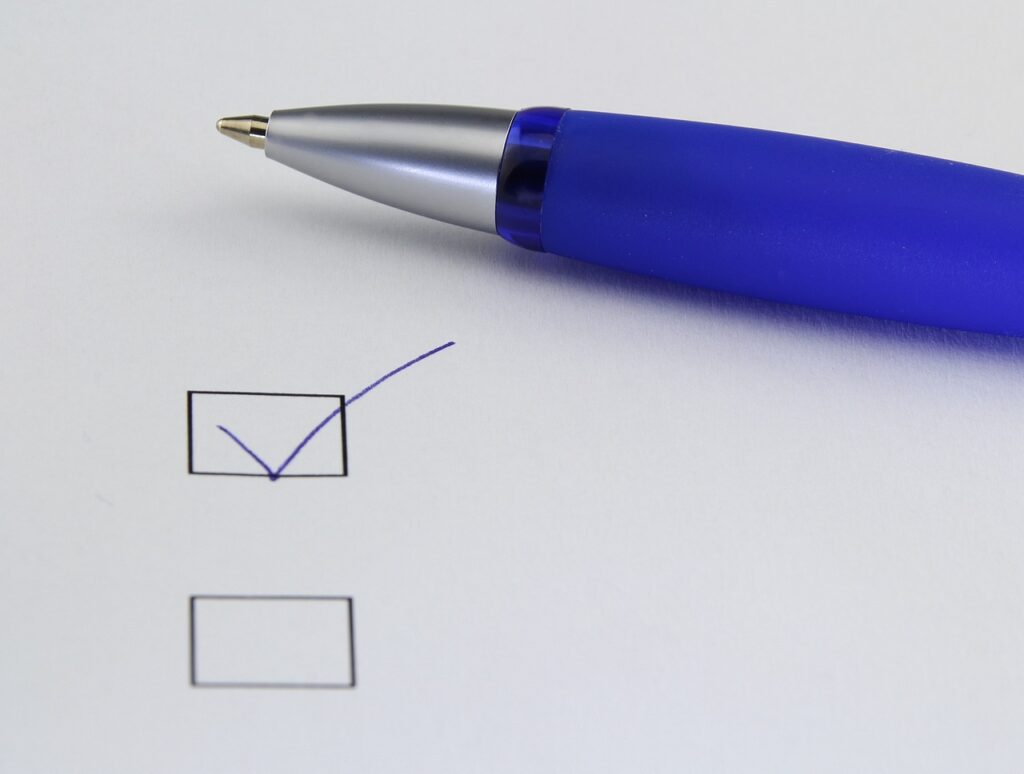
2026年度の受験動向を早めに知っておくことで、対策が立てやすくなります。とりわけ2026年度はサンデーショックの影響が大きいので、どの学校を併願するかは、検討を重ねるようにしてください。願書を入手するのは10~11月なので、それまでに選定しておくとよいでしょう。日程が変われば倍率も変わりますし、塾や家庭教師に相談した上で慎重に決めることが求められます。
2026年度は、受験者数の増加や中堅校の多様な入試、出題傾向の変化などさまざまな特徴が指摘できます。特に対策しておきたいのは今年度、関心を集めた社会問題についてです。難関校では特に、多様性や共生社会の実現を目指す観点から、問題提起をするような内容を出題する傾向にあります。2025年は、排外主義の蔓延や、泥沼化する戦争、言論や表現を抑圧し規制しようとする動き、気候変動に対する関心の低下などさまざまな問題が指摘されてきました。そのため、2026年度の入試はそうしたトピックを掘り下げた問題が出題される可能性があります。
まずは、自分の意見を記述できるように準備しておいてください。ただし、問題の背景を正しく理解しないままではよい答えは書けません。記事中に参考になる書籍をいくつか挙げているので、一度読んでみることをおすすめします。