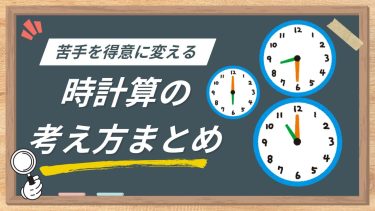首都圏において、中学受験対策は小学三年生の二月頃から始まります。つまり新四年生のコースに合わせて中学受験対策を進めていくのです。この記事では、中学受験は初めてという家庭に向けて、入塾後知っておきたいことを紹介します。
なぜ小学三年生の二月からが一般的なの?

中学受験においては、なぜ小学三年生の二月からの入塾が一般的なのでしょうか。
複雑化するカリキュラム
首都圏では、新四年生コースが始まる小学三年生の二月から受験勉強を始めるやり方が一般的です。四年生にもなると、小学校のカリキュラム自体がだいぶ複雑化してきます。たとえば、算数なら小数や分数を使った計算、複雑な割り算の計算が出てくるため、ついていけなくなる子供が続出する頃です。
中学受験ではこうした学校レベルに留まらず、難易度の高い学習内容を理解する必要があります。つまずきの多い時期に大きく遅れをとらないためにも、新四年生コースからの参加が望ましいでしょう。
小学五年生・六年生になる前の下地作り
受験勉強は学年が上がるごとに、塾に通う回数も増え、取り組む勉強量も膨れ上がります。そう聞くと大変そうですが、つまりは段階を踏まえたステップアップです。
たとえば、五年生からいきなり受験勉強を始めようとしても、学習習慣が定着化していなければ求められる勉強量をこなすのは難しいです。学力的にも、積み重ねてきた知識がなければ理解に時間を要します。
そのため、中学受験では新小学四年生から、学習習慣の定着化と学力の下地作りを進めていきます。
小学三年生の二月より前に始める家庭もあるの?
中学受験対策を小学三年生の二月より前に始めている家庭もあります。サピックスをはじめ人気の大手塾に入塾させる予定の場合、入塾倍率が低いうちにわが子を入れてしまおうとする家庭も多いです。
また、塾側も新小学四年生前に準備コースを設けているところが増えています。たとえばサピックスは小学三年生の冬休みに、準備講座としてまだ通塾していない子供を対象にした全四日間の冬期講習を行っています。
ちなみに、首都圏以外では新五年生あたりから受験対策を始める子供が多い地域もあります。
- 四年生から小学校のカリキュラムが複雑化する
- 勉強についていけず遅れをとる子が増える
- 学年が上がり勉強量が増えることに慣れる為の準備段階になる
中学受験塾についていけない子供も

新四年生から中学受験塾に入塾しても、勉強がスムーズに軌道に乗るとは限りません。どんなケースがあるのか紹介します。
塾での授業内容が理解できていない
勉強にまったくついていけず、入塾早々に「塾に行きたくない」「受験やめたい」と言い出すケースもあります。塾に行って、勉強が理解できないまま大量の宿題をこなさなければならないとなれば、モチベーションが上がらないのは当然です。
中学受験塾ではクラス編成によって成績が可視化され、子供たちは競争意識をもって勉強に取り組むことになります。しかし、競争意識を持つ前に、プレッシャーに参ってしまう子供も少なくありません。
まずは学習を軌道に乗せて、子供が受験勉強に手ごたえを感じられるようにしなければなりません。そのためには、授業参加の仕方と、家庭での勉強の仕方を見直す必要があります。
授業に集中できていないのはタイムロス
中学受験塾に通う生徒の中には、授業時間内にすべて理解するつもりで集中して聞く子供もいれば、ぼんやりと授業が終わるのを待つ子供もいます。
授業に集中できていなければ、家庭で取り戻すしかありません。宿題や予習復習だけでも大きな負担なのに、授業で習った分をイチからやり直さなければならないとなると、普通は処理が追い付きません。仮に新小学四年生ではなんとかなったとしても、学年が上がり学習量が増えればいずれは破綻します。そうなる前に、なんとか授業に集中する習慣づけをしましょう。
中学受験塾についていくための対処法
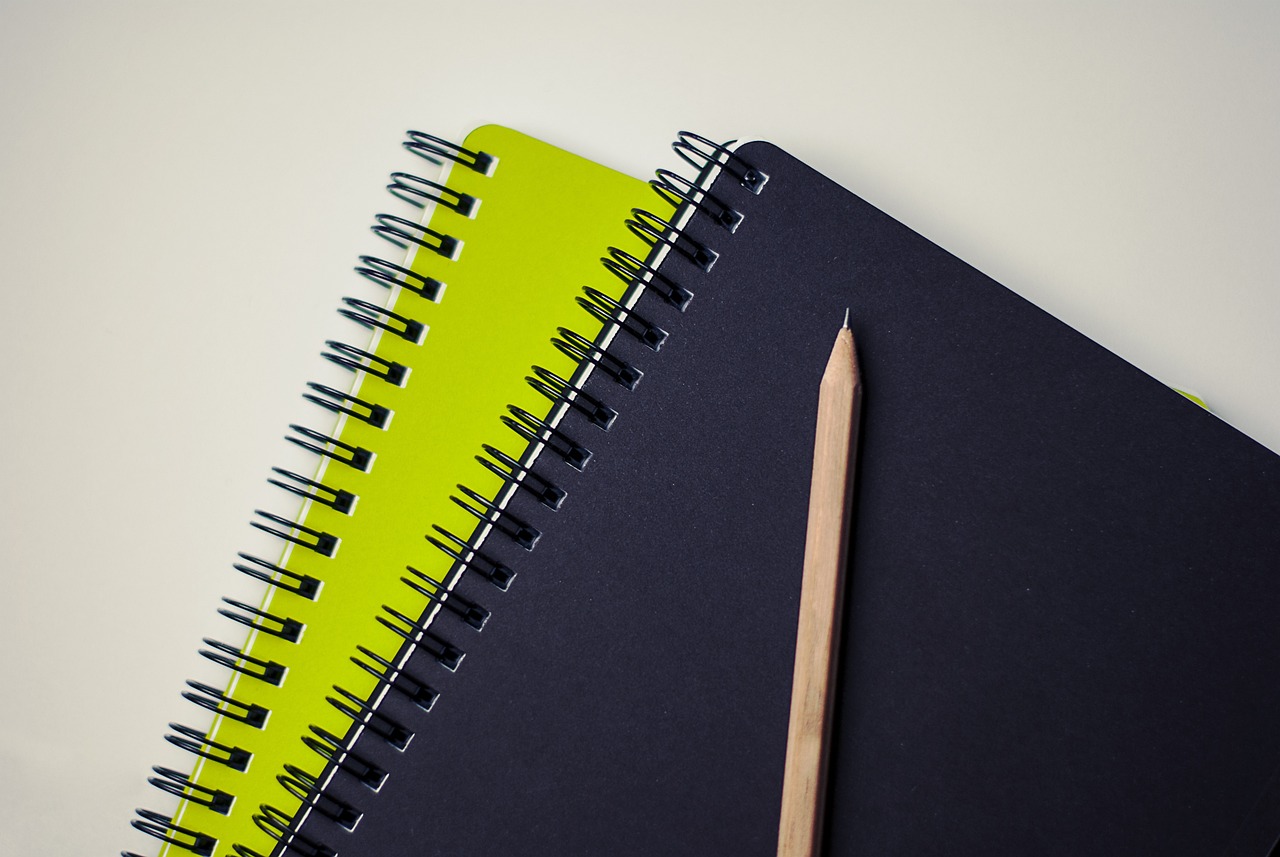
中学受験塾の授業についていくための方法は以下のとおりです。
授業の内容を理解するためのノートを
授業中聞き流さないためには「ただ板書をするのではなく、自分が見直せるノートを作る」作業が必須です。以下見ていきましょう。
ルーズリーフは使わない
まずルーズリーフではなくノートを用意します。ルーズリーフの管理がきっちりできる小学生はほとんどいないためです。ノートの表紙には科目名と学年、使い始めた日付を書きます。今後、ノートはどんどん増えていくので、いつのノートかをすぐ把握できる工夫が必要です。
色分けは三色まで
ノートをとる際の色分けは三色までにしましょう。カラフルなノートをとる子ほど、授業内容を聞き流す傾向があるので、色分けに夢中にならないよう数を絞った上で色分けのルールを決めておきましょう。たとえば、要点は青、暗記は緑、採点は赤といった具合です。
見直したときにひと目でわかるように
問題を解くにあたって、「日付」と「テキストや問題集の名前」と「問題番号」は必ず書き込みます。この三つは成績が上がりにくい子供が書き忘れがちなものです。見直したとき、「どこの」「なんの問題」が解いてあるのかひと目でわかるようにしましょう。
先生の話を聞いてノート作りを
ノートにわかるように落とし込んでいくためには、先生の話を集中して聞く必要があります。先生の話を整理してノートにまとめることで、理解が深まるのです。板書の内容はあくまで要点に過ぎません。板書をただ写すのではなく、板書の内容を自分の頭で理解するためにはどう書けばよいのかを考えるとよいでしょう。
宿題は難しくても一度考えてみる
宿題のやり込み具合には、その子の勉強に対する姿勢が顕著に出ます。できるだけ自力で解いてくる子供、わからなかった問題は問題集に印をつけて持ってくる子供、とりあえず難しそうな問題はすべて飛ばして持ってくる子供。
こうした宿題への姿勢は子供の成績に直結しています。いい加減に宿題をやれば成績も上がりません。ただ、そうはいっても、たしかにわからない問題をずっと考え続けているのはタイムロスです。切り上げるべきタイミングはあります。
しかし、最初から「難しそうだから」という理由で問題を飛ばすのはよくありません。問題の意味を理解できるまで読み直してみましょう。どう頑張っても解けなさそうであれば飛ばしても構いませんが、その際は問題集にマークを残しておいてください。解けるようになってからやり直す必要があるためです。
問題集に答えを書き込まない
塾と宿題だけやっていても成績は上がりません。肝心の「自分の成績向上のために必要な問題」が解けていないためです。成績を上げるために必要な問題は一人ひとり違います。苦手なところを何度もやり直してください。
低学年までは問題集に直接答えを書き込んでいるかもしれません。小さいうちは用意されたフォーマットに答えを書く練習も必要なので、それはそれで理に適っています。
しかし、中学受験対策では、基本的に問題集には書き込みません。同じ問題集を何周もやり直すのが前提だからです。必ず答えはノートに書くようにしましょう。
- 見直すことを前提としたノート作りをする
- ノートは板書するだけではなく自分の頭で内容を理解してまとめる
- 難しい問題でも意図を理解できるまで読み直して自力で解く習慣を付ける
- 問題集は何度もやり直すものなので答えはノートに書くことを徹底する
家庭学習が定着化しない場合、どうすればよいの?

「いざ塾に通わせてみたものの、家庭学習が定着化せず成績も伸びない」というのは親としてできれば避けたいケースです。どうすればよいのでしょうか。
勉強は終了時間ではなく目標時間を決める
毎日、「何時から机に向かう」という習慣をつけておきましょう。ただ、「何時から何時まで勉強する」と終了時間を設定するのはおすすめしません。集中していても、集中していなくても時間が来れば終わり、というのはあまりよい習慣ではないためです。
勉強をする際は、開始時間とその日にやる内容を決めて机に臨ませるようにしましょう。その上で、終了時間ではなく目標時間を決めます。「何時までに終わる」ではなく「何時までに終わらせるよう集中する」という姿勢でいられるとよいです。
塾の自習室を積極活用
塾に自習室があるのなら、積極的に活用しましょう。塾の自習室のメリットは先生にすぐ質問に行ける点です。また、ライバルたちが頑張って勉強に励む姿が刺激となります。家庭ではどうしても緊張感を維持するのが難しいので、塾の自習室で済ませられる勉強は居残って済ませてしまうとよいです。
ただ、小学三年生の二月からいきなり自習室に居残りさせても、ほとんど手付かずのまま終わるケースが少なくありません。まだ新小学四年生ですから、「宿題だけでも終わらせてきて」と親が指示したとしても、そのとおりにできる子供ばかりではないのです。
もどかしいでしょうが、最初は塾に通うこと自体に慣れるよう促してあげてください。本人が自習室はまだ早いと思っているのであれば、気持ちの準備ができてからの利用でもよいでしょう。
子供部屋が無理ならリビング学習
集中力のある子供なら、子供部屋でも問題なく勉強できるでしょうが、一般的に新小学四年生ではあまり期待できないことが多いです。中には集中力のある子供もいますが、やはり個人差があります。人目がないと集中できないようであれば、リビング学習に切り替えてあげましょう。親の目を意識して勉強を進めていくはずです。
保護者は塾の先生に頼って
宿題だけならともかく、予習や復習となると保護者としてもなにをどう進めていけばよいのかよくわからないかもしれません。そういうときは遠慮なく塾の先生に質問しましょう。塾には保護者からの電話がしょっちゅうかかってきますし、悩み相談も多いです。長電話になるケースも珍しくありません。
「勉強の相談をしたい」と電話して嫌がられることはまずありませんし、そこで難色を示される塾なら転塾してもよいでしょう。もちろん、塾の先生も忙しいので、その場ですぐ返事がもらえるわけではないかもしれません。
しかし、時間や場所を再設定して、話を聞いてくれるはずです。子供の成績が上がるよう塾と二人三脚で進めていきましょう。
- 終了時間を決めるのではなく決めた内容を終わらせる目標時間を決める
- 塾の自習室を積極的に活用する
- 家の中での学習環境を変える
- 塾の先生に相談する
学習が軌道に乗らない場合は家庭教師・個別指導との併用も
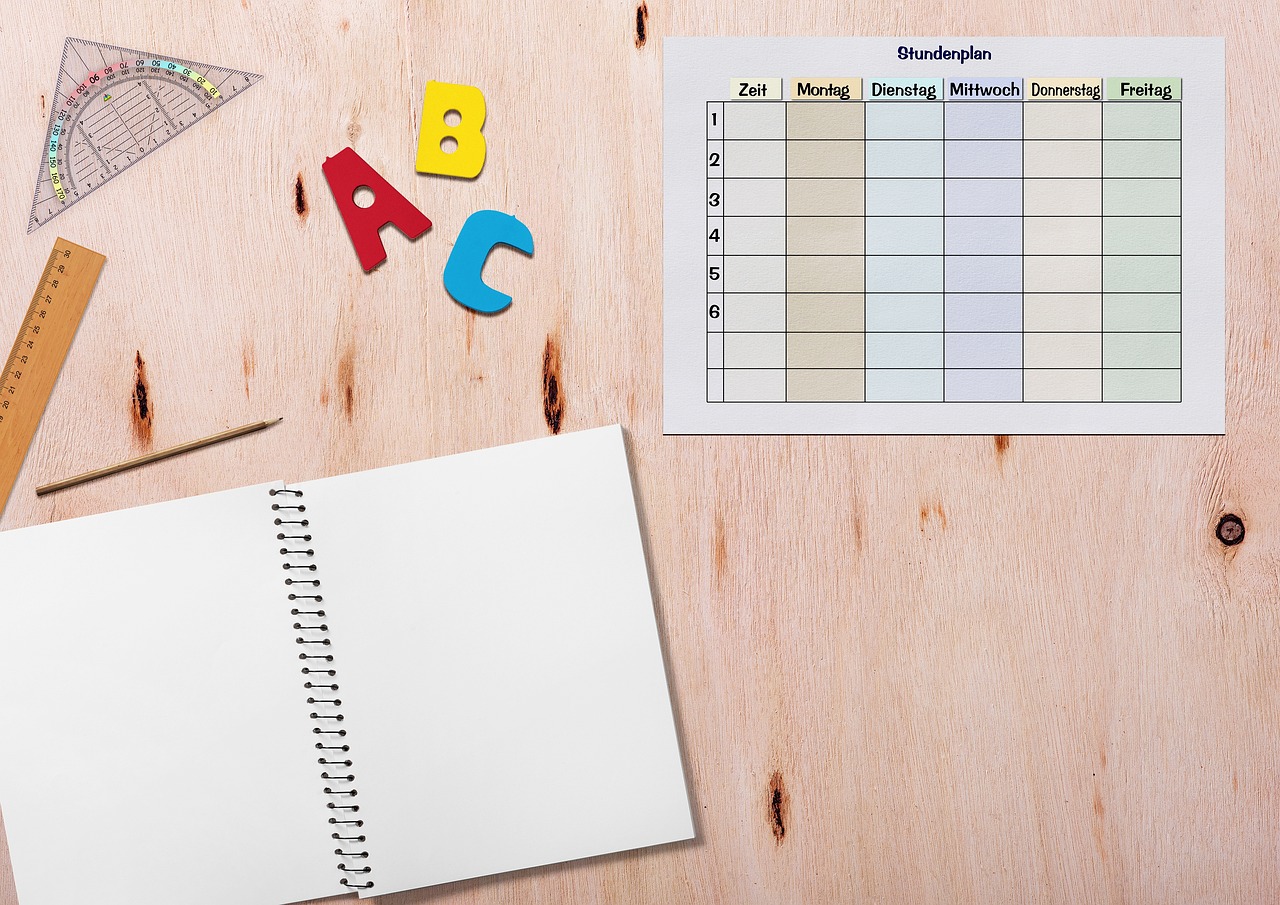
中学受験は保護者が伴走者にならなければ、なかなか学習が軌道に乗りません。しかし、アウトソーシングする方法もあります。
中学受験は「親の受験」。アウトソーシングする方法も
中学受験は「親の受験」と言われるように、保護者がするべきフォローがたくさんあります。しかし、共働き家庭はもちろん、そうでなくとも保護者が子供につきっきりでフォローに回るのはなかなか負担が大きいです。
いっそ、経済的に余裕があるのであれば、家庭教師や個別指導にアウトソーシングしてしまったほうがよいでしょう。実際、家庭教師や個別指導にも「〇〇塾(大手塾)の補習コース」が用意されているところが多いです。
家庭教師なら保護者の目も届きやすい
小学三年生の二月から始めて、さっそく個別指導塾まで併用するとなると息切れする子供も多いです。その点、家庭教師であれば、基本的には自宅指導ですし保護者の目もありますから、子供も落ち着いて授業を受けることができます。
「小さいうちから塾ばかり行かせるのもどうだろう」と考える家庭にとっては、併用しやすいサービスだといえるでしょう。先生との距離も家族ぐるみで近くなるため、中学受験勉強の進捗を保護者もしっかりと把握できます。
新四年生としてのスタートダッシュを成功させよう

いよいよ本格的に中学受験対策に臨むわが子の姿に、親としては心配が尽きないでしょう。小学三年生の二月の時点で、保護者の目から見て「大丈夫そう」と思える子供はほとんどいません。塾でのコミュニケーションこそ楽しめても、授業内容は理解できず、ましてや家での勉強は手付かずなんてケースもよくあります。
そういうときには勉強に集中できるよう保護者がサポートしてあげましょう。ノートの使い方を共有し、宿題のやり方をアドバイスします。自習室の活用やリビング学習への切り替えで、子供が勉強しやすい環境を整えてあげましょう。
学習習慣が定着化しないと焦りますし、子供が集中力を発揮できずにいる様子を見ているとイライラしてしまうかもしれません。その場合、経済的に可能であれば、家庭教師や個別指導塾にサポート役をアウトソーシングしてしまってはどうでしょうか。
「塾をこれ以上増やすと子供の負担になる」というのであれば、家庭教師をつけるのをおすすめします。自宅ですし、親の目も行き届きやすく通塾するためのタイムロスがありません。家庭教師にも、大手塾の補習コースを用意しているところは多いです。学習が軌道に乗るまでサポートを頼むとよいでしょう。