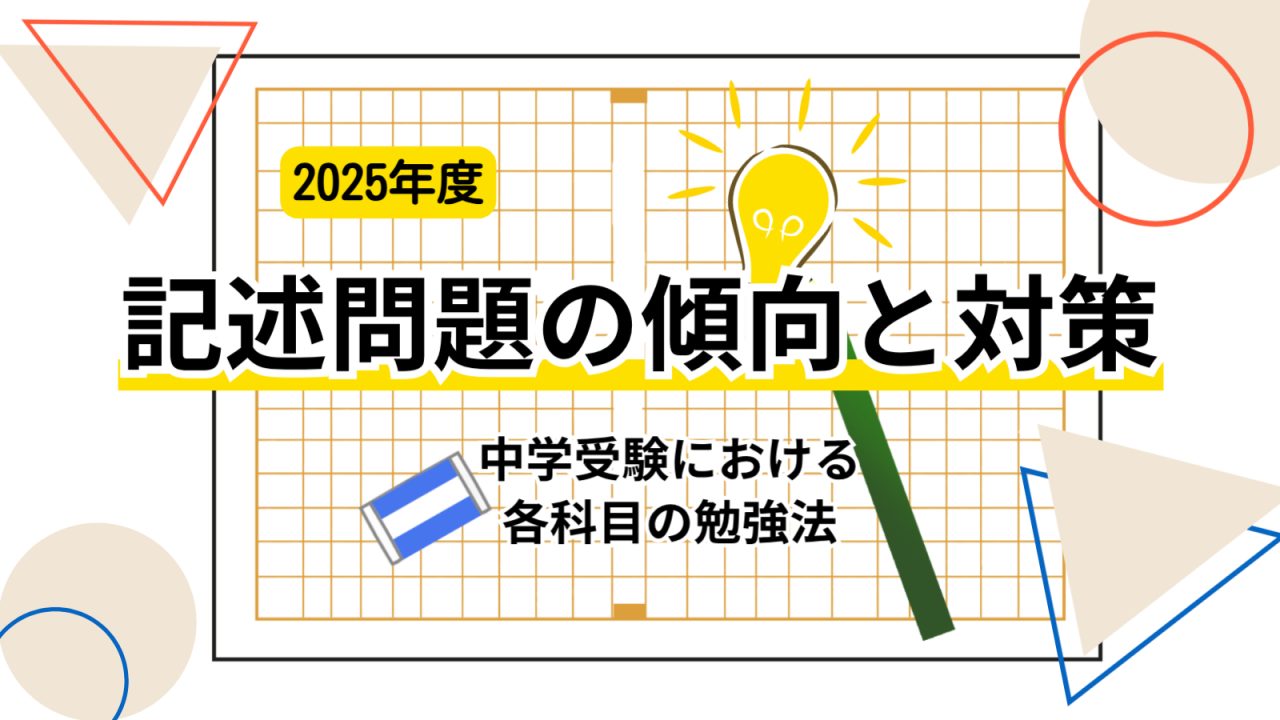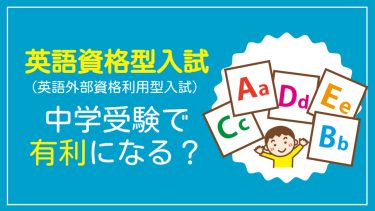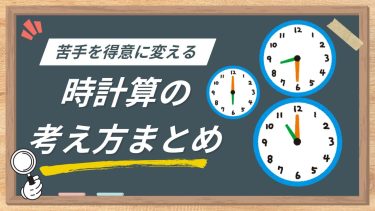中学受験において、記述問題に苦戦する子供は多いです。文章を読むことはできても、記述で得点するにはまた別の能力が要ります。この記事では2025年度の記述問題の傾向と対策について紹介します。
記述問題は国語以外でも

記述問題といわれて連想する科目はなんでしょう。多くの人が最初に国語を挙げるのではないでしょうか。しかし、理科や社会での記述問題も学校によっては定番です。算数でも途中式や考え方を記述する問題がよく出ます。つまり、昨今の中学受験では、どの科目でも記述問題が出題される可能性があるのです。複数校受験する場合、記述問題を避けて通るのは難しいでしょう。
どうして記述問題で点をとるのは難しいの?

記述問題の難しさは科目によって異なります。
たとえば、国語を例にすると、「抜き出し」の問題は比較的正答率が高いです。しかし、「説明記述」となると、途端に得点できない子供が出てきます。指定字数がボリュームアップするほど、難易度は上がります。設問の意図を汲む力、要点をおさえる力、まとまった文章を書く力。さまざまな力が必要とされるため、「本は好きなのに、記述問題で点数がとれない」というケースも珍しくありません。
算数では途中式や考え方を整理する力があるかどうかが問われます。答えを導き出すまでの過程を他の人にわかるように提示できるかどうかがポイントです。日頃から、過程をすっ飛ばして答えだけを出していると、読み手の理解を促すような書き方ができません。
理科・社会では、語句だけで完結する知識ではなく、背景にあるものを説明する力が必要です。理解が生半可だと答えられない問題がよく出題されます。
| 国語 | 設問の意図を汲む力、要点をおさえる力、まとまった文章を書く力 |
|---|---|
| 算数 | 途中式や考え方を整理する力 |
| 理科・社会 | 背景にあるものを説明する力 |
実際の問題例を見ていこう

実際に出題された問題例を交えながら、出題傾向を見ていきましょう。
国語における記述問題の出題傾向と対策
国語ではどんな記述問題が出ているのでしょうか。
タイトな試験時間内でどう解くか
国語で記述問題を多く出題する学校の中には、分量に対し試験時間をタイトに設定しているところが多くあります。本文を速読する力や問題を素早く解く力が問われる試験です。一問でも多く解き、合格ラインに到達できるように日頃から速読に取り組みましましょう。速読では段階的にスピードを上げていきます。読んだ作品のだいたいの字数と、かかった時間の記録をつけると、意識的に取り組めるようになっていくのでおすすめです。
CHECK!!
速読スキルは必須だよ
「指示語」の示す先を考える問題
たとえば開成の2025年度の問題を見てみましょう。大問一の出題は古内一絵の『百年の子』からです。小問三つはすべて記述問題で、説明記述ばかりでした。字数指定はありませんが、解答欄は二行、もしくは一行半のスペースとなっていて、適当な文章量で埋めなければなりません。
たとえば、問一ではとある登場人物が児童文学の仕事において重視していることを説明するよう求めています。「それが児童文学の仕事だ」という台詞を受けての問いなので、「それ」という指示語が示す箇所をひとつ抜き出せばよい、と考える子供は多いでしょう。その発想自体は間違っていないのですが、問題は「それ」が指し示す範囲です。本文におけるわかりやすい箇所をひとつ抜き出せばよいという問題ではなく、複数の箇所から要点をまとめる力が求められる内容でした。
また、問三でも本文中の台詞にある「ああいう誠実さ」とはどういうことかを説明せよという問題が出ました。これも問一同様に、指示語がなにを示すのかを考える問題です。解くためには、指示語に至るまでの文章の流れを読み返していきます。本文では、抽象的な話を先にし、続いて具体例を挙げています。「ああいう誠実さ」の具体例が直前に提示されていることを受けて、そちらを答えに落とし込んでしまう子供も多いことでしょう。しかし、この問題ではひとつの具体例の話だけをしているのではないので、抽象的な話のほうから抜粋しなければなりません。
指示語の問題というと、比較的簡単なイメージがあるかもしれませんが、難関校では昨今間違えやすい問題が出題されています。
理由を説明させる問題
記述問題の定番のひとつに、理由を説明させる問題が挙げられます。登場人物がある行動を起こした理由、ある考えに至った理由を問う問題が出ます。
たとえば、2025年度桜蔭中学校の国語大問二では、植松三十里の『イザベラ・バードと侍ボーイ』から出題がありました。五つの小問のうち、登場人物の心情を記述する問題が二問も出ています。
理由を説明させる問題では、文末表現に注意しなければなりません。最後を「から」もしくは「ため」で終わらせる文章がないのはNGです。難易度の高い記述になればなるほど、要約能力も求められます。一文を抜き出して多少手を加えるだけでよいような簡単な問題ではなく、作中の流れを把握し、要点をおさえた文章を書くことが求められるのです。
特に登場人物の心情を説明させる問題は、心情の変遷を理解していないと答えられません。変遷を追いきれない子供は多いので、物語文を読むときに、該当箇所すべてに線を引いていくといった意識的な取り組みが必要です。
説明記述は指定箇所を踏まえて解くものも
記述の分量の多さで有名な学校のひとつに麻布中学校があります。麻布中学校では解答欄のほとんどを記述問題が占めていて、しかも一問あたりの書く量が多いので、時間との戦いです。2025年度の麻布の問題を見ると、本文の〇行目や△行目の傍線部の要素を踏まえて答えを記述するように求める出題がよくされています。こうして本文中の複数の箇所を踏まえて解かせるタイプの記述問題は麻布に限らず最近多いです。
自分の意見を書かせる問題も
慶應義塾湘南藤沢中等部をはじめとする学校でよく出題されるのが、意見を書かせるタイプの作文です。150字以内などの字数指定があることが多く、その中で自分の意見をまとめます。自分の意見をまとめる際は、意識的に伝わりやすさを目指してください。説得力をもって相手に読ませるにはなにを書けばよいのか、書き出す前にキーワードをメモしておくのがおすすめです。
算数における記述問題の出題傾向と対策
算数ではどんな記述問題が出ているのでしょうか。
途中式や考え方を書く問題
算数の記述では解き方を書き出させるものが多いです。日頃から途中式を省いてしまっている子供にとっては意外と難しい作業です。また、式だけではなく、考え方を文章や図解で書く問題を出す学校もあります。式や考え方を書かせる学校はとても多く、一例としては渋谷教育学園渋谷中学校が挙げられます。答えが違っていても部分点がもらえる可能性がある点が大きなメリットです。
CHECK!!
日頃から途中式を書く習慣を付けよう
スペースに必要な情報を落とし込む
渋谷教育学園渋谷中学校の解答欄は大きめですが、そうした学校ばかりではありません。限られたスペースの中に、伝わるように書くことが必要です。スペースが小さい場合は途中式の中で必要な要素を厳選してください。
理科における記述問題の出題傾向と対策
理科ではどんな記述問題が出ているのでしょうか。
基礎知識を問う問題から思考力を問う問題まで
理科では、基礎知識をそのまま落とし込めばよい問題から、データ等を踏まえての思考力が必要な問題まで幅広く出題されます。
たとえば、2025年度の筑波大学駒場中学校の大問五では、ニホンジカの増加について出題されています。その中の小問四では「なぜニホンオオカミが絶滅したことが、シカが増えた要因として考えられてきたのか」を問う問題が出ていました。食物連鎖の仕組みを理解した上で答えを出す問題です。基礎知識寄りの出題といえます。
2025年度の女子学院中学校の問題では、大問二の小問五で実験結果を見て実験者に何を質問してみたいかを書けと言う問題が出ています。実験の内容を説明すると、まず産卵経験のないコナガサムライコマユバチと四種のキャベツ株を用意します。コナガサムライコマユバチとは、コナガというガの幼虫に産卵する寄生バチです。この実験では、四種あるキャベツの中から二種類を選び、コナガサムライコマユバチがどちらのキャベツに何匹止まったかを調べています。設問は、実験結果をデータから読み取った上でなにを尋ねるのが有意義なのかを解く側に考えさせます。したがって、深い思考力が欠かせません。
CHECK!!
ただ暗記するだけでは得点するのは難しい
絵を添える問題も出題
武蔵中学校の理科では、2025年度の大問三で、三種類の葉を配布し、観察させる問題が出ています。どんな点に注目して観察するべきか「葉の」という書き出しに続く言葉を三つ書けという問題です。さらに、その「葉の」という書き出しで挙げた三つのポイントを踏まえ、それぞれの葉の絵を描くようにという問題も出題されました。葉の特徴を見分ける観察眼が求められます。このように文章だけではなく、絵を必要とする問題も出るので注意が必要です。
社会における記述問題の出題傾向と対策
社会ではどんな記述問題が出ているのでしょう。
データを読み取る問題・考察させる問題が多い
社会における記述問題では、解く側に考察させるタイプの問題がよく出ます。たとえば、洗足学園中学校の2025年度の記述問題を見てみましょう。
大問一の記述問題は、資料を見ながら千里ニュータウンの人口構成の変化と理由について答える問題でした。大問三の記述問題は、鉄道運賃及び料金の上限の設定や変更には政府の認可が必要であるとされている理由を述べる問題でした。大問一では、資料から必要な情報を読み取り思考できるかどうかが問われます。大問三では前問で切符と税負担の関係が指摘されているので、その指摘を足掛かりにして考えます。
他にも、渋谷教育学園渋谷中学校では、歴史分野で年表を見ながら書くタイプの記述問題が出題されました。年表に載っている出来事を追うことで、時代が陶器に与えた影響を考察する記述問題です。
また、時事分野の記述問題はさまざまな学校で広く出題されています。日頃から社会で起きている出来事に関心を持っておきましょう。
CHECK!!
日頃から時事問題に関心を持てるようにしよう
記述問題の数が多い学校も
渋谷教育学園幕張中学校の社会の入試問題では、記述問題を数多く出題しています。2025年度も各大問に複数にわたる記述問題が出題されていて、一見すると国語の解答用紙のようなレイアウトでした。記述問題はどうしても時間がかかるため、問題数が多い場合は時間配分を間違えず、確実に解くためのイメージトレーニングが欠かせません。
自分の学校に関連する問題も多い
渋谷教育学園幕張中学校の2025年度の問題を見ると、地理分野で渋谷教育学園渋谷中学校に関する問題を出題しています。こうした自校(この場合は関連校)に関する出題はさまざまな学校であります。
渋谷教育学園渋谷中学校の校舎の上部を斜めに設計している理由を考えさせる問題で、答えは「周囲の建物の日照を遮らないようにするため」「風通しをよくするため」でした。自校の立地や周辺環境と絡めて出題する学校は少なくないので、あらかじめ志望校のある土地について調べておくのもよいでしょう。
志望校の記述問題に対応できるようになろう

国語は特に記述問題の比率が高い学校ほど、試験時間がタイトになる傾向があります。時間内に終わらせるためには速読のスキルや時間配分の感覚を磨き、記述問題を多くこなして慣れておくことが必要です。要約や文末表現の選定をはじめ、確実に点をとるための技術を身につけるようにしてください。自分の意見を求められる学校もあるので、さまざまなトピックにおいて日頃から自分なりの意見を持つようにしましょう。
算数では式や考え方を書くことが求められます。限られたスペースの中で、採点者が評価できるような答案を書いてください。途中式を省いたり乱雑に書きなぐったりする癖がついている場合は早めに改めましょう。
理科では基礎知識を答えさせる問題から、思考力を問う問題まで幅広く出題されます。絵を描かなければならない問題が出ることもあるので、過去問を通して志望校の傾向に慣れておいてください。
社会では、図表からデータを分析して考察させる問題が多く出ます。時事関連の出題はさまざまな学校でよく見られますし、学校によっては自校の地理や歴史と絡めた出題もあります。
志望校の傾向を把握し、どの科目も早めに対策を練るようにしましょう。