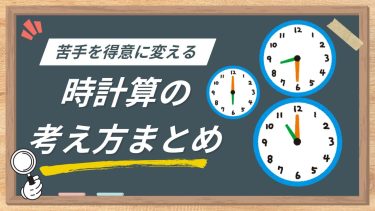受験生にとって悩ましい問題のひとつに行事と受験勉強の両立が挙げられます。この記事では、学校行事と受験勉強のバランスのとり方について紹介します。
学校行事が受験勉強に差し障るのはどんなとき?

学校行事が受験勉強の妨げとなってしまうのはどんなときでしょうか。
生活リズムに影響があるとき
朝練や居残り練習を必要とするような行事の場合は、生活リズムに大きく影響するため、受験勉強にどうしても差し障ります。勉強時間を減らさざるを得なかったり、塾の時間との調整が難しかったりすると、負担は大きいです。ただし、最近の学校では時間割内で進めるところのほうが多いでしょう。
よく聞くのは、野外学習や修学旅行への参加で塾に行けないケースです。二泊三日の旅行に行ったとして、その週の勉強を取り戻すのがどれだけ大変かは、受験生ならば多くの知るところでしょう。週テストのある塾では、一週間をひとつのサイクルとして、一日一日みっちりと詰まったスケジュールをこなしています。そのリズムが崩れてしまえば取り戻すのは生半可なことではありません。週テストでよい点数をとるのは一時的に諦めて、週末にひたすら復習するといった変則的な対応が必要になります。
体力的に負担が大きいとき
運動会をはじめとする運動系の行事では、どうしても体力を消耗してしまいがちです。終わったあと、受験勉強に身が入らず、塾や家庭教師の授業中に眠ってしまう子供も多くいます。結果、塾を休まないで済んでも、学習に遅れが生じてしまうパターンです。
行事前後の子供は不安定
行事の前後は気持ちの落ち着かない子供が多いです。幼稚園・保育園の先生や、小学校の先生から「行事前後はクラスが落ち着かなくなる」という話を聞いたことはないでしょうか。あるいは、子供が行事前後に落ち着きをなくして困った経験はないでしょうか。「行事前」ならともかく「行事後」というのはあまりピンとこない人もいるかもしれません。しかし、大きな行事は子供に緊張感を与えますから、反動もまた大きいものです。喜怒哀楽の振れ幅が大きくなったり、勉強に身が入らなくなったりするケースは珍しくありません。
行事はある種イレギュラーな出来事です。子供たち皆が柔軟に対応できるかというと、そういうわけではありません。発達特性や性格によって、見通しが立てられないことにストレスを感じたり不安感を持ったりする場合もあります。
学校行事の意義を改めて考えよう
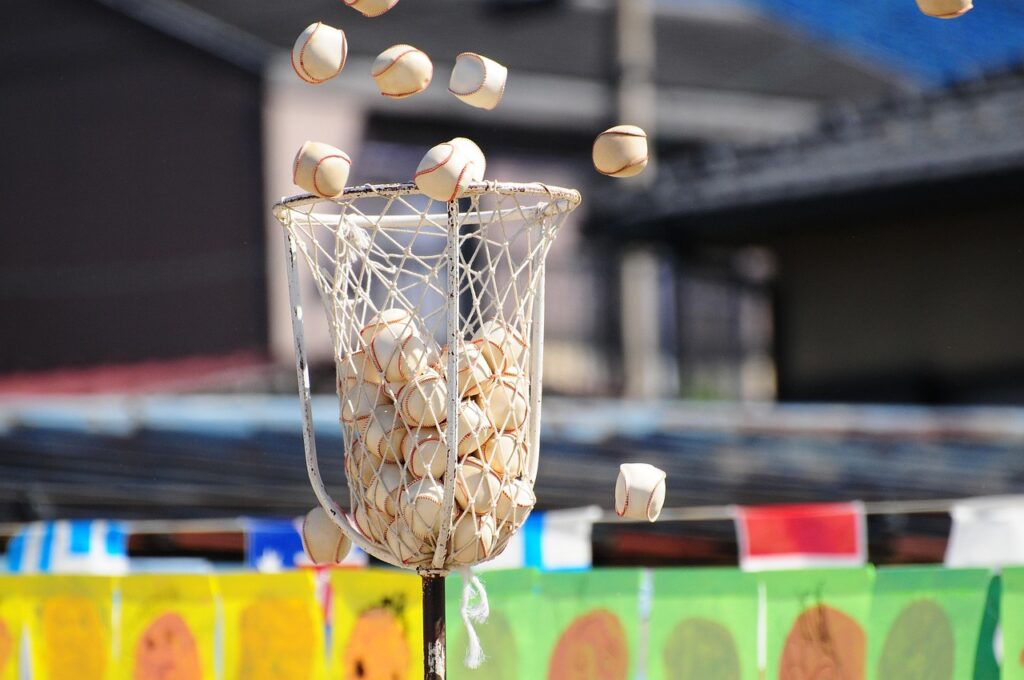
負担の大きさから学校行事を持て余してしまう前に、その意義を改めて考えてみましょう。
学校行事はかけがえのない思い出になることも
受験勉強に悪影響を及ぼすとなると、「学校行事、困ったな。面倒くさいな」と感じる保護者も少なからずいるでしょう。しかし、学校行事には学校行事の意義があります。
まず、子供にとって学校行事はかけがえのない思い出となるものです。小学校の行事では、クラスメイトと競い合ったり、ひとつの作品を仕上げたり、ときにはクラスメイトたちと旅行に行ったりします。それは学校行事でしかできない貴重な経験です。
協調性や社会性の育成に
学校行事は、協調性はもちろん、社会性や創造性を育成する場としても機能します。受験の合否が人生設計に大きく影響を及ぼすことは事実でしょう。しかし、だからといって学校行事を「要・不要」の天秤にのせてしまうのには慎重になったほうがよいです。多くの場合、学校行事でしかできない貴重な経験は、子供が将来に向けて歩み出す上で必要な力となります。
POINT!!
日頃から子供とよく会話して希望や思いを共有してもらうことが大事です。
行事による影響を軽減するためには

行事に振り回されて勉強が進まないときはどうすればよいのでしょうか。
塾や家庭教師に行事予定を事前に伝える
塾や家庭教師には早い段階で行事の予定を伝えておきましょう。臨機応変に対応してくれる先生であれば、どうやって行事で生じる負荷を軽減するかを一緒に考えてくれます。たとえば、宿題量を調整したり、先取り学習をしたりといった対応です。
勉強時間の見直しをする
勉強を効率的に進められる人は限られています。たとえば、子供が「今から二時間勉強する」と決めて取り掛かったとして、実際に集中して取り組めている時間は何分の一かでしょう。子供の大半は着手するのが遅く、ようやく始めても集中力が続かない子供のほうが多いです。
行事によって勉強時間を縮小しなければならないときは、無駄な時間を削除する必要があります。そのためにはまず学習計画を時間ではなく中身で設定するのが鉄則です。「二時間勉強する」ではなく「この問題集を五ページ進めて間違い直しまでやる」といった目標の立て方をしましょう。もちろん、いざ一生懸命解いてみたら難問続きで二ページしか時間内に終わらなかったというケースもあり得ます。その場合はその場合で構いません。
計画を立てれば、必ずズレは生じますし、そのズレは翌日以降調整すれば大丈夫です。やるべき内容が明確に見えていることが大切です。見通しを立てられれば、効率はある程度上がります。
移動時間を有効に
机に向かう時間を確保するのが難しいようであれば、移動時間を有効に使いましょう。移動中できることをあらかじめピックアップしておきます。たとえば、大手塾に通っている子供の場合、電車で移動することが多いです。行き帰りの時間で暗記カードやチェックペンで塗った箇所の確認などをやれば効率化が図れます。
子供の話を傾聴する
行事前後の子供は精神的に落ち着かないことが多いです。そのため、周囲が意識的に、子供の話を傾聴するように努めるとよいでしょう。かかえている不安だったり焦燥感だったりを共有してあげることで、少しは気持ちが落ち着く可能性があります。最近は、親子ともども忙しい家庭が多く、ゆっくり話をする時間は限られますが、だからこそ行事前後は意識的に取り組むことをおすすめします。
就寝・起床の時間をずらさない
予定が詰まっていると、たいていの子供は寝る時間を削る判断をしてしまいます。しかし、睡眠時間のリズムを崩すと、集中力は著しく低下して、やがて気持ちも安定しなくなってしまいます。就寝・起床の時間をずらさないようにして、いかに時間内でやるべきことを終わらせるかを考えましょう。
ただそうはいっても、効率的に予定を組めたとしても、いつもどおりの内容を短い時間内でこなすのは難しいです。内容を縮小せざるを得なくなるでしょう。けれど、無理に全部やろうとすると、後半で体がついていかなくなりますし、万一体調を崩してしまったら、結果的により長くタイムロスすることになります。就寝・起床の時間は今までのままにしておいてください。
保護者が行事を面倒くさがらない
保護者の感情の機微に対し子供は意外と敏感です。「面倒くさい」「受験の邪魔」「できれば休ませたい」と思っていると、その気持ちは伝わってしまいます。そうすると、子供自身が楽しい気持ちで行事に参加するのは難しくなってしまうので、保護者はなるべくポジティブな気持ちで見守ってあげてください。
周囲の理解が得られていないときは
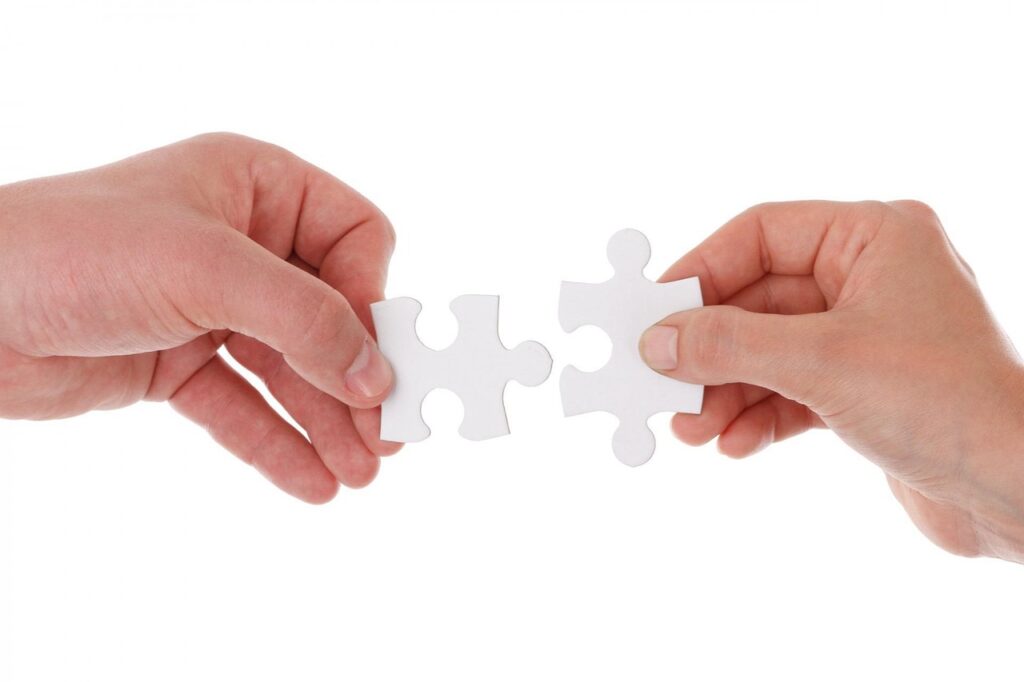
行事参加の影響について、学校や塾、家庭教師など周囲の理解が得られないときにはどうすればよいのでしょう。
まずは面談の場を設けよう
それぞれの先生と連絡をとり、話し合いの場を設けましょう。その際には抽象的な説明だけに終始しないようにすることをおすすめします。どのぐらい難しい状態にあるかを数字で可視化してみてください。「忙しい」「受験が大切」「勉強時間が不足」といってもなかなか実際のところは伝わらないものです。具体的な日程や時間を共有するほうがはるかに伝わりやすいです。学校にしろ、塾にしろ、家庭教師にしろ、それぞれの立場での理解が欠かせません。子供にしわ寄せがいかないよう、大人がはっきりと「現状、こういう状態である」と詳細を共有してください。
友人間のトラブルに親はどう対応する?
大人の理解が得られても、子供同士の間での理解が得られるかは別問題です。たとえば、行事への参加が中途半端になってしまっていて、他の子供から白眼視されるケースもあります。子供同士の揉め事に発展してしまうと、メンタル面での負担が大きいです。子供間のトラブルはなかなか正直に打ち明けてくれるものではありません。行事前後は子供の様子を注視するようにし、様子がおかしいときはすかさず話をするようにしましょう。
子供が行事を嫌がっている場合はどう対応する?

子供が行事を嫌がっている場合は、また事情が変わってきます。
嫌がっている原因を聞いてみよう
子供が行事を嫌がっている場合は、なぜ嫌なのかについて聞いてみましょう。嫌な理由が深刻なものなのかどうかを見極める必要があります。友人関係なのか、学校があまり好きではないのか、保護者の気持ちを汲んでいるのかによって対応は変わってきます。正直に話してくれるとも限らないので、日頃から子供とよく会話し、様子を知っておくことが大切です。
もし、友人関係の悪化や学校へのモチベーション低下に原因があるのなら、担任に相談することも検討してください。学校での様子を早めに知っておきましょう。原因を突き止め、子供を悩ませている問題を共有しなければなりません。
嫌な場合は欠席も含めて検討を
行事は楽しい思い出になるからこそ、参加する意義のあるもので、嫌な思い出になることが最初からわかっているのなら、無理に参加させる必要性はありません。思いきって欠席も選択肢に入れてみてください。
ただし、受験に対する不安感や保護者への気遣いが原因の場合は、すぐに休ませるべきではありません。親子での話し合いが先です。
POINT!!
受験前は親子ともに気持ちがピンと張りつめて、不安感もあっという間に伝染してしまいます。そういうときほど気分転換が必要になるので、行事への参加が効果的な場合もあります。
行事後、再スタートを切るには

行事後、気持ちを切り替えて再スタートをきるにはどうすればよいのでしょうか。
スケジュールを可視化しよう
一度崩れた生活リズムを取り戻すのは難しいです。スケジュール表を作成するなどして、ルーティンを可視化して動くようにしましょう。感覚的に動くとどうしてもズレが生じてしまうので、表を確認しズレを修正しながらひとつひとつやるべきことを進めていきます。そうしているうちに段々とリズムが整ってくるものです。
疲れが出やすい時期なので気をつけよう
行事が終わったあとは気のゆるみから風邪をひきやすい時期です。ケアをすることが大切になります。忙しいですが、適度に体を動かしたり栄養をとったり十分に体をいたわるようにするとよいです。
思うように進まなかった部分をやり直そう
時間が足らず、思うように進まなかった問題が少なからずあるはずです。見直しをし、解き残しがないようにしましょう。塾の週テストや模試、家庭教師の確認テストがあったなら、間違えた問題をすべて解き直してください。スラスラ解けるようになるまで何度でもやり直します。
バランスをとるには保護者のサポートやケアが必要

受験勉強と学校行事なら、基本的には学校行事を優先するようにしましょう。その学年でしか経験できないことですし、子供にとってはかけがえのない思い出です。加えて、協調性や社会性を身につけられ、達成感を得ることができます。子供にとっては大きな成長につながる経験です。
しかし、受験勉強より学校行事を優先すれば当然、その分のしわ寄せはあります。勉強が思うようにいかず遅れが生じたり、その週のテストで点数がとれなかったり、生活リズムが乱れてしまったりします。問われるのはそのとき、保護者がどのように子供をケアし、サポートするかです。
週の勉強を無理のないものに変えて、その遅れを復習で追いつけるようにしなければなりません。そのためには、塾や家庭教師および学校との連携や、学習効率の見直し、睡眠時間の確保など、さまざまなアプローチが必要です。学校行事と受験勉強のバランスをとるためには、保護者のサポートやケアが欠かせません。
一方で、子供が人間関係や学校への苦手意識を理由に、学校行事への参加を希望しない場合もあります。その場合は子供とよく話をし、学校にも状況を確認するようにしましょう。子供が嫌がっている場合は無理に参加するよう勧めるのは避けたほうがよいです。