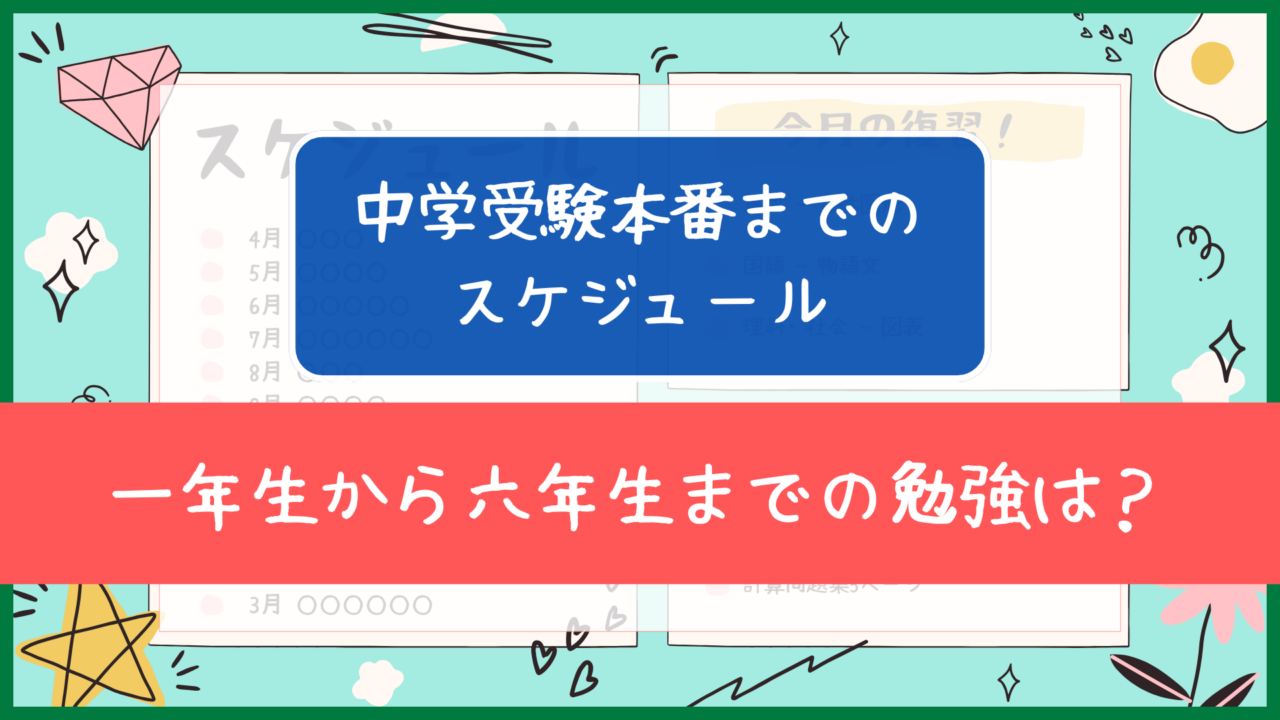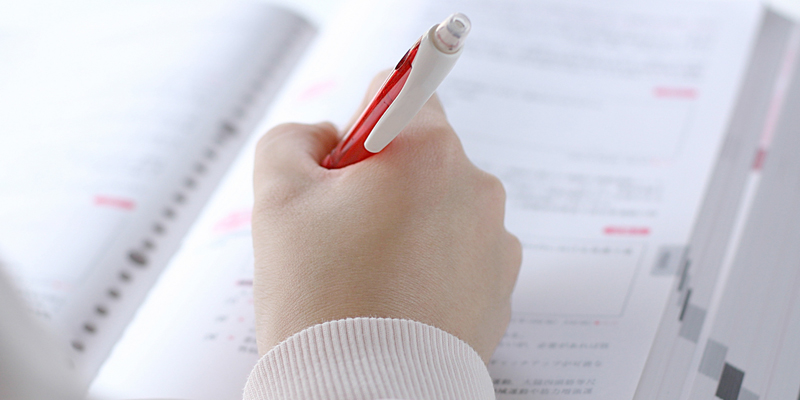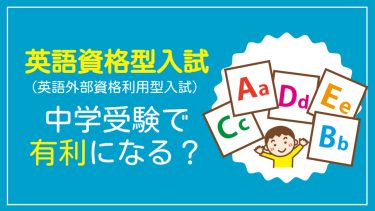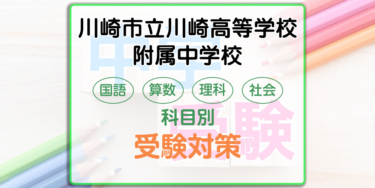中学受験本番までにやるべきことはたくさんあります。低学年から高学年までにかけて、具体的になにをするべきか、あらかじめ知っておくと動きやすいです。この記事では、各学年でやるべき内容を紹介します。
一年生のうちにやるべきことって?

入学したての一年生がやるべきことを見ていきましょう。
詰め込む前に慣れる時間を
最初は学校のペースに慣れることが大切なので、いきなり中学受験対策のために、詰め込み学習をさせるのは避けましょう。幼稚園や保育園から小学校に進学したばかりの子供は、環境の変化についていくだけで必死です。「学校についていけるようにする」「宿題をこなせるようにする」と段階を踏み、慣れてきてから必要な家庭学習を追加していきます。家庭学習は親がその都度、指示を出すのではなく、ある程度枠組みを確立しておいてください。その枠組みの中で調整していきます。
計算力は段階的に上げていく
一年生の算数では、基本の計算を身につけることが目標です。計算は段階的に身につくものなので、たいていの子供は指を曲げてカウントするところから始まります。指での計算は見ていてもどかしいかもしれません。しかし、慣れれば自然と使わなくなるので、気長に見守ってあげてください。
漢字の学習のペースはそれぞれ
文字の学習の中で、一番苦戦する子供が多いのが漢字の学習です。漢字の習得速度もまた、計算と同様、個人差が大きいといえます。一度書いて覚える子供もいれば、何度書いても間違えてしまう子供もいます。「字を書く」ことへの得意不得意の差は顕著です。また、漢字の場合、「覚えてもすぐ忘れてしまう子供」もいます。完璧に覚えさせても、翌日には半分以上を忘れてしまっている、という事態は珍しくありません。漢字の学習のペースは人それぞれです。一気にたくさん覚えさせる必要はありません。ただし、何度も復習させましょう。
なにより、この時期からなるべく丁寧にとめ・はね・はらいを意識して書く習慣を身につけることが大切です。字の癖はなかなか直らないので最初が肝心といえます。
読書の機会を持てる環境作りを
子供が読書できる環境を整えてあげましょう。たとえば、リビングに本棚を置き、すぐに手を伸ばせる環境を作るのはよい方法です。絵本用の本棚だと、本の表紙が見えるような収納方法ですから、子供が興味をもって手を伸ばす回数が自然と増えます。まずは機会を用意してあげることが大切です。
一年生のうちにやるべきこと
焦ってすぐに中学受験に向けて動き出すより、環境の変化に慣れさせることを優先してください。計算や漢字の習得には個人差があるので、まずは一つ一つ丁寧に取り組む習慣をつけることと、環境作りが重要になります。
二・三年生のうちにやるべきことって?
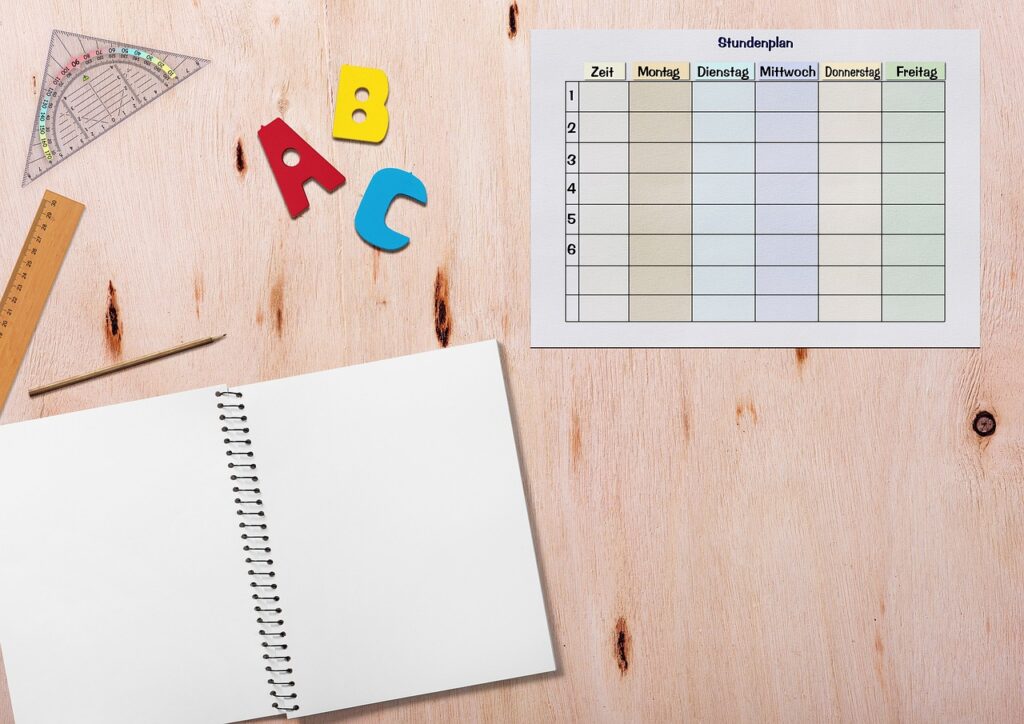
学校生活にも慣れてきたタイミングでやるべきことを見ていきましょう。
自主的に学習する力を育成しよう
保護者や教師の指示どおり勉強ができる子供は伸びます。しかしもっと伸びるのは主体的に学習に取り組める子供です。そのため、自主的に学習する力を育んでいきましょう。まず、基本のルーティンを共有し、追加で取り組むべき内容があれば「なぜそれが必要なのか」を共有するようにします。今、自分にどういう力が足りないのかを子供自身に考えさせる機会を作りましょう。自分に必要な学習がなにかについて、すぐにわかるようになるわけではありません。考えさせる機会を作ることが重要です。
受験用の難しめの問題にチャレンジ
中学受験塾が出している低学年向け問題集を解かせるのがおすすめです。学校よりも少し歯応えのある問題を解くことで、実力を養うことができます。ただ、学力の下地がないと、難しめの問題集は逆効果です。まずは基本を理解することを最優先にしてください。レベルに合った問題を解くことが大切です。そういう意味では幅広いレベル別に構成されている問題集を使うことをおすすめします。基礎レベルしか解けない時期があったとしても、やり込んで応用レベルにステップアップすればよいです。
子供の関心から読書を広げよう
低学年のうちの読書は学力アップに必要です。なぜなら、文章を正しく理解できることは科目を問わず欠かせない能力だからです。
図書館や書店に行く機会を多く設ければ、読書好きな子供は自ら進んで本に手を伸ばすでしょう。しかし、中にはなにを読んだらよいのかわからないという子供もいます。そうした子供には、教科書に載っている話の続きを読ませてあげたり、あるいは好きなゲームやアニメ、漫画のノベライズを買ってあげたりするとよいです。
一例をあげるなら、角川つばさ文庫から出ている『星のカービィ』シリーズあたりだと読みやすいでしょう。いきなり小説の文庫本はハードルが高いということであれば、KADOKAWAの『どっちが強い!?』シリーズや、朝日新聞出版の『サバイバル』シリーズといった、理科の知識も身につくような漫画が人気を集めています。『サバイバル』シリーズはNHKでアニメ化もされているので、アニメを入口にして興味を持たせる方法もあります。
とにかく好きになれる本を見つけてあげてください。親が読ませたい本を選ぶのではなく、子供が慣れ親しめる作品をチョイスしましょう。
知的好奇心を引き出す機会を
受験勉強は学年が上がるごとにスケジュールがタイトになっていきます。家族で外出をする機会も確実に減っていくため、低学年のうちに科学館や博物館といった場所に連れて行き、興味関心を伸ばすことをおすすめします。科学館や博物館は普通に行くだけでも面白いですが、小学生から参加できる、より専門性の高いイベントを開催しているところも多いです。多くの場合は事前予約制なので、ホームページをチェックしておきましょう。
中学受験について話し合っておこう
中学受験は親主導で進んでいくことがほとんどです。しかし、子供の同意を得ないまま親が一方的に進めてしまうことはおすすめできません。子供のモチベーションのためにも早い段階で「なぜ中学受験をするのか」について話し合っておきましょう。
中学受験塾や家庭教師の受験対策コースを探そう
首都圏では、小学三年生の二月ごろから中学受験塾に通うのが一般的です。新四年生コースが始まる時期であり、本格的に受験勉強が始まります。家庭教師で受験対策を考えている場合も同様で、中学受験対策のコースや、各中学受験塾に対応する補習コースを用意している派遣センターはたくさんあります。
塾探し、家庭教師探しは早めに動きましょう。三年生の早いうちに、見学に行ったり季節講習に参加させたりして、気になる塾や家庭教師派遣サービスをチェックしておくことをおすすめします。低学年の季節講習は期間も長くありませんし、知的好奇心を引き出す方向に重きを置いているためお試しにはちょうどよいです。
なお、人気の塾では新四年生コースから入るのが難しいケースもあります。その場合はもっと下の学年のうちに入塾しておくとスムーズでしょう。
二・三年生のうちにやるべきこと
読書の重要性が一気に高まります。まずは好奇心を引き出す機会を作り、自主的に学習する力を育成してから本格的な中学受験対策を始めましょう。
四・五年生のうちにやるべきことって?

塾や家庭教師の受験コースを利用している場合は、いよいよ本格的に受験対策が始まります。どのように進めていけばよいのでしょうか。
四年生は早めに学習サイクルを確立しよう
四年生になったら受験勉強が本格的に始まります。そのため、早めに学習サイクルを確立するようにしましょう。授業のある曜日を軸に、宿題や予習復習をいつやるのかを決めていきます。四年生は五、六年生に比べれば、まだ量も多くないですが、それでも中学受験の難しい内容を一定ペースでこなしていく負担は大きいです。本人にとって無理なく、それでいて成績が上がっていくペースを見極めなければなりません。
週テストのある塾は、週テストまでに単元を仕上げ、週テストで間違えた問題を復習するのがひとつのサイクルです。居残りができる塾ならば、授業後その場で復習や宿題に取り組んで、わからないところは先生に質問すると効率がよいでしょう。翌日以降は類題を解く時間に回すこともできます。
効率のよいサイクルを早めに確立できる子供ほど、成績が伸びやすい傾向にあります。
五年生は置いていかれやすい時期
四年生のペースならなんとかついていけていた子供も、五年生になると学習内容の急激なボリュームアップについていけなくなるケースが多いです。五年生は置いていかれやすい時期なので、「まずい」と思ったら塾や家庭教師にすぐ相談しましょう。集団授業塾についていけない場合は個別指導や家庭教師を併用するのもひとつの手です。四年生までなら、多少効率が悪くても真面目に取り組んでいれば成績は上がります。しかし、五年生以降は要領よく勉強していかないと時間が足りません。
学校見学を本格的に
低学年のうちから学校見学には行っておくとよいのですが、本格的に回り始めるのは四年生ぐらいからがおすすめです。受験直前である六年生では、回れる学校数は時間的に限られています。四、五年生ぐらいから本格的に回るというのがちょうどよいでしょう。学園祭、オープンスクール、学校説明会、合同説明会といったイベントに参加しておきましょう。
模試を受けてみる
五年生になったら、一、二回は模試を受けておきたいところです。自分の立ち位置を知ることで、学習計画を見直せます。
四・五年生のうちにやるべきこと
早い段階で効率の良い学習サイクルを確立することが受験成功への近道になります。また親、子ともに塾や家庭教師の先生に質問や相談をする機会を増やすことも重要です。
六年生のうちにやるべきことって?
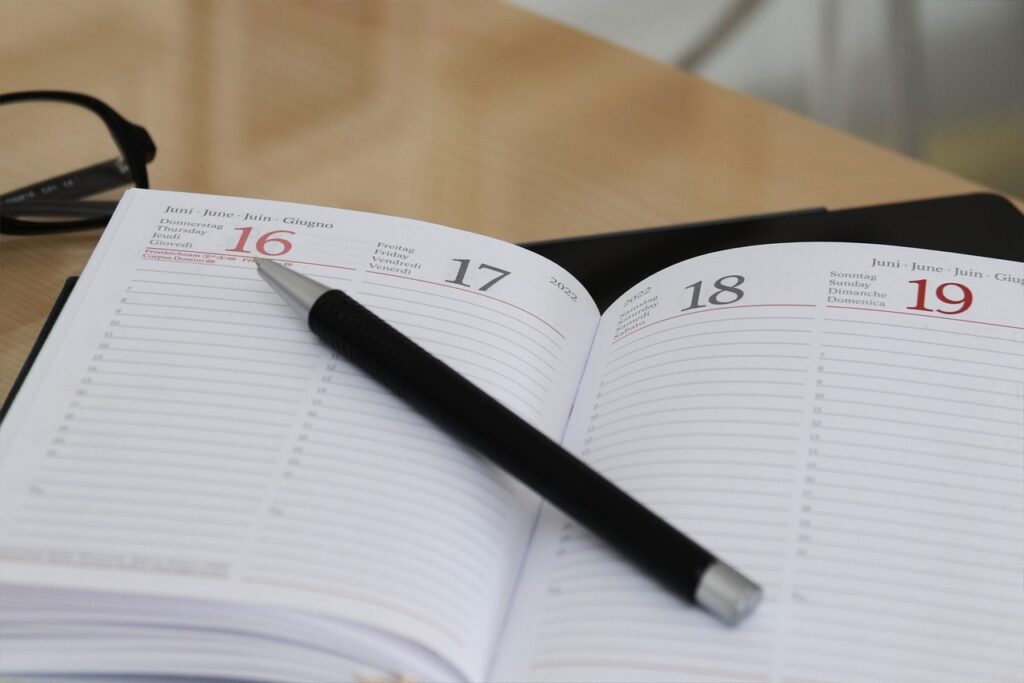
本番を控えた六年生のやるべきこととはなんでしょう。
前半は受験範囲の復習、後半は志望校別の対策
六年生の前半は受験範囲の勉強です。すでにひと通り終わっている場合も、苦手単元を中心に、復習に時間を割きます。夏休み後は志望校別の対策へとシフトしていきます。シフトするタイミングは難関校ほど早いです。
模試を積極的に受けて成績を分析する
六年生の間は何度も模試を受けます。四谷大塚の合不合判定テスト、サピックスのサピックスオープン、日能研の全国公開模試、首都圏模試センターの統一合判などの中から、自分に合ったものを受けます。六年生の夏休みまでに受ける模試は3~4回ぐらいで、六年生の夏休み後は毎月1回程度です。
必要な追加講習を受ける
学校別対策の講習であったり、季節講習以外の追加講習であったりと、六年生はさまざまなオプション講習が用意されています。なにを受けるべきか早めに相談し、決めておきましょう。
遅くても9月までに志望校決定
9月から過去問を始める子供が多いので、できれば9月までには受験する学校をだいたい決めておきたいものです。なお、難関校を目指す子供ほど早い時期から過去問に取り組む傾向があるので、より早めに受験校を絞り込みたいところです。
10月、11月は必要書類の準備を
秋に入ったら、改めて受験校の願書の入手方法を確認しておかなければなりません。ホームページや窓口での配布もあれば、学校説明会での配布もあります。また、願書だけではなく、調査書が必要な学校もあります。入手したら学校の先生に記入をお願いしておきましょう。
なお、受験本番に備えて、インフルエンザの予防接種を受けておいてください。
1月は出願忘れのないように
出願期限は学校によって違いますが、1月に出願を受け付けている学校は多いです。入試ギリギリまで受け付けてくれている学校がある一方で、もう少し早い時期に締め切る学校もあります。忘れないようにカレンダーに書き込んで、親子で共有しておきましょう。1月は早い学校だと受験が始まっています。年明けから受験のために学校を休ませる家庭もありますが、その場合はトラブルを避けるためにも、よく学校と相談してからにしてください。
2月はいよいよ受験本番
2月は受験本番の時期です。多くの学校がこの時期に受験を実施しています。実力が発揮できるように体調を整えておいてください。
六年生のうちにやるべきこと
本格的な志望校別の対策をどのタイミングからスタートするべきか、塾や家庭教師に相談しながら決めましょう。また、積極的に模試を受けましょう。出願に向けた書類に不備があると全てが台無しになるので、見える位置にカレンダーを貼って親子で共有しながら中学受験に向けて頑張りましょう。
各学年でやるべきことを忘れず準備万端で
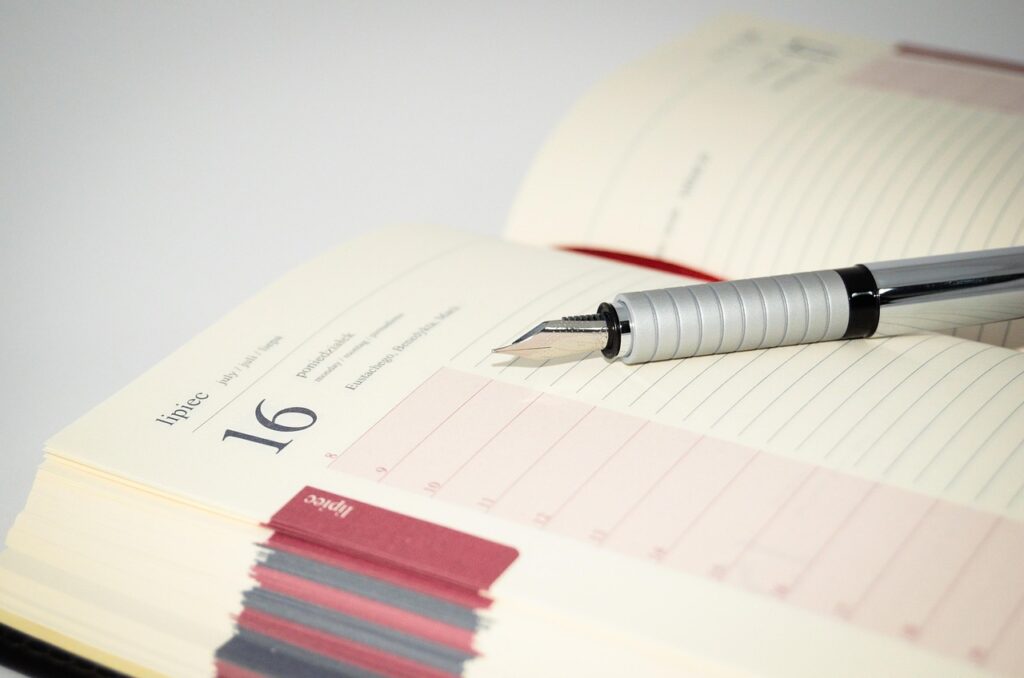
学年が上がれば上がるほど、目の前の受験勉強だけで手いっぱいになります。早め早めに動いて、必要な準備を進めていきましょう。学習の下地となる知的好奇心の育成や学習習慣の定着化は、低学年のうちから取り組みたいところです。受験についての話し合いや志望校見学、締め切りがある書類の準備なども順次進めていきましょう。
六年生になってからは、無駄にできる時間はありません。学力を固め、志望校を選定します。必要であれば、オプション講座を受講し、対策を練りましょう。
秋になると手続き関連でやることが増えてきます。調査書は学校の協力が必要です。願書にしろ、調査書にしろ、締め切りがあるものなので、遅れないように管理しなければなりません。カレンダーにすべての予定を書き込んでおくことをおすすめします。家族全員で共有しておきましょう。