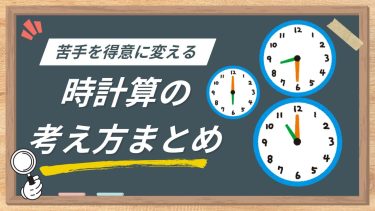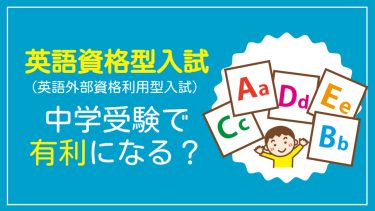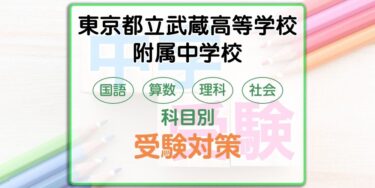受験生が最も注力するべきものは勉強ですが、効果的に学習するためには、睡眠や食事といった生活面も大切です。とりわけ、夏は暑さから体力が削られ、食が細くなる子供が増える傾向にあります。この記事では、受験生の夏バテ対策について紹介します。
夏休みは睡眠と食事を大切に

受験生にとって、夏は大切な時期です。夏休み中にどれだけ苦手単元を克服できるかが合否を分けるカギとなります。その一方で、夏休みは健康を損ねやすい時期です。外の暑さとクーラーのきいた室内の温度差に、体調がおかしくなってしまう子供は珍しくありません。
こうした不調に対し、家庭でできるサポートは第一に生活習慣の見直しです。受験生の睡眠時間は、学年が上がれば上がるほど短くなる傾向にあります。しかし、睡眠不足は集中力の低下や体調不良の原因になりやすいものです。また、睡眠だけではなく食事も大切にしないと、消耗が激しい時期ですから体力を維持できません。
受験生は睡眠の見直しを

受験生は日々の睡眠時間が足りているかどうか見直していきましょう。
受験生の睡眠時間ってどのぐらい?
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、小学生は9~12時間の睡眠が推奨されています。しかし、勉強との兼ね合いで睡眠時間を確保するのが難しい受験生は多いです。せめて健康のためには8時間程度の睡眠時間は確保したいもの。実際には、毎日6時間程度しか眠れていないケースも珍しくありません。
受験生の睡眠不足
睡眠時間が6時間程度でも大丈夫な子供がいないわけではありませんが、頑張り過ぎて、夏期講習や授業中に眠ってしまうようでは本末転倒です。「夜遅くまで勉強したせいで起きているのが辛い」となると、受験勉強のサイクルが確立できなくなってしまいます。「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、睡眠不足による学業成績の低下は指摘されています。
また、同資料には「思春期が始まる頃から睡眠・覚醒リズムが後退し、睡眠の導入に関わるホルモン(メラトニン)の分泌開始時刻が遅れることで、夜寝る時刻が遅くなり、朝起きるのが難しくなる傾向がみられます」とも書かれています。小学六年生はまさに多くの子供が思春期の始まりを迎える頃合いです。つまり、たとえ受験勉強を予定時間どおり切り上げられても、早寝早起きを維持するのが難しい年頃であるといえます。
生活リズムを確立しよう
基本的に勉強は「何時間勉強する」ではなく「何ページまで勉強する」という発想で臨むべきものです。そうしないと、ダラダラしているだけで寝る時間が来てしまいかねません。「なんとしても〇時までに終わらせる」という意志の力と集中力が必要です。しかし、意志の力や集中力があれば、計画どおりに進むわけでもありません。就寝時間がずれ込んでしまいそうなときは、翌日の負担を軽減するために、寝る時間のほうを優先してください。
受験生の食事ってなにに気をつけるべき?

受験生の食事の注意点について見ていきましょう。
朝食で体調を整えよう
受験生は朝必ず食事をとる必要があります。「健康づくりのための睡眠ガイド2023」にも、「朝食を摂らない生活習慣は、朝〜午前中に日光を浴びない生活環境と同様に、睡眠・覚醒リズムの後退を促すことが報告されています」との記載があり、睡眠と食事には深い結び付きがあると指摘しています。
夏期講習中のお弁当は負担軽減のスタイルで
塾の夏期講習が午前午後に跨るところでは、お弁当持参のケースが多いです。基本的には家庭で手作りですが、中には塾が宅配弁当サービスと契約しているところもあります。また、コンビニなどに買い出しに行く子供も珍しくありません。
お弁当の場合、手の込んだお弁当を作っている家庭はごくひと握りです。冷凍食品等でなるべく簡略化しましょう。すべて手作りでは家庭の負担が大きいですし、それによって作る側がストレスをため込んでイライラしてしまっては、受験の応援のつもりが逆効果になってしまいます。三食で見たときに、バランスが取れるようにすれば問題ありません。
ただし、食べ物が痛みやすい季節なので、温度管理だけは徹底しましょう。お弁当を詰めるときは必ず冷ましてから入れてください。保冷剤を入れた保冷バッグを使うのも有効です。逆に、ランチジャーやスープジャーを持たせて、温かいものを食べられるようにするのもよいでしょう。お腹が膨れすぎて眠くなるのも困りものですが、だからといって少ない量で小腹が空いてしまっても集中できません。子供にちょうどよい量を聞いてみましょう。
休憩時間の間食も効果的
夏期講習後に居残りをする子供たちが、食事スペースでちょっとしたお菓子で気分転換を図るのもよく見る光景です。集中力が切れたときの甘いものは効果的です。塾で許可されていない場合は別ですが、小腹が空いていては集中できないのでちょっとしたお菓子での休憩時間を持てるとよいです。
ただし、匂いの強いものや、食べカスが散らばりやすいもの、食べるのに時間がかかるものは避けましょう。パクッと口に入れてすぐに勉強へと意識を切り替えられるものがよいです。
勉強に効果的と言われる栄養素って?

勉強に効果的と言われる栄養素とそれを豊富に含んでいる食べ物を紹介します。なお、栄養素はバランスよくとってこそ。身体にいいからと言って必要以上に摂る必要はありません。
オメガ3脂肪酸(DHA・EPA・a-リノレン酸)
一時期非常に話題になったDHA。サケ、イワシ、マグロ、サバなどに多く含まれています。脳機能の維持や記憶力向上に役立つと言われている栄養素です。現代人は魚より肉を食べる機会が多くなりがちですが、意識的に青魚を取り入れるとよいでしょう。
EPAは心身の健康維持に役立ち、気分の安定に関与する可能性も研究されています。a-リノレン酸はアマニ油やエゴマ油、くるみなどに多く含まれていて、体内で一部DHAやEPAに変換されます。
複合性炭水化物
穀物・芋類・豆類などに多く含まれていて、血糖値の上昇が緩やかなのが特徴です。
腹持ちもよく、脳のエネルギー源であるグルコースを供給するため、夏期講習で忙しい期間にはもってこいの栄養素といえます。
レシチン
レシチンは、記憶や学習において重要な働きをする神経伝達物質アセチルコリンの材料になります。卵黄や大豆、アーモンド、うなぎ、レバーなどに豊富に含まれている成分です。
鉄分
脳に酸素を運ぶためにも鉄分は欠かせません。鉄不足だと、頭がぼーっとしてしまうことがあります。女性は特に鉄分不足になりやすいので、意識的に摂取することが必要です。豊富に含まれているのはうなぎやレバーですが、一般的にはあまり頻繁に食べる機会があるものではないでしょう。その場合は、鉄分入りの菓子や乳製品などがいろいろ出ているので試してみることをおすすめします。
ビタミンB群
ビタミンB群はさまざまな種類があります。たとえば、B1は不足すると疲労感を招きます。B2は「発育のビタミン」とも呼ばれ、成長期には欠かせない栄養素です。B6とB12は神経伝達物質の合成を行うのに欠かせません。ビタミンB1は豚肉、B2はレバー、B6はかつおやバナナ、モロヘイヤなどに多く含まれます。B12は魚介類やレバーに豊富です。葉酸もビタミンBの一種で、欠乏しないように気をつけたい成分です。葉酸はビタミンM、ビタミンB9、プテロイルグルタミン酸とも呼ばれています。ほうれん草に多く含まれている成分です。
ビタミンK・βカロチン
ほうれん草やケールに含まれていて、抗酸化作用や脳機能の維持に役立つ可能性があると言われています。
アントシアニン・ポリフェノール
ブルーベリーをはじめ、ベリー類に豊富に含まれるアントシアニンやポリフェノールは、記憶力や情報処理能力に効果を発揮すると言われています。
POINT!!
それぞれの栄養素が含まれている食べ物をまとめるよ
| 栄養素 | 代表的な食べ物 |
|---|---|
| オメガ3脂肪酸 | サケ、イワシ、マグロ、サバ、アマニ油、エゴマ油、くるみ |
| 複合性炭水化物 | 穀物、芋類、豆類 |
| レシチン | 卵黄、大豆、アーモンド、うなぎ、レバー |
| 鉄分 | うなぎ、レバー |
| ビタミンB群 | 豚肉、レバー、かつお、バナナ、モロヘイヤ、魚介類、レバー、ほうれん草 |
| ビタミンK、βカロチン | ほうれん草、ケール |
| アントシアニン、ポリフェノール | ベリー類 |
受験生におすすめのメニューって?

受験生におすすめのメニューを見ていきましょう。
朝食メニュー
朝食に相応しいメニューを紹介します。
豆乳オートミール
オートミールは複合炭水化物がとれます。豆乳からは記憶や学習に効果があると言われる大豆レシチンと植物性タンパク質です。
ブルーベリーとバナナのヨーグルト
ブルーベリーにはアントシアニンなどのポリフェノールが豊富です。また、バナナは脳のエネルギー源となるブドウ糖、安定した血糖維持に役立つ食物繊維、ストレスを和らげるトリプトファン、ビタミンB6などがたっぷりと含まれています。ヨーグルトは良質なタンパク質とカルシウムがたっぷりですし、腸内環境を整える効果も高いです。
目玉焼き
卵は「準完全栄養食品」と呼ばれています。これはビタミンCと食物繊維以外の栄養素をバランスよくとれるためです。卵黄にはレシチンも含まれています。
昼食メニュー
昼食(お弁当)に相応しいメニューを紹介します。
梅干しおにぎり
梅干しはクエン酸が含まれていて疲労回復に効果的です。
かぼちゃの胡麻和え
かぼちゃはβカロテンがたっぷり含まれていて、抗酸化作用があります。脳の疲労や身体の疲労にも効果的です。ビタミンCも豊富で、疲労回復や免疫力アップに効果を発揮します。またかぼちゃと胡麻にはビタミンEが含まれていて、強い抗酸化作用があります。胡麻に含まれている鉄分は、全身に酸素を運んでくれる大切な栄養です。酸素が足りないと頭がぼーっとしてしまいます。
レバニラ炒め
レバーには鉄分が豊富に含まれていて、脳や全身への酸素供給を手助けします。ビタミンB群、中でもB12は疲労回復に効果的です。ビタミンAは免疫力をアップしますし、疲れた目にもよいでしょう。ニラに含まれているアリシンはビタミンB1の吸収を助けます。また、もやしには食物繊維やビタミンが含まれていて、体調の維持に役立ちます。
ブロッコリーナムル
ビタミンB群、カルシウムや鉄、食物繊維やビタミンCが含まれています。疲労回復や脳や体への酸素の供給に効果的です。免疫力アップや整腸作用、イライラ予防にもおすすめできます。
間食メニュー
間食はダラダラ食べにならないものを選びましょう。
ドライマンゴー
ドライマンゴーにはビタミンAやCが含まれていて、免疫力アップにおすすめです。夏の勉強は体力を削られます。病気にならないためにも健康によいおやつをササッと食べておきたいところです。
ナッツ
良質な脂質がたくさん摂れます。オメガ3脂肪酸や不飽和脂肪酸が多いです。脳の神経細胞を保護し、情報伝達をスムーズにします。ビタミンEには抗酸化作用がありますし、マグネシウムや亜鉛は神経伝達物質やエネルギー代謝に必要です。食物繊維がとれるところもおすすめポイントといえます。
夕食メニュー
夕食に相応しいメニューを紹介します。
鮭のワンプレートディッシュ
玄米ご飯に焼き鮭とベビーリーフとミニトマトをのせます。玄米ご飯には食物繊維が豊富ですし、ミネラルもたっぷりで神経や脳の働きをサポート。ビタミンB群もエネルギー代謝に必要です。焼き鮭にはDHA・EPAが含まれていて、記憶力や集中力の維持に働きかけます。ビタミンDには免疫アップの効果がありますし、ベビーリーフはビタミンCや葉酸が含まれていて、鉄の吸収を助けます。トマトもリコピンが含まれていて、抗酸化作用から疲労軽減に役立ちます。
豆腐とわかめとネギの味噌汁
豆腐は植物性タンパク質とイソフラボンでホルモンバランスや集中力を安定させます。わかめはヨウ素やカルシウム、食物繊維が豊富で脳や神経の働きをサポートしてくれます。ネギはアリシンの効果で疲労回復、味噌は腸内環境の改善によいです。
睡眠と栄養をとって受験生の夏を乗り切ろう

受験生は夏の暑さに負けない生活を送りましょう。ついつい夜更かししがちですが、就寝時間が遅くなるとそのサイクルで生活することになってしまいます。早寝早起きを目指してください。小学生で必要とされる睡眠時間は9時間から12時間です。また、健康を考えた食生活も欠かせません。ただし、夏期講習中は弁当持参の家庭が多いでしょう。手の込んだおかずにする必要はありません。
その分、可能であれば、朝食や夕食をしっかり食べましょう。朝食を抜いてしまうと体調を崩しやすいので、食べる習慣を定着化させます。勉強に効果的な栄養素を意識すると尚のことよいでしょう。レシチンや鉄分、ビタミンB群をはじめ、日々の食生活で取り入れたい栄養素はたくさんあります。夏バテすることなく合格を目指しましょう。