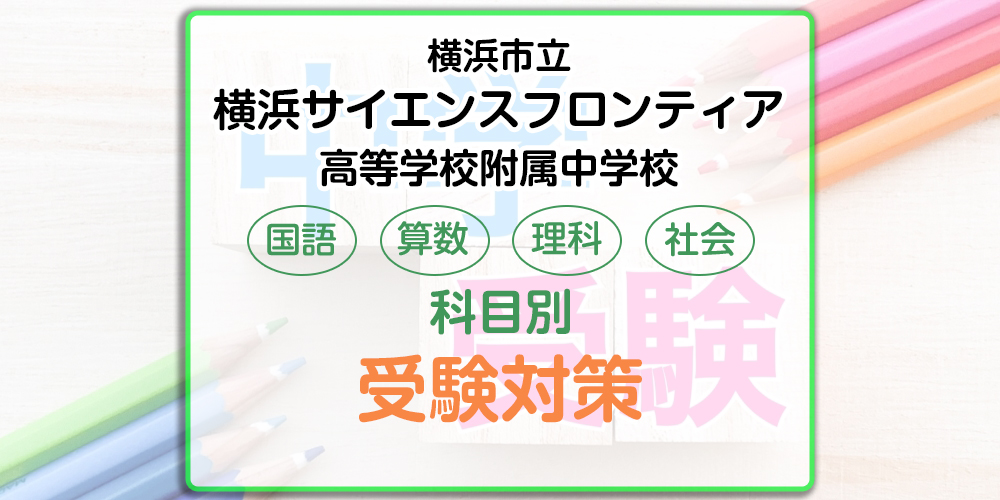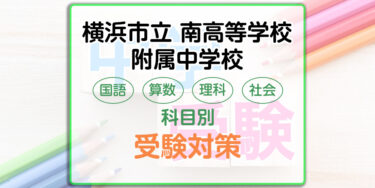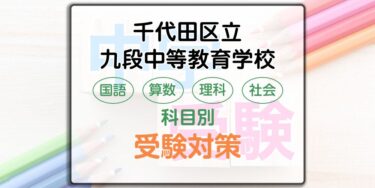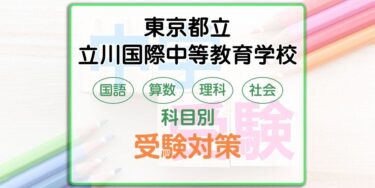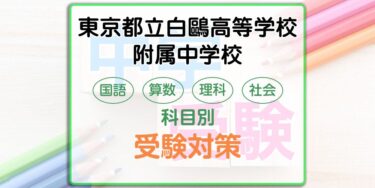横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校は、サイエンスエリートの育成をコンセプトにしている、比較的新しい学校です。この記事では横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校を目指す子供に向けて、出題傾向と勉強法を紹介します。
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校ってどんな学校?

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校は、「サイエンスの考え方」を身に付けた生徒、豊かな社会性や人間性を身に付けた生徒、次代を担うグローバルリーダーの素養を身に付けた生徒の育成を目指す中高一貫校です。
総合的な学習の時間に実施する「サイエンススタディーズ」は、自然科学や社会科学を核とした課題探究型の学習で、「読解力」「情報活用力」「課題設定力」「課題解決力」「発表力」の5つの力の育成を図ります。
中学校を基盤形成期、高校を充実発展期と位置づけ、それぞれの段階を経てサイエンスエリートを育成していくカリキュラムです。国語・数学・理科・英語の授業時間が多めで、教科の特性に応じて授業を少人数で実施。先取りを売りにする学校が多い中で、探究力を育てるような、生徒の興味関心を引き出す授業をしています。
卒業後の進路としては、2025年度の合格実績を一部挙げると、東京大学2名、京都大学5名、一橋大学2名、筑波大学6名、東北大学5名、早稲田大学31名、慶應義塾大学21名です。名だたる大学に卒業生を送り出しています。
なお、定期的に小中学生対象のサイエンス教室を実施しているため、関心のある家庭はぜひ参加してみてください。
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校の入試概要
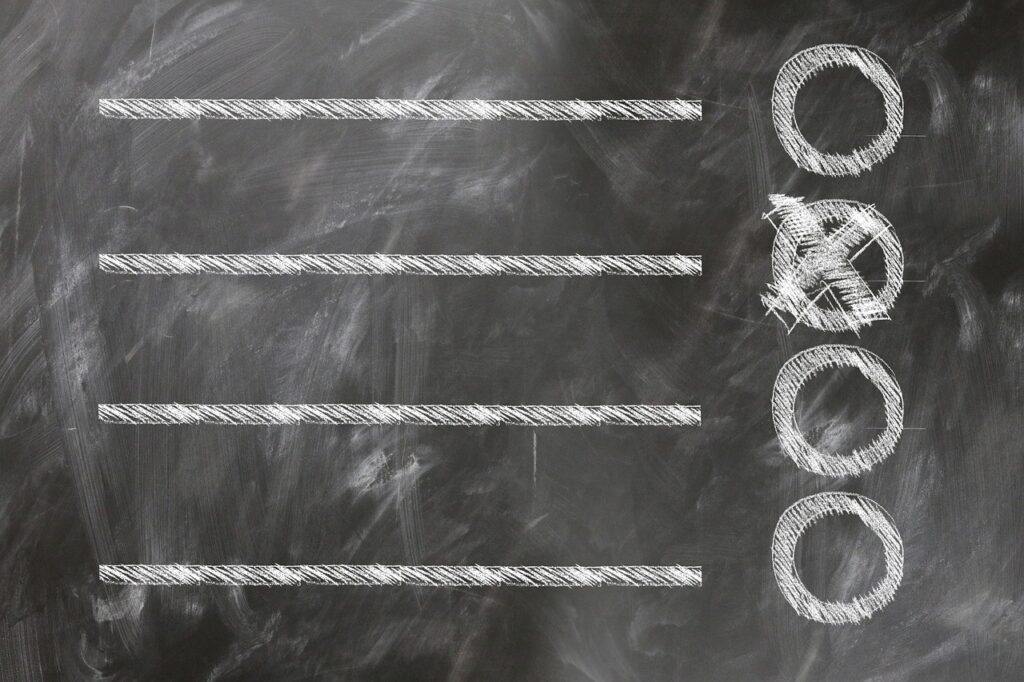
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校の入試について見ていきましょう。
2026年度の入試
2026年度の試験日は2026年2月3日、80名の募集です。出願期間はウェブサイトが2025年12月22日から2026年1月5日まで、出願書類が2026年1月6日から1月8日までに設定されています。
2025年度の入試倍率
受検者数340名、合格者数80名、実質倍率は約4.3倍です。なお、2024年度は受検者数429名、合格者数80名、実質倍率は約5.4倍でした。なお小数点第二位以下は四捨五入しています。
| 入試年度 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 340名 | 80名 | 約4.3倍 |
| 2024年度 | 429名 | 80名 | 約5.4倍 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校における適性検査の出題傾向

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校の適性検査における出題傾向は以下のとおりです。
適性検査Ⅰでは情報を読み取る力と記述力が必須
適性検査Ⅰの制限時間は45分で、配点が100点、大問が二つです。2025年度の適性検査Ⅰは、大問一が多数の資料を参考にしながら会話形式で展開していく問題。大問二は、適切な選択肢を選ぶ問題と字数の多い記述問題が出題されていました。出題形式は例年と同じです。
具体的に内容を紹介すると、人物年表を見て考える問題や、富獄三十六景神奈川沖浪裏を見て答える問題が出題されました。他にもピクトグラム、ピクトグラムが設置された場所の地図、各国のお札など、たくさんの資料のついた問題が出題されました。
つまり、適性検査Ⅰでは、文章や図表、絵、写真、地図など多くの資料から情報を読み取る力、提示された条件に従い記述する力が求められます。
適性検査Ⅱでは思考力が求められる
適性検査Ⅱでは、物理的な仕組みについて書かれた文章と資料から思考するタイプの問題が出題されます。2025年度の大問一では、鉄道の仕組みについて掘り下げました。信号と転てつ機、継電連動装置、リレーという部品について詳しく掘り下げています。こうした知識があらかじめある子供はほぼいないでしょう。
そのため、個々で問われるのは読み取る力と思考する力です。大問二では立体の問題が出題されています。会話文形式で、さまざまな立体の問題が展開していきます。会話文はボリュームこそありますが、内容自体は平易で読みやすいものです。
なお、2024年度も同様の出題形式で、大問一では深海調査について、大問二では平面図形について出題されていました。よって、2026年度も大問一では提示された文章と資料から情報を読み取り思考する力、大問二では図形を考える力が求められる可能性が高いです。ただし2023年度の出題傾向は違うので、今年度もガラリと内容が変わるかもしれません。
- さまざまなテーマを扱うため大半が慣れないテーマになる
- 情報を処理し、設問の意図を汲ませる問題が多い
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校に合格したい。どんな勉強が効果的?

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校に合格するためには、どういう勉強をするべきなのでしょうか。科目別に見ていきましょう。
国語の勉強法
国語にはどう取り組めばよいのでしょうか。
長い文章を読み込む力を
長い文章を読み込む力を身につける必要があります。大問一は会話文形式で展開していくため、基本的には読みやすいです。しかし資料と文章が交互に展開し、その都度頭を切り替えていく必要があります。素早く情報を処理する力が欠かせません。
文章の構成を把握しよう
文章の要点が理解できるように、構成を把握できるようになりましょう。形式段落に番号を振り、意味段落ごとにまとめる練習をおすすめします。意味段落ごとに何が書かれているのかを要約してみるとよいでしょう。文章を相手に伝えるためにどういう工夫がされているかを知ることは、読み取りの上ではもちろん、記述においても役に立ちます。
文章を素早く読む力を身につけよう
文章をスピーディーに読み込む力がないと、時間内に解くのは難しいです。特に、説明文や論説文で読むスピードが落ちてしまう子供は少なくないので、練習が欠かせません。さまざまなテーマを扱った文章に慣れておく必要があります。
まとまった文章を書く作業に慣れておこう
適性検査Ⅰのラストには、ボリュームのある記述問題が例年一、二問出るため、そこで点差がつきやすいです。長い文章を書くのが苦手な子供は多いので、早期からトレーニングに取り組みましょう。
文章の要約もよい練習になります。国語の勉強で出てきた読解文を必ず、要約するようにしましょう。最初からうまく書ける子供はほぼいません。「文体が安定しない」「接続詞の使い方が間違っている」「一文が長過ぎる」「要点をまったく押さえてない」など、なにかしらの瑕疵があります。
要約の練習を通して子供の問題点を把握しましょう。子供がどういう書き方をするのか、どういう読み方をしているのかを分析します。なお、こうした作業は保護者が引き受ける必要はありません。塾講師や家庭教師にお願いしたほうがよいです。記述問題の採点には専門性を要します。添削して、フィードバックを繰り返していくと、少しずつ子供の技術も向上していきます。一気にうまくなることはまずないので、長い時間をとって段階的に改善していきましょう。
要約する際には、必ずタイマーをかけて取り組ませます。10分ぐらいでまとめられるようになるとよいです。テスト本番の記述問題に対応できる力を身につけさせましょう。
- 長い文章の中に資料と文章が交互に展開されるため頭の中で素早く処理し、切り替える訓練をしておく
- 速読の練習をし、文章を読み進める時間を出来る限り短縮できるようにしておく
- 文章の要約を多くこなし、記述問題は必ず塾講師や家庭教師に添削してもらうようにする
算数の勉強法
算数にはどう取り組めばよいのでしょうか。
図形が頻出なので対応できるように
ここ2年は図形が頻出単元なので、対応できるようにしておきましょう。2025年度が立体図形、2024年度が平面図形でした。特に立体図形は立体の切断の問題を多く解いておくことをおすすめします。あらゆる条件下で立体がどんな形に見えるのかを学ぶとよいです。立体内部の立体も出題されています。立体図形は苦手意識の強い子供の多い単元ですが、だからこそ早い段階でたくさんの問題を解いておく必要があります。すぐには理解できなくても、問題数をこなしていくうちにパターンがつかめてくるでしょう。
ただし、2023年まで遡ると出題傾向は異なります。2023年度の大問は三つで、大問一が二次元コードについて、大問二がオセロについて、大問三が地球上で自分の位置を知る技術についてでした。そのため、2026年度どういう問題が出るかは正確には予想しづらいです。大きく方向性を変えてくる可能性もあります。さまざまな可能性を念頭に置き、冷静に問題に向き合っていきましょう。
慣れない問題でも怯まない
思考力を問われる問題が出題されます。専門的な知識を解説しながら展開する問題が多いので、基本的に見慣れない問題ばかりが出題されることとなります。文中にヒントが散りばめられているので確認しながら解きましょう。
たとえば2023年度の問題では、ファインダパターンについて出題されています。ファインダパターンに関する文章を読み、比の問題を解くという内容です。ファインダパターンについて、あらかじめ知識を持っている子供はほとんどいないでしょう。難しく感じるのは受検者全員同じといえます。まずは、「自分だけではない」と認識して焦らない姿勢が大切です。
- 頻出の図形問題に苦手意識を持たないよう、早い段階から多くの問題をこなしておく
- 問題文の中からヒントを見つけられるように、見慣れない問題に多く挑戦しておく
理科の勉強法
理科にはどう取り組めばよいのでしょうか。
専門的な分野を掘り下げていく出題
理科は専門的な分野を掘り下げていく出題です。これまで触れたことのないテーマから出題されるため、とっつきにくさを感じることは間違いありません。慣れない名称がたくさん出てきて、読みづらさを感じることもあるでしょう。基本的には物理分野に近い出題が多いです。
図表を読めるようにしておこう
図表を使った問題も多いです。数字が羅列されていて、情報を読み取るタイプの問題です。読めるように練習しておくとよいです。2025年度はリレーの可動接点についての表、2024年度は海水温と水深の関係や、塩分濃度と水深の関係、音の速さと水深の関係のグラフ、沈む重さについての表などが出題されました。慣れているテーマの表やグラフはまず出ませんが、見方自体を理解していれば大丈夫です。落ち着いて解きましょう。
- 図表の見方を理解するために色んな種類の問題に取り組んでおく
社会の勉強法
社会にはどう取り組めばよいのでしょうか。
歴史の基本を押さえておこう
適性検査Ⅰで歴史の問題が出題されています。解けるように、基本的な知識の抜けがないか、定期的に確認しておくようにしましょう。保護者に聞き手になってもらい、時代ごとに掘り下げた解説ができるようになるとよいです。文化史も細かな内容まで押さえておきましょう。
地図を読めるようにしよう
資料として地図が出題されるケースがよくあります。地図を見て各場所の基本的な名称を書けるようにしておきましょう。たとえば、2025年度は会話文と地図から、海洋名を答える問題が出題されています。世界地図からの出題でした。地理の対策は日本に偏ってしまうケースが多いので、基本的な知識は満遍なく頭に入れておきましょう。
会話文の示す内容をよく読み込もう
会話文形式でテーマが移り変わっていきます。次々と知らないテーマが提示されますが、資料から正しく情報を読み取ることができれば、解くことができます。ひとつひとつ着実に解くようにしましょう。
- 保護者相手に歴史の解説をすることを習慣づける
- 地理は日本地図だけでなく世界地図も基本的な知識を入れておく
慣れないテーマでも諦めず読み込む力を身につけよう
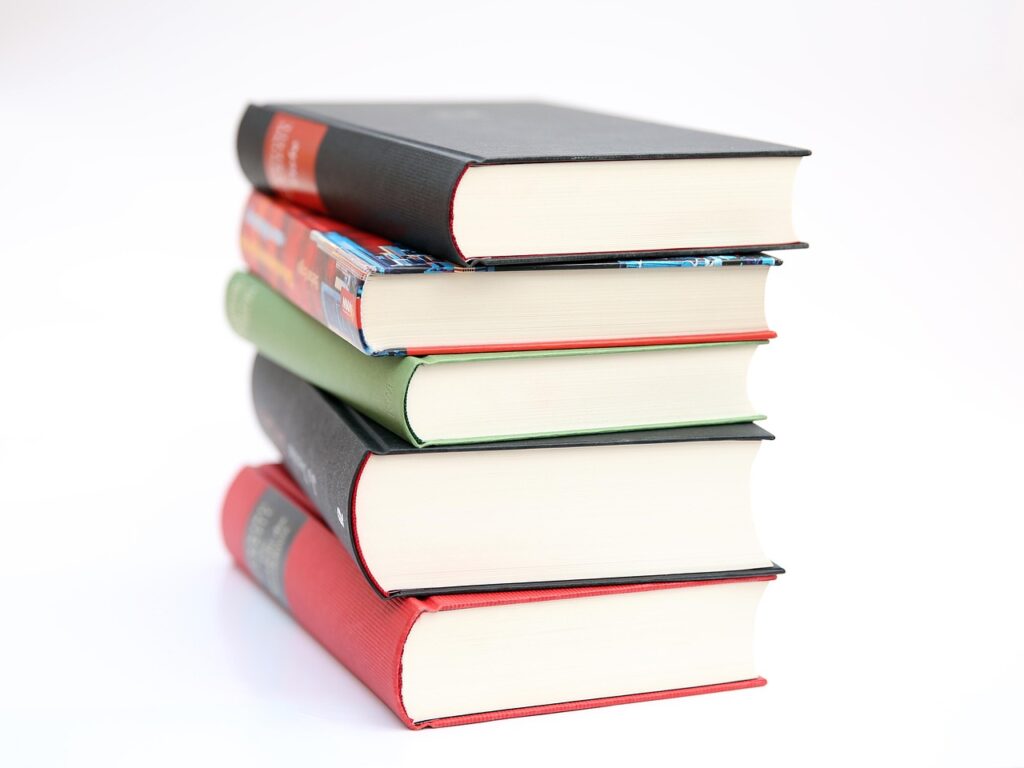
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校の適性検査では、さまざまなテーマを扱います。小学校で学んだ知識を生かせば解ける問題ばかりですが、慣れないテーマが大半なので、身構えてしまう子供が多いです。読解力はもちろんですが、「難しそうな問題だけど、慌てずに読んでみよう」と思えるかどうかが合否を左右します。試験本番までに自信をつけておくことが大切です。そのためにも過去問や類題をやり込んで、「解けた!」という経験を積み重ねておきましょう。
適性検査Ⅰでは、記述力が大きく求められます。字数が多めなので、過不足なく書けるように練習しておかなければなりません。適性検査Ⅱでは専門的な知識を掘り下げていく問題が出題されます。一見して難しそうに見えますが、求められている知識自体は一般的なものです。
ただ、文章をしっかりと読み込み、情報を処理し、設問の意図を汲んで答える力が必要です。テーマ自体は年度によって大きく変わるので対策のしようがありません。テーマごとの対策は難しいので、腰を据えて読み込む力を身につけておく必要があります。
記述にせよ読解にせよ、ボリュームがあるため、スピーディーにこなしていかなければなりません。テスト本番と同様の時間制限を設けて、挑むようにしてください。