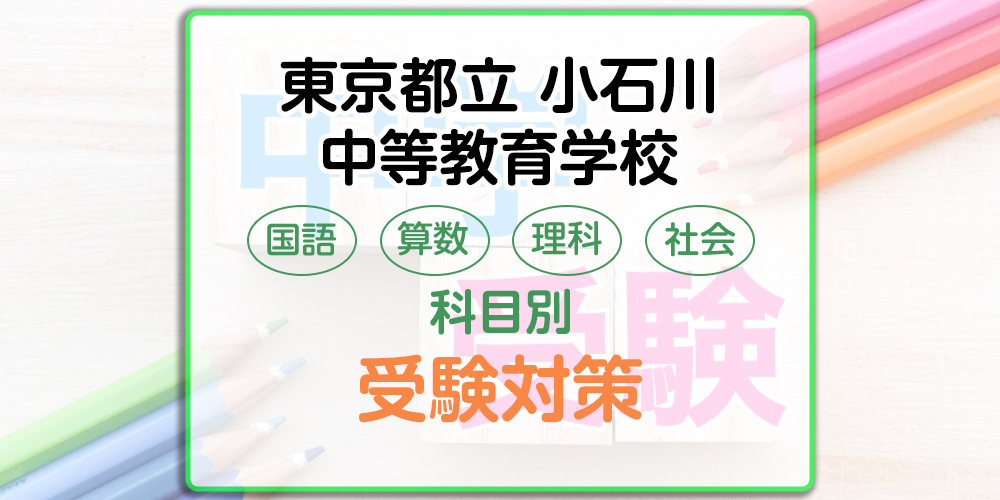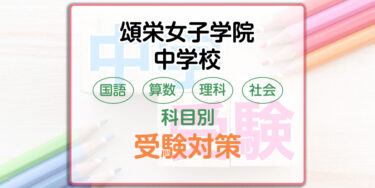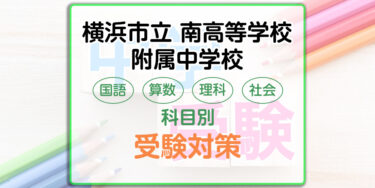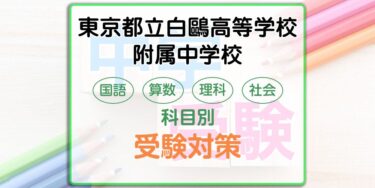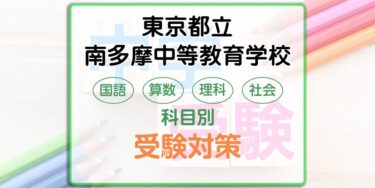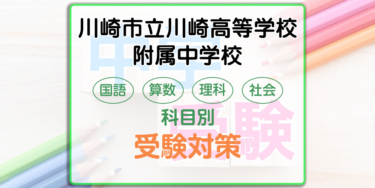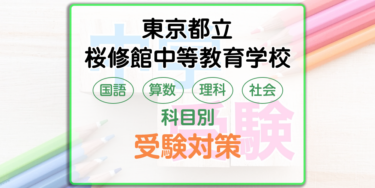東京都立小石川中等教育学校は伝統ある都立の中高一貫校です。理数教育や国際理解教育に注力していることで知られています。この記事では、小石川中等教育学校の出題傾向や勉強法を紹介します。
そもそも東京都立小石川中等教育学校ってどんな学校?
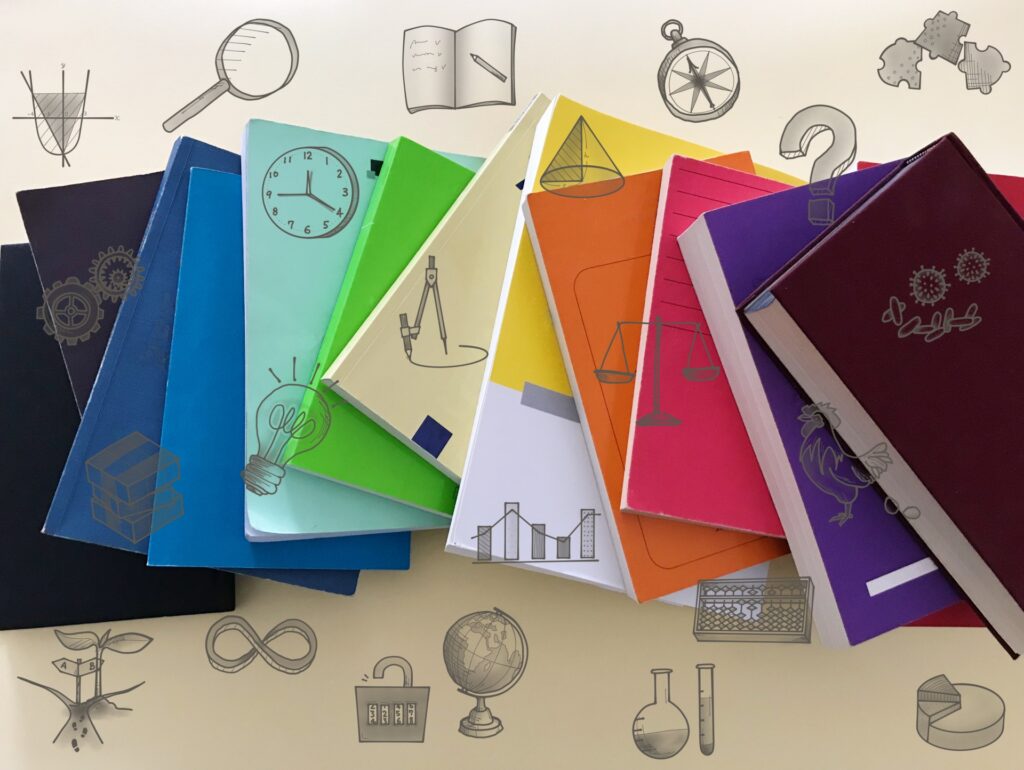
東京都立小石川中等教育学校は、1918年に府立五中として創設した小石川高等学校の伝統を引き継いでいます。中高一貫校として開校したのは2006年です。「理数教育」に注力していて、文部科学省から「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)」の指定を受けています。「国際理解教育」にも熱心で、3年生で「海外語学研修(オーストラリア・アデレード)」、5年生で「海外修学旅行(シンガポール)」を実施。それ以外にも、「海外派遣研修(イギリス)」の機会を設けています。
行事も充実していて、生徒自治の象徴として「行事週間」があります。これは芸能祭、体育祭、創作展、後夜祭の4つの行事を十日の間に行うというものです。部活に加入する生徒も多く、兼部するケースが少なからずあるため、加入率は150%を誇っています。
高い進学実績も注目を集めていて、2025年度は東京大学に現役で16名が合格しています。京都大学には現役5名、浪人1名で、筑波大学には現役8名合格です。私立では慶應に現役24名、浪人5名、早稲田には現役50名、浪人13名合格となっています。
小学生向けの体験事業をたくさん行っているため、興味のある家庭はぜひ申し込んでみることをおすすめします。理数系から語学までさまざまなテーマのイベントが実施されている学校です。
東京都立小石川中等教育学校の入試概要
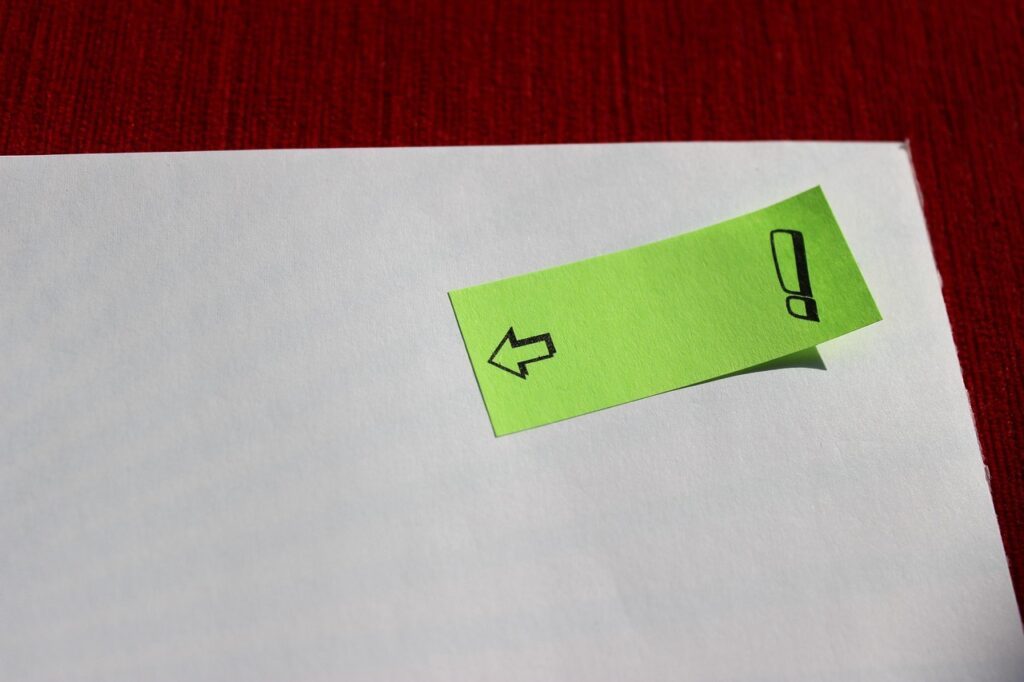
東京都立小石川中等教育学校の入試について見ていきましょう。
2026年度の入試
入試は2月1日実施の特別枠募集と2月3日実施の一般枠募集の二種類があります。出願期間はどちらも同じで、インターネット出願の場合は、2025年12月18日(木)から2026年1月16日(金)午後5時まで。書類出願の場合は、2026年1月9日(金)から1月16日(金)までで、インターネット出願より期間は短めです。
特別枠募集の条件は、家庭環境や被災などの事情で一定の条件を満たしているか、もしくは、自然科学分野の全国的なコンクール等に入賞し、入学後もその能力の伸長に努めることができるかが問われます。
なお、条件が合致するのであれば、特別枠募集と一般枠募集の両方に応募することも可能ですが、特別枠募集で合格したのであれば、一般枠募集は受けられません。
2025年度の倍率
2025年度の一般枠募集は受検者数501人で合格者数160人、倍率は約3.1倍でした。特別枠募集は、受検者数3人、合格者数0人です。なお、実質倍率は小数点第二位以下を四捨五入しています。
| 入試区分 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 一般枠 | 501名 | 160名 | 約3.1倍 |
| 特別枠 | 3名 | 0名 | – |
東京都立小石川中等教育学校における適性検査の出題傾向

東京都立小石川中等教育学校の入試における出題傾向は以下のとおりです。
適性検査Ⅰは文章を読み取り表現する力
適性検査Ⅰは大問がひとつで、制限時間は45分です。2025年度は、説明文と物語文が二つ掲載されていて、その二つを受けた会話文を経て、問題を解く構成になっていました。文章自体は難解なものではなく、平易な文体で書かれた読みやすいものが出題されています。
2025年度の内容は、小学生がカブトムシの新たな生態を論文として学会に発表した話と、恩田陸の『spring』です。さらに、最後にこの二つを読んだふたりの人物の会話文が載っています。出題された問題は、文章の内容を読んで適切な言葉を抜き出して穴埋めしたり、文章を完成させたりするというもの。それから、指定字数で400字以上440字以内の記述でした。この記述は自分の考えをまとめるものです。また、書くにあたっていくつかの決まりが設定されています。
つまり、文章を読み取る力と、条件に従った上で自分の考えをまとめる力が求められます。科目でいえば国語の試験です。
適性検査Ⅱは多角的な力を問う問題
適性検査Ⅱの大問は三つ、制限時間は45分です。算数と社会と理科が混ざったような試験で、求められるのは提示された資料や文章から正しく情報を読み取り考える力です。2025年度の場合、大問一は展開図やブロックの問題、大問二はごみの収集と処理についての会話文と資料を見ながら答える問題。大問三はシャボン玉の実験の問題で、実験結果を見て記述問題などを解く内容でした。
理科がどの分野から出題されるかは年度によって異なります。計算、作図、記述、表の完成など、問題の内容はさまざまです。記述問題の数は多く、自分の考えを求められる問題もあれば、説明記述もあります。資料から必要な情報を読み取る力、思考力、判断力、考察力、処理能力、表現力など多角的な力が問われる内容です。
適性検査Ⅲは思考力が問われる出題
適性検査Ⅲの大問は二つで制限時間は45分です。身近な題材をテーマに据えて、分析力・思考力・判断力・問題解決力などを問う内容となっています。知識をもとに考えさせる問題であり、全体的に応用問題だといえます。
2025年度は光や虫やワイパーなどの問題が出題されています。科目で言えば、理科と算数からの出題です。記述問題が多く作図問題もあります。思考した内容を伝わるように文章に落とし込む力が必要です。
- 読解力、思考力、表現力とさまざまな力が必要になる問題が出題される
- 思考力重視の問題では問題自体にヒントが多く含まれている
東京都立小石川中等教育学校に合格したい。どんな勉強が効果的?
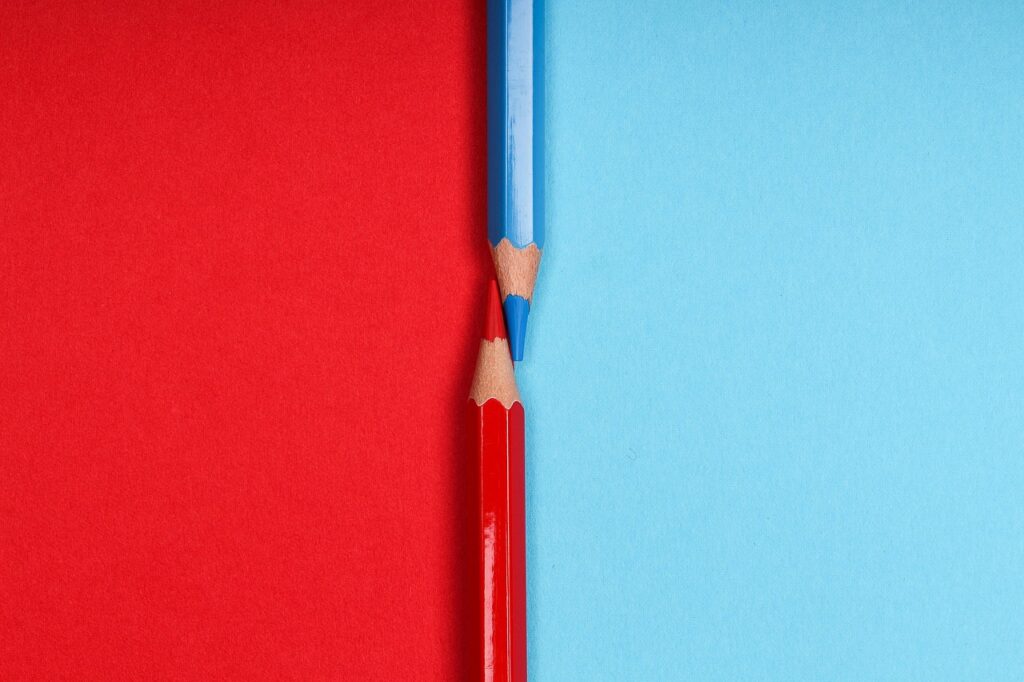
東京都立小石川中等教育学校に合格するためには、どういう勉強をするべきなのでしょうか。科目別に見ていきましょう。
国語の勉強法
国語にはどう取り組めばよいのでしょうか。
文章を要約してみよう
国語は文意を読み取る力が必要となります。穴埋めにしろ、記述にしろ、要点を押さえていないと、答えられない問題が出ます。そのため、読解文の要約をするのがおすすめです。要点を洗い出せるようになりますし、短い分量でまとめる力もつきます。
文章が多いので先回りという選択肢も
2025年度の問題では、適性検査Ⅰが実質的に国語の試験に該当し、説明文、物語文、会話文を経てから設問に移る形式でした。こういう構成では、設問に辿り着いたころには、最初に読んだ内容を忘れてしまう子供も出てくるものです。
過去問を解いてみて、子供にそのような傾向があった場合は、設問を先にチェックさせることをおすすめします。なにを聞かれるのか、あらかじめ把握した上で臨めば時間短縮にもなります。
自分の意見を書けるようにしよう
一般的な説明記述だけではなく、自分の意見を書けといった作文的な出題が目立ちます。意見を書くのが苦手な子供は、早いうちから練習しておきましょう。意見を書くといっても、文意を理解した上での意見でなければなりません。好きに書くのではなく、要点を押さえた上での意見を展開する必要があります。
- 要点を押さえて短い分量にまとめる力を養うために文章を要約する練習を多くこなす
- 過去問で出題形式と長い問題文に慣れる
算数の勉強法
算数にはどう取り組めばよいのでしょうか。
基礎知識を定着化させよう
数量や図形についての基礎知識を身につけていないと、解けない問題が出ます。特に図形は苦手意識の強い子供が多いので、早いうちから取り組んでおいてください。
計算問題は時間内で確実に
計算を使って解く問題でミスをすると、続く問題でもミスをしかねないので、スピーディーかつ正確に解けるよう繰り返し解き実力をつけましょう。なお、計算問題ではなく記述問題が出題される年度もあるので、どちらが出た場合にも対応できるようにしておきたいところです。
資料を読み取る力をつけよう
長い問題文に加え、図表が多く提示される問題が頻出です。与えられた情報を隅々までチェックし、論理的に考察する力が欠かせません。とりわけ立体図形は苦手な子供にとって最も苦労する単元です。数を多く解いてあらゆるパターンに対応できるようにしておきましょう。
作図の問題に慣れておこう
解答欄に書かれている図に線を引くといった問題が多く出ます。頭の中で図形を展開できる力をつけなければなりません。
- 基礎知識の定着は早い段階から取り組むようにする
- 計算問題でのミスは後の問題にも響くため、スピーディーかつ正確に解けるように数をこなす
- 図形問題を多くこなしながら論理的思考力を養う
理科の勉強法
理科にはどのように取り組んだらよいのでしょうか。
対照実験の問題が定番
東京都立小石川中等教育学校では、対照実験の問題が定番で出題されます。知識をもとに考える問題もあれば、思考力を問う問題もあり、難易度には多少ばらつきがあります。
実験の問題に慣れておきましょう。たとえば、2025年度はUVレジンの問題で、紫外線を当てると固まる性質を使った問題が出題されました。UVレジンや紫外線についての詳しい知識は、直接的に教科書から得られるものではありません。しかし、これまで学んできた物質の性質を思い出せば解ける問題ではあります。難しく感じた受検生も多かったはずですが、教わっていない内容でも、思考を深めて工夫して解けるようにしましょう。
すべての分野を解けるように
理科関連は物理・化学・地学・生物のうち、どの分野から出題されるかわかりません。不得意な単元を後回しにしたまま疎かになることがないようにしてください。計算問題が出題される可能性も高いので、スピーディーに処理できるようにしておきましょう。計算問題でタイムロスする傾向がある場合は、問題数をなるべく多めにこなしておきます。解き慣れておくことが大切です。
理科の記述に慣れておこう
理科の記述問題はボリュームが大きく、書き方に苦労することが多いです。また、国語とは異なるタイプの記述で、書き方がわからず苦労する子供もたくさんいます。過去問や対策問題集を解くことで、理科の記述に慣れておきましょう。読み手に伝えるためにはどういう情報を落とし込んだらよいのかを考えられるようにします。
学校で学んだことと日常を結び付けよう
私たちは、日常でさまざまな事象を目にします。思考力を問う問題では、日常での事象と学校で学んだことを結び付けて考えるような問題がよく出るものです。「どうしてそうなるのか」という問いの眼差しを忘れず、観察眼を養いましょう。人と事象について語り合うことが大切なので、気づいたことがあれば、進んで子供に話題を振ってあげるとよいです。
- 対照実験の知識を定着させておく
- 思考力を養うために疑問を抱く癖づけと観察眼を養っておく
- 過去問を通して理科の記述方法に慣れておく
社会の勉強法
社会にはどのように取り組んだらよいのでしょうか。
身近な事象に目を向けてみよう
2025年度はゴミをめぐる問題が出ています。日常の中のさまざまな問題を考える習慣をつけてください。受検勉強だけではなく、日頃から諸々の事象に関心を持ちましょう。理科と同様、社会の分野でも日常的な事象や社会問題が出題されます。
暗記よりも思考力
私立中学校対策では、社会は覚える内容が多く、暗記事項を頭に入れようとするだけで、パンクしてしまうケースは珍しくありません。しかし、都立の検査は異なります。頭に知識を詰め込むのではなく、提示された資料をもとに思考力を深める問題が多いです。文章の中に課題を見つけ、その解決法を考えて記述するといった問題もよく出ます。
資料からの読み取りに慣れよう
理科と同様に社会の記述問題も、国語とは違った難しさがあるため、苦労することでしょう。資料から読み取った内容を言葉に置き換えて書く問題が多いです。資料を扱う問題を一問でも多く解いて慣れておいてください。
- 理科と同様に日常のさまざまな問題について考える習慣をつける
- 資料の内容をただ暗記するのではなく、文章中の課題と解決方法を考える練習をしておく
過去問や問題集で対策。苦手をひとつずつ潰そう

適性検査は読解力、思考力、表現力とさまざまな力が求められます。まずは自分の苦手箇所がどこにあるのかを把握するために、過去問を解くようにしましょう。
試験時間と同じ時間設定で挑戦するのがよいです。必ずタイマーをかけてください。記述問題が多くを占めるため、どのぐらいの速度で解けば、時間内に終えられるのかを把握しておくことが大切です。
適性検査ⅠからⅢはそれぞれに特徴があり、得意不得意が反映されやすいです。おそらく、「一番苦労するのは適性検査Ⅲだ」という人も少なくないのではないでしょうか。思考力重視の問題が出題されると、多くの人は焦ってしまいます。問題自体にヒントが多く含まれているはずなので、解くために必要な知識を記憶から取り出しましょう。加えて、点と点をつなげて発想する力が大切です。落ち着いて問題と向き合うことをおすすめします。
なお、記述問題は自己採点ではなく、塾講師、家庭教師などのプロに採点してもらってください。そうしないと減点や失点の要因に気づかないことがあります。