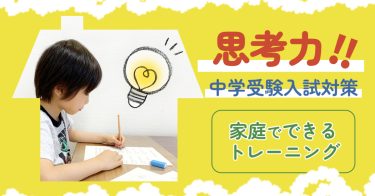中学受験は一般入試以外にもさまざまな形式があります。最近よく聞くようになった入試のひとつとして挙げられるのが思考力入試です。この記事では思考力入試を検討している家庭に向けて、家でもできるトレーニングや基本情報を紹介します。
そもそも思考力入試とは
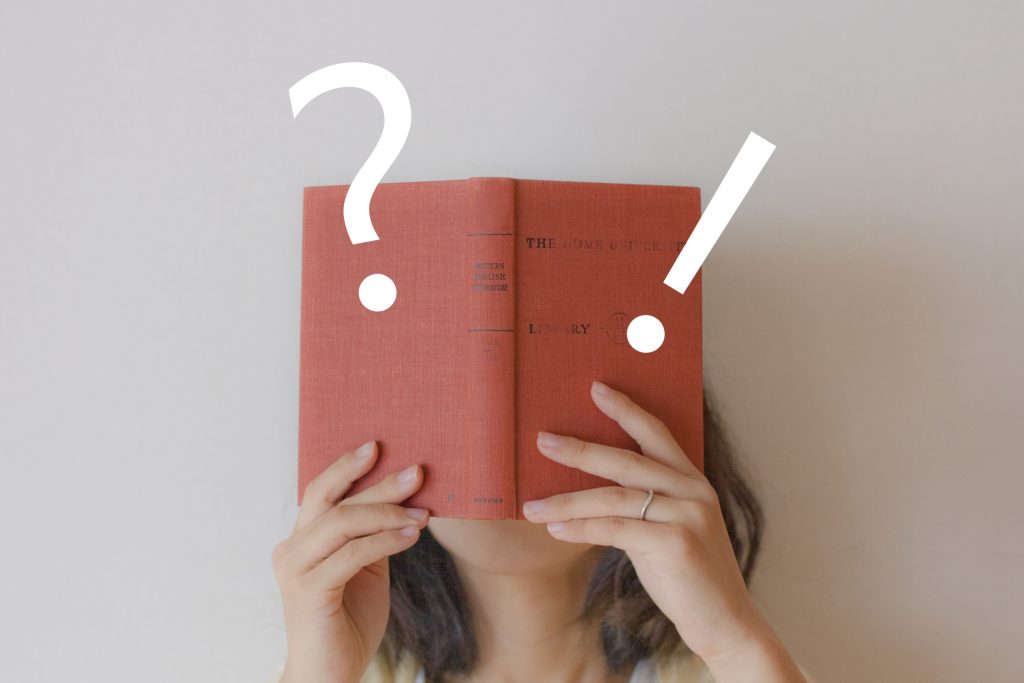
思考力入試とは、その名のとおり思考力を問う入学試験のことです。学力とは別の軸から生徒を評価しようとする試みで、学校によってさまざまな問題が用意されています。たとえば、聖学院中学校では三種類の思考力入試を実施。2026年度の入試は、「ものづくり思考力」「デザイン思考力」「グローバル思考力」の三つです。
「ものづくり思考力」はブロックを使った試験で、情報を読み取る力、物事への探究心、表現力や伝える能力を計るものとなっています。「デザイン思考力」はデザインに必要な考え方と手法を利用して問題を解決する「デザイン思考」を取り入れていて、与えられた条件下で思考をめぐらせて新しい何かを創り出せるかどうかが問われます。「グローバル思考力」は、課題解決と価値創造に加え、グローバルな視点を持っているかどうかを見る入試です。
これはあくまで一例で、ひと口に思考力入試といっても、学校によって課される内容は大きく異なります。つまり、学校側が求める生徒像に合わせて、入試の内容にもバリエーションがあるということです。
また、思考力に特化した入試を実施している学校がある一方、一般入試に思考力入試を組み込んでいる学校も多くあります。むしろ、数でいえばそちらのほうが主流です。そのため、思考力入試対策をすることは、一般入試においても非常に有益といえるのです。
家庭で思考力入試の対策をするなら?

家庭で思考力入試対策をするとしたら、どのような方法があるのでしょうか。
まずは各校の過去問をやり込もう
思考力入試はバリエーションが多様なので、自分が受けたい学校の過去問をやり込んで、出題傾向を把握してから対策に臨みましょう。そうしないと、見当違いの対策でタイムロスしてしまいかねません。学校のホームページに過去問を載せているケースも多いので検索してみてください。過去問を入手したら、テストと同じ制限時間内に解けるかを試しましょう。
社会問題について話し合う時間を持つ
思考力入試では社会への問題意識を問われるケースも多いです。2025年度に実践女子学園中学校の思考表現入試で出題されたのは、世界をよりよいものにしていくためには、解決しなければならない課題が世の中にたくさんあることを前提にした思考力問題です。筆記試験を終えたあとは、内容についての質疑応答もあり、思考力だけではなく表現力も問われました。
日頃から社会について考えていなければ、解けない問題はたくさんあります。実践女子学園中学校の過去問を遡ってもそれは明らかです。2024年度はジェンダーギャップの問題、2023年度はバーチャルウォーターの問題でした。
社会問題の知識はなるべく、専門家の意見から学んでいきましょう。ネットでも多くの専門家が情報を発信していますが、専門性の乏しい過激でキャッチーな言説のほうが広く拡散される傾向にあります。そうした無責任な言説を真に受けていると、中学受験で求められている答えとは対極にあるものばかりが身についてしまいます。情報を精査する作業が欠かせません。
読書ノートをつける
本を読んだあとに、思ったことや考えたことをノートにまとめるのもおすすめです。自分が読書を通して何をどう考えたかを記録できます。それによって、表現する力を身につけることができるのです。
読む力と書く力は連動しています。しかし、読むことができる子供が必ずしも書くことができるわけではありません。書くためにはうまく書くためのノウハウが必要だからです。身につけるために、書く習慣を定着化するのは効果的といえます。
多くの本を読み、その感想をノートにつけるようにしましょう。
作文の添削サービスを受講する
作文を添削してくれる教育サービスを受講するのもよいでしょう。文章を書く練習をする際に、欠かせないのが添削です。塾や家庭教師が対応してくれるならよいのですが、難しいのであれば、添削サービスを通して書いて表現する技術を磨くことをおすすめします。
ロジカルシンキングを鍛える
ロジカルシンキングの鍛え方はさまざまですが、代表的なものをいくつか紹介します。
ディベートをしてみる
あるテーマに基づいて肯定と反対の二組に分かれて、ディベートをしてみることをおすすめします。その際に、肯定側と反対側のどちらの意見に立つかを決めてください。ディベートでは、必ずしも自分の意見と同じ意見の側に立たなくても大丈夫です。自分の意見とはあえて異なる側の意見を代表してみるのも新たな学びにつながります。
ディベートではまずそれぞれの立場で立論を行います。自分の意見を説得力のある主張にするにはどうすればよいのか、よく考えてみましょう。できるだけ意見を裏付ける証拠となるデータがほしいところです。
双方の立論が終わったら、今度は双方の反論へと移ります。双方のチームが複数人の場合は、相談や作戦の時間を設けるようにしてください。
最後に最終弁論です。最終弁論では相手の論に対して自分の論がどれだけ正当性があるかを主張します。相手がどんなポイントで反論をしてくるかを想定してまとめる作業が欠かせません。
ディベートをすることで、そのテーマについての考えを掘り下げることができますし、自分の意見、あるいは自分とは違う意見を改めて検討することができます。
POINT!!
相手に説得力をもって意見を届けるにはどうすればよいか考えよう
ひとつのテーマに基づきロジックツリーを作成してみよう
テーマに基づき、ロジックツリーを作成するのもよい方法です。ロジックツリーにはさまざまなアプローチがあります。ここで紹介する例以外にもKPIツリーが有名ですが、子供が作成しやすい以下の三つを紹介します。なお、ロジックツリーは向かって左側から右側へと展開していくものです。
要素分解ツリー(Whatツリー)
物事を分解していくことで整理して全体像を把握するツリーです。
たとえば向かって「勉強」と書き、「予習」と「復習」に分けたとします。「予習」は「教科書を読む」「基本問題を解く」などに分けられますし、「復習」は「宿題をやる」「間違えた問題を解き直す」などに分けられます。どんどん分けていくと、「勉強」についてやっていることの全体像が細部まで把握できます。これはロジカルシンキングを鍛えるという意味で効果的ですし、受験勉強の全体像を見直す一助にもなります。
原因追求ツリー(Whyツリー)
物事の原因を突き止めるためのツリーです。たとえば「成績が上がらない」という問題点を挙げたら、その原因を追求していきます。原因として、「授業に集中できない」「宿題に時間がかかる」「以前学んだ内容を忘れてしまった」などを挙げたとします。ひとつめの「授業に集中できない」原因として「寝不足」「予習不足」を、二つめの「宿題に時間がかかる」原因として「とっかかりが遅い」「集中できる環境がない」を、三つめの「以前学んだ内容を忘れてしまった」原因として「復習不足」を挙げていきます。そうすると、「成績が上がらない」原因がさまざまな角度から浮かび上がってきます。
問題解決ツリー(Howツリー)
ある問題についてどういった解決法があるかを考えていくツリーです。たとえば「睡眠不足」という問題があったとします。それに対し、「22時には布団に入る」「睡眠環境を整える」といった問題解決法を挙げます。
続けて、「22時には布団に入る」ためになにをすればよいのか、「睡眠環境を整える」にはどういう取り組みが必要なのかなどをさらに書き出していきます。「22時に布団に入る」ために、「寝る時間から逆算して予定を決める」「食事をダラダラ食べない」などを挙げるのもよいでしょう。「睡眠環境を整える」ために「寝具の見直しをする」ことや、「カーテンを遮光に変える」ことも効果的かもしれません。
POINT!!
ツリーにまとめることで課題を解決するためのさまざまなアプローチが見えてくるよ
ピラミッドストラクチャーを作成してみよう
一見ロジックツリーと似ているのですが、ピラミッドストラクチャーという方法もあります。ロジックツリーが向かって左から右へと展開していくのに対し、ピラミッドストラクチャーは一番上に結論を据え下へと根拠を展開していきます。
たとえば、「日本では環境問題についてもっと考える機会を設けるべきだ」という結論を一番上に書き、その根拠をいくつか下に展開していきます。「日本人の気候変動意識は2025年の調査で32か国中最下位」「2024年度の調査で七割以上の親が『猛暑は異常』ととらえている」「熱中症での搬送人数も右肩上がりで2024年は最も多かった」といった思いつく根拠を複数並べていきます。
さらにそれぞれの下に「2021年から2025年にかけて個人の行動変容の必要性への認識が19%も低下」「九割以上の親が猛暑の原因を地球温暖化に求めている」「熱中症対策への呼びかけは増えているのに、搬送人数は増加の一途」などと書き加えましょう。地球温暖化を体感し、日々猛暑を「異常」と感じながらも、気候変動への意識が低い現状の矛盾が見えてきます。
思考力入試やそれに類する新入試を採用している学校とは

聖学院中学校と実践女子学園中学校についてはすでに紹介しました。それ以外で、思考力入試やそれに類する新入試を採用している学校を一部紹介します。
かえつ有明中学校
2026年度は、思考力特待入試・アクティブラーニング思考力特待入試を実施予定です。思考力特待入試の試験科目は個人探究、アクティブラーニング思考力特待入試の試験科目はグループワークが予定されています。
東京家政学院中学校
フードデザイン入試を実施しています。小学五、六年生の家庭科の教科書に載っている基礎知識に基づいた模擬授業を進め、受験生とやりとりするアクティブラーニング型の試験です。学びながらワークシートに記入し、グループワークを実施します。発表も行い、ルーブリック評価で採点されます。
清泉女学院中学校
アカデミックポテンシャル入試を実施しています。思考力・表現力・総合力をはかる試験です。
湘南学園中学校
ESD入試を実施しています。受験者が自身の語る様子を撮影した動画を提出し、記述・論述およびグループワークの試験を受けます。
実践学園中学校
コミュニケーションデザイン入試が行われます。思考力文章表現で100点、コミュニケーションデザインで100点という配点です。
桐蔭学園中等教育学校
桐蔭学園中等教育学校では、探求型(みらとび)入試が実施されています。試験科目は総合思考力問題です。思考力・判断力・表現力等を評価するテストで、資料を分析するところから始まります。その後に、関連する問題を解いていくという流れです。
CHECK!!
思考力入試の内容は学校によって大きく異なるよ
家庭で対策して思考力入試で結果を出そう

家庭でも思考力入試対策に取り組むことは可能です。受験校の出題傾向を把握して取り組んでみましょう。文章を書くタイプの入試の場合、記述力は欠かせません。文章を書き慣れるための方法のひとつとして読書ノートがおすすめです。読む力と書く力はたしかに連動していますが、読めば読むほど書く力がアップするかというと、そうならない子供もいます。書く機会を増やし、書くノウハウを身につけることが大切です。作文の添削サービスを受講してレベルアップを図るのもよいでしょう。
社会問題について学び、話し合う時間を持つことも有意義だといえます。日頃から社会問題にアンテナを張っておきましょう。社会問題をテーマにディベートをして、説得力を持った意見を表明する力を養うのもよいです。論理性という点ではロジックツリーやピラミッドストラクチャーを作成するのもよいでしょう。
ひと口に思考力入試といっても、学校によって大きく出題傾向が異なるので、一番効果的だと思える方法に挑戦してください。情報のひとつひとつにアンテナを張り、自分の頭で考える訓練を日常的に行うようにしましょう。