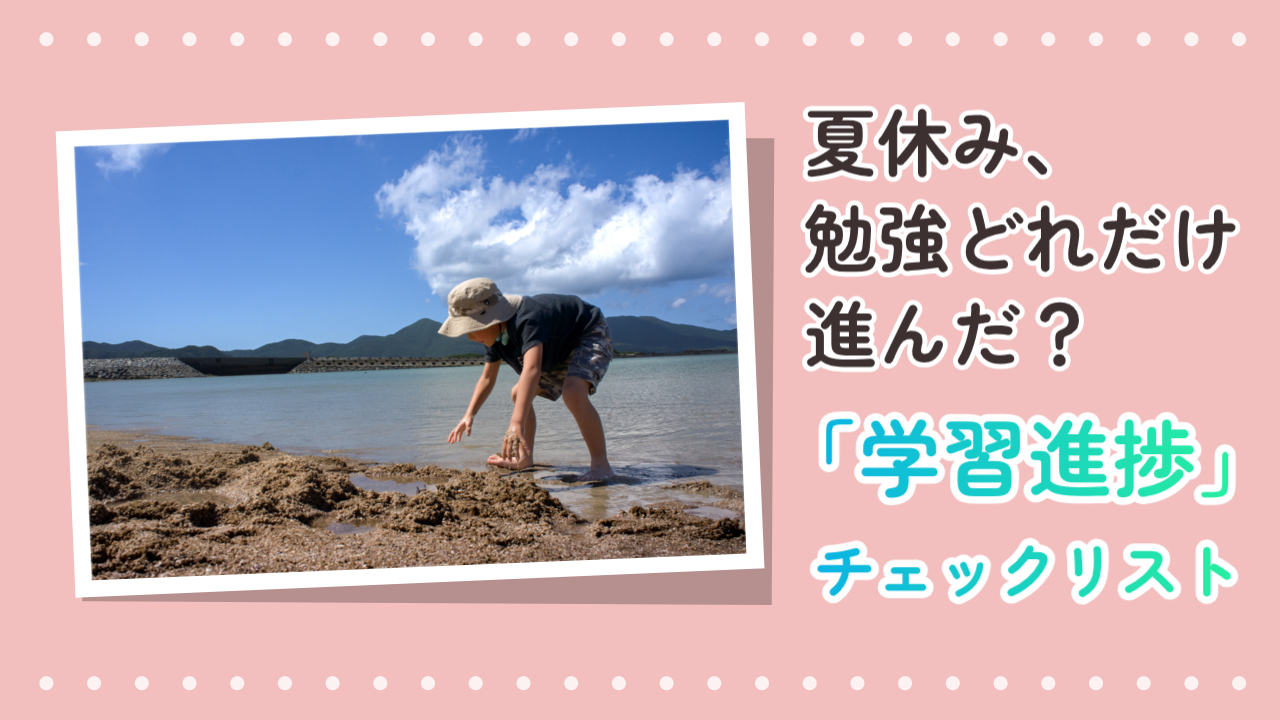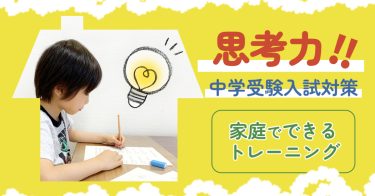夏休みは、苦手単元の復習を進めるチャンスです。夏休みの間に、計画的に学習を進められるかどうかが合否を大きく左右します。この記事では夏休みの計画の立て方や、学習進捗チェックの仕方についてリストとともに紹介します。
夏休みの計画はいつどんな風に立てるべき?

理想としては、夏休みが始まる直前までに計画を立てておきたいものです。それが難しければ夏休みに入ってすぐ、塾や家庭教師の先生と相談しながら、学習計画を作成するようにしましょう。ひとりで作ると実現不可能な計画になってしまったり、ポイントを外した内容になってしまったりする可能性があります。
学習計画の中心に据えるのは、塾や家庭教師による夏期講習や夏期特別授業です。たとえば四谷大塚の六年生を一例に挙げると、夏期講習は400分×16日間、8月特訓授業は400分×8日間です。どちらも一日400分、つまり6時間40分ですから、かなりの時間を占めます。さらに宿題や復習をする時間も必要です。そうなってくると、夏期講習や夏期特別授業以外の勉強を頑張る時間は非常に限られてきます。その限られた時間の中で、優先順位をつけて苦手単元を克服していかなければなりません。
苦手単元の洗い出しPOINT!!
自覚のある単元だけではなく模試やテスト結果の分析が欠かせないよ。漠然とイメージだけで計画を立てることを避けるためにも、プロのチェックを活用しよう!
学習しながら計画表の見直しもしよう

計画どおり学習を進めていこうとしても、なかなかうまくいくものではありません。どのように軌道修正するべきなのでしょうか。
計画表とのズレを修正する日を設けよう
計画表と比べて、できていない部分を洗い出します。できれば週に一回、計画表とのズレを確認する日を設けてください。計画表とのズレが大きくなればなるほど、学習に差し障りが出てきます。そうならないよう適宜、修正していきましょう。
計画表とズレが生じた場合、「進み過ぎてしまった」というのは稀で、多くの場合は「遅れてしまった」状態です。そのため、遅れた分を取り戻す日をあらかじめ設けておく必要があります。
計画は随時バージョンアップ
学習を進めていくことで、自分の理解できていない箇所が改めて見つかることがあります。その場合は、計画を変更して、理解できていない箇所を集中的に復習しましょう。
計画表を作成するコツ
変更した計画内容を書きこめるスペースをあらかじめ確保しておこう!
学習進捗チェックリストを使ってみよう!

中学受験を目指す四年生から六年生に向けて、学習進捗チェックリストを用意しました。自身の夏休みの学習の参考にしてください。
四年生
四年生のチェックリストは以下のとおりです。
□ 夏期講習や夏期特別授業の宿題をしっかりやれている
夏期講習や夏期特別授業ではたいてい一律に宿題が出ますが、宿題のやり込み具合については子供によって大きな差が出ます。一読してわからない問題でも、腰を据えて考えてみる姿勢が大切です。「わからない。次」ではなく、わからない問題だからこそ、どういう解き方があり得るか、模索してみましょう。
□ 夏期講習や夏期特別授業の復習ができている
授業内容の復習まで手が回らない子供は多くいますが、「解きっぱなしで放置」では、成績は上がらないので、間違えた問題は必ずやり直しましょう。できれば当日のうちにやり直すのがおすすめです。
ただ、学習慣れしていない四年生ですから、当日は宿題だけで精一杯な子供がたくさんいます。そういう場合は「休みの日にまとめて復習」スタイルでもよいでしょう。
□ 一学期の復習をしよう
一学期の学習内容の中から苦手単元を洗い出しましょう。たとえば、算数であれば四年生の前半で「周期性」「等差数列」「立方体と直方体」などを習い、苦手とする子供は多いです。苦手単元をリストアップし、復習し終わったものから消し込んでいきます。
□ 漢字と計算を毎日やろう
それぞれ五問ずつでよいので、毎日解くようにしましょう。継続のためには、問題数を絞ることが大切です。
□ 都道府県と県庁所在地を頭に入れよう
各校の過去問を見れば一目瞭然ですが、多くの学校で社会は地理の知識を下地に展開しています。そのため、基本的な内容は早い段階で固めておかないと、のちのちしわ寄せで大変なことになります。地図とにらめっこしてもなかなか覚えられないので、都道府県カルタや都道府県パズルを使って、遊び感覚で少しずつ知識を蓄えていくのがおすすめです。仕上げとして白地図でチェックしてみてください。
□ 読書記録をつけよう
読書に本格的に時間を割けるのは四年生までです。この機会にできるだけたくさん本を読みましょう。もし可能であれば、読書記録の隣に、あわせてちょっとした感想文を添える習慣をつけるとよいです。読むだけではなく書く能力の向上につながります。慣用句やことわざもたくさん覚えるようにしたいところです。
□ 社会や理科を実地で学ぶ機会を作ろう
勉強が忙しくなるとお出かけの機会を作るのも難しくなってしまいます。科学館や博物館に足を運ぶことをおすすめします。プラネタリウムに行くのもよいでしょう。
五年生
五年生のチェックリストは以下のとおりです。
□ 夏期講習や夏期特別授業の宿題をしっかりやれている
五年生ぐらいになると、難易度も上がり、宿題量も増えてきます。結果として、手の抜き方の上手い子供が一定数出てくるようになるのです。国語の記述問題や算数の文章題を「ちゃんと考えたけれどわかりませんでした」と空欄のまま提出するケースが頻発します。
実際に、「ちゃんと考えて」いればよいのですが、残念ながら「ただ読み流して終わり」の子供が少なからずいます。「宿題をひと通りやっているだけ」では成績は上がりません。取り組み方の違いが大きな差を生みます。
仮に空欄で出さざるを得ない箇所があったなら、先生から解き方を教わり、改めて解き直すようにしましょう。その場で一度解き直すだけでは実力として定着化しないので、期間を空けて繰り返し解き直します。
□ 算数で苦手だった単元の復習をしよう
五年生になるとどの科目も難しくなります。特に算数は、場合の数、図形の移動などを苦手とする子供が多いです。関連する単元が積み上げられていく分野なので、復習が欠かせません。
□ 国語は、総合知識問題の復習をしよう
夏休み中に総合知識問題の復習をしておきたいところです。特に、文法の知識や語彙を頭に入れ直してください。語彙は一学期読んだ文章で知らなかった言葉にあらかじめ線を引いておき、覚え直していくとよいです。言葉だけで覚えるより、文脈の中で覚えられたほうが、実践的だといえるでしょう。
□ 理科は物理分野・化学分野の計算が解けるように
一学期に物理・化学分野の計算を学んだなら、スムーズに解けるよう夏休み中に復習しておきましょう。力のつり合いや水溶液などを学んできたものの、苦手意識を持っている子供は多いことでしょう。計算問題は数も大切です。いろいろな問題に挑戦しましょう。
□ 社会は地形図や資料を読み解けるように
社会では地理を下地にした出題をする学校が多いです。地図や地形図が読めないと、地理以外の分野でも解けなくなってしまう問題は多いので練習しておいてください。四年生のチェックリストでも挙げましたが、都道府県名や県庁所在地も覚え直しておきましょう。
□ 漢字と計算を毎日やろう
漢字は毎日やって、間違えた問題を頭に入れ直しましょう。計算にもできるだけ取り組みたいところです。問題数は少なくてよいので、積み重ねていきましょう。計算はそろそろスピードも大切になってきます。タイマーで時間を計ることをおすすめします。問題にもよりますが、複雑な四則計算を一分以内で解くぐらいのところから始めたいものです。
六年生
六年生のチェックリストは以下のとおりです。
□ 夏期講習や夏期特別授業の宿題をしっかりやれている
六年生になっても、宿題をやり込まないまま、形だけ整えて提出する子供がいます。夏期講習や夏期特別授業の宿題が「義務」という認識になっているため、その場しのぎの対応になってしまっているケースです。「合格のために取り組んでいる」という認識を持って臨まなければなりません。
自習室のある塾では、居残って宿題をすべて片付けてから帰ることをおすすめします。自習室であれば先生に質問に行けるため、「わからないから空欄のまま提出する」というわけにはいきません。自然と、宿題に対する姿勢も変わってきます。夏休みを無駄しないためにも、授業後すぐに宿題に取り組む習慣を確立しましょう。
□ 算数で苦手だった単元の復習をしよう
志望校の頻出単元を優先しながら、苦手単元をやり込んでいきましょう。一般的に、算数で頻出なのは、立体図形、平面図形、場合の数、規則性、特殊算あたりです。ただし、学校によって出題傾向は大きく違うので、過去問を確認してください。特に、立体図形に関連する単元は、克服するのには時間がかかる傾向にあります。早めに取り組んでひとつひとつわからないポイントを潰しておきたいところです。
□ 国語は読解文や記述問題の対策をしよう
夏期講習や夏期特別授業では多くの読解文を解くことでしょう。読解文が苦手なのであれば、夏休み中にノウハウを身につけておきたいところです。説明文、物語文などのうち、苦手とするジャンルがあれば、集中的にやり込みましょう。記述問題が苦手な場合は、夏期講習や夏期特別授業で扱った文章の要約を書いて、塾や家庭教師の先生に添削してもらってください。この時期、要約をうまく書ける子供は少ないです。ピントがずれていたり、冗長な文章になったりするケースが多いので、回数を重ねて上達を目指しましょう。
□ 理科は夏期講習や夏期特別授業で苦戦したところを
理科は夏期講習や夏期特別授業で苦手だったところを中心に、復習を進めていきましょう。六年生の子供がよく引っかかっているのは、電流、力のつり合い、光などです。それ以外でも自分が苦手だと感じる単元は復習していきます。特に計算で引っ掛かっている単元は早めの復習が欠かせません。知識の取りこぼしは覚え直せばよいですが、計算は数をこなさないとスムーズに解けるようにはならないためです。
□ 社会も夏期講習や夏期特別授業で抜け落ちているところを確認
社会も理科と同様、夏期講習や夏期特別授業で広く復習をするので、抜けている知識を入れ直していきましょう。その際にテキストの解説部分を読み、人に説明できるように仕上げていくことをおすすめします。
□ 漢字を毎日やっておこう
漢字のチェックをしておきましょう。語彙力に自信がない子供は、漢字と並行して語彙のチェックしておくとよいです。直前になってまとめて覚えようとする子供が多いですが、詰め込むのは難しいので、早めに取り組み始めるのがよいでしょう。
□ 最難関校レベルの場合は過去問を始めよう
一般的に、過去問は秋から開始で大丈夫ですが、最難関校レベルを受験する場合は早めに取り組んでおきましょう。
学習進捗チェックをして、夏休みを合格につなげよう
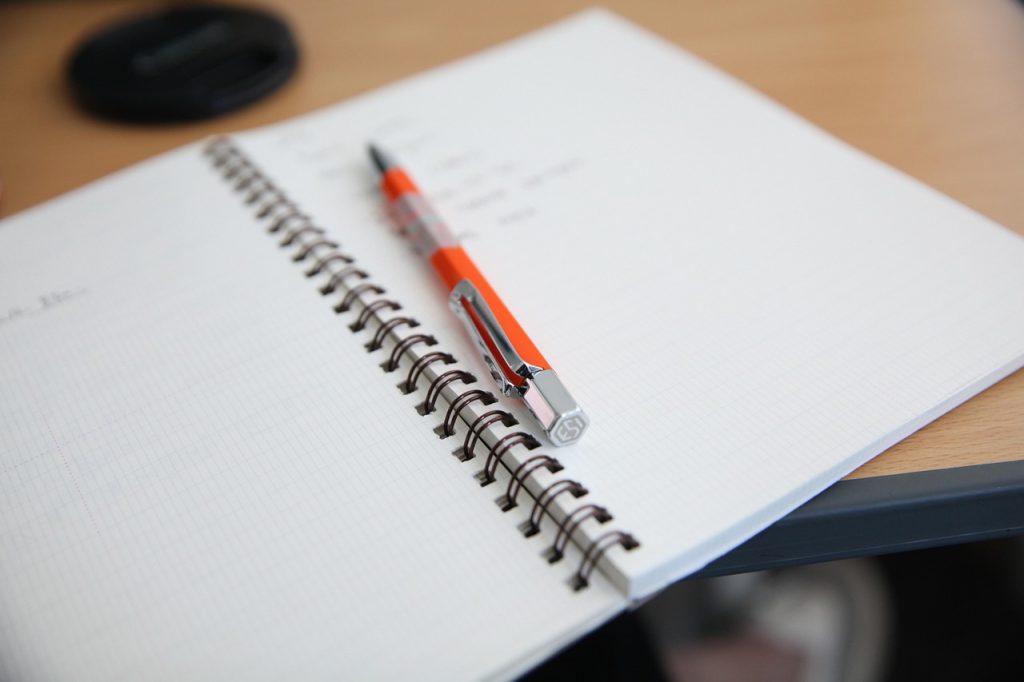
夏休みの頑張りが、中学受験の合否を分けるといっても過言ではありません。そのため、夏休みは最適な計画を立て、適宜学習進捗チェックを行うことで、とりこぼしがないように学習を進めたいところです。
学年によって取り組むべき内容は異なります。四年生のうちは机に向かう勉強だけではなく、学習におけるモチベーション向上につながる体験もしておきましょう。
五年生になると、本格的な勉強が始まります。四年生に比べて負担が大きくなるので、ついていくだけで精一杯な子供も多いです。なるべく早めにコツをつかんで、苦手な箇所をひとつひとつ潰していきましょう。
六年生は受験生なので、やみくもに苦手な箇所を潰していくのではなく、受験する学校の出題傾向も意識したいところです。限られた時間の中で、優先順位の高いものから頭に入れ直していきます。塾や家庭教師と綿密に連携して、自分の現在地を絶えず確認するようにしてください。
どの学年も夏休みの軸は夏期講習や夏期特別授業にありますが、そこからの+αが大切です。一方で、+αにとらわれて、夏期講習や夏期特別授業の内容を通り一遍でしか理解していないようでは、実力は定着化しません。復習と自分に合った学習の両方を欠かさないようにしましょう。