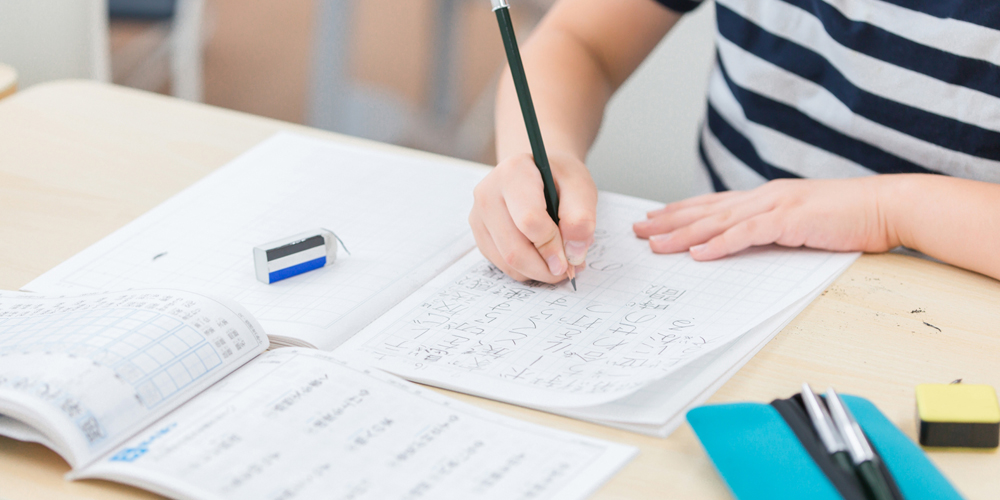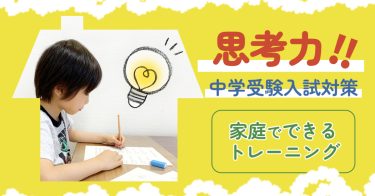12月ともなると、受験本番まであとわずかです。12月に受ける模試が最後の模試という家庭も多いでしょう。この記事では、思うように成績が上がっていない受験生の対策について紹介します。
12月の模試って?どう生かしていけばよい?

12月の模試について見ていきましょう
12月の模試のスケジュール
12月にはたくさんの模試が行われます。2022年の例で見てみましょう。
- サピックス
「合格力判定サピックスオープン」「学校別(筑駒)サピックスオープン」 - 日能研
「合格判定テスト」「公立中高一貫校適正検査対策テスト」 - 首都圏模試センター
「合判模試」
- 日能研
「合格力実践テスト」 - 四谷大塚
「合不合判定テスト」
- 日能研
「合格力完成テスト」「ファイナル256」
- 日能研
「合格判定テスト」
- 日能研
「合格力完成テスト」「ファイナル256」
12月の模試の結果が悪くても合格する?
12月に受けた模試の結果が悪いケース自体はあまり珍しくありません。そもそも、12月の時点で、受験生は受験校対策に特化した勉強へと移行しています。つまり、模試で有利になるような広範な勉強ではなく、ある程度絞り込みをかけた勉強をしている時期なのです。そのため、受験対策がきちんとできている子供ほど、多少模試の結果が悪くなりがちではあります。
受験校に合格できるかどうかを知りたいのであれば、過去問の出来を見ましょう。模試の点数がイマイチでも過去問でよい成績をとれているのであれば大丈夫です。ただし、同じ年度の過去問を何度もやり込んでいるうちに点数が上がるのは当たり前なので、あくまで一回目として解いた過去問の点数を参考にしてください。
模試の結果のどういう点を注意して見ればよい?
模試の正答率を見て、子供がどのレベルの問題まで解けているかを確認しましょう。実のところ、「模試で何点だったか」よりも「どのぐらいの正答率の問題が解けるレベルにあるのか」を知ることのほうが大切です。
たとえば、正答率五割の問題が解けない状態では中堅校でも厳しいです。上位校であれば正答率三割以下の問題を解ける力がほしいところでしょう。正答率の高い問題で間違えているところをピックアップして、どの単元が弱いのか確認してみてください。
模試の目的は現状把握と弱点の洗い出し、方針の見直しです。ただ受けて満足することがないようにしなければなりません。
模試の解き直しをどう進めるべき?
解き直しをどう進めるかはとても重要なポイントです。合格する子供と不合格になる子供との差はここで生まれるといっても過言ではありません。間違えた問題はいわゆる「捨て問」を除いてすべて解き直します。どれが「捨て問」かは、塾や家庭教師にも確認をとるとよいでしょう。
丸付けの際には、まず解説を読んで考え方を整理します。その後、自分で解いてみましょう。ここで重要なのは解けたからといって、そこでおしまいにしないことです。問題集から類題を探してやってみてください。それによって、実力を固めることができます。
模試の問題も日を空けて解き直してみましょう。解説に頼らずスラスラ解けるようになっていれば実力が定着化したと考えてよいです。
1月の模試は受けなくてよい
1月にも模試はありますが、受験本番が迫っているのでわざわざ受けに行かなくてもよいです。この時期は受験本番に向けて、集中的に勉強したほうがよいでしょう。
中学受験に向けて12月からの勉強の仕方

焦りやすい12月。どのように勉強を進めていけばよいのでしょうか。
12月の時点では大半の子供が仕上がっていない
塾の面談や家庭教師との打ち合わせで、「年が明けたらすぐ受験なのに、ぜんぜん勉強が仕上がっていない!」と保護者の悲鳴が飛び交う時期です。ただ、12月の時点ですでに仕上がっている子供はほとんどいません。ここからの追い上げが合否を分けます。
暗記事項をしっかり固めて
この時期は、暗記できていない事項をしっかり覚え直しましょう。国語であれば、ことわざや慣用句といった語彙、理科や算数であれば公式、社会であれば年号や地図です。これまで覚えてきていても、直前になって抜けてしまうケースも少なくありません。しっかりと覚え直すようにしましょう。
12月は週に二回過去問を解く
12月は受験校の過去問を週に二回解いてください。難しい週は一回でもよいです。過去問を解いて間違えた問題のやり直しをしましょう。解く際は必ずタイマーをセットして本番を再現します。イメージトレーニングにもなるため、できるだけ本番のスタイルに合わせるのです。一科目だけではなく、休憩を挟んで本番どおり全科目解きます。
間違えたところは終わったあと、捨て問以外すべてやり直し、解き方を覚えましょう。この場合の「解き方を覚える」は「類題が出題されても自力で解けるレベルまで仕上げること」です。そのため、繰り返しが重要になります。その日だけ間違えたところをやり直すのではなく、間を置いて後日再度やり直しましょう。
やり直すべき問題を一括管理する
やり直すべき問題の管理も数が多いと大変です。付箋やマークだけで管理できているのならよいのですが、難しいようであれば、専用のノートやファイルを作るのも手です。間違えた問題もしくはその類題だけを集めて綴じていきます。やり直してスラスラ解けた頁は外していくようにすると、今できていない問題はどこか一目瞭然になります。弱点をとりこぼしなく克服できて効果的ですし、やるべきことがわかりやすく提示されることで不安感も和らぎます。
保護者自ら過去問を解いてみよう
行き詰まっているようなら一度、保護者自ら過去問を解いてみることをおすすめします。何年分か解くと、その学校の出題傾向や間違えやすいポイントがはっきりと見えてくるものです。私立の過去問の多くははっきりとした出題傾向がありますし、そこを見極めてフォローができれば成績向上は間違いありません。家庭学習を進める上での指針が明確になります。
まとめ教材の苦手箇所だけやろう
大手塾のまとめ教材、あるいは市販のまとめ教材を持っているのなら、苦手箇所だけピックアップしてやってみましょう。塾の教材だと、四谷大塚の「四科のまとめ」やサピックスの「コアプラス」、日能研の「メモリーチェック」が該当します。まとめ教材は万篇なく内容をカバーしている分、難易度が低いことがほとんどです。そのため、上位校狙い以上であれば、網羅的にやり込む必要はありません。苦手箇所だけピックアップして基礎力をつけてください。時間がない中で、効率的に基礎を固める役に立ちます。
受験校を確定させてモチベーションアップ
この時期に気を引き締めるタイプの子供であれば問題ないのですが、中には気を緩めてしまうタイプの子供もいます。しかし、この時期に失速してしまっては、受かるものも受かりません。そのため、受験校確定を改めて気合を入れ直す機会にしましょう。併願校含めた全ての受験校を決めることで、学習方針を改めて明示します。
その際には最終的な目標とは別に、ショートスパンで達成すべき目標を設定してください。失速してしまう子供の多くは「なにをしたら受かるのか」が見えない不安を持て余しているため、課題の可視化は大切です。
また、苦手教科や苦手単元の克服は重要ですが、ずっと苦手な内容ばかりやっていると自信を失ってしまいかねません。子供の様子を見て、ネガティブになっているように感じるのであれば、合間に得意な教科や単元を挟んであげるとよいです。
中学受験直前。1月は学校を休んだほうがよい?

1月に小学校を休んで受験勉強する子供も一定数います。1月は休んだほうがよいのでしょうか。
勉強時間の確保だけではなく感染症対策にもなる
学校を休むのはなにも勉強時間の確保だけを目指したものではありません。冬は風邪をひきやすい上、インフルエンザなど感染症の流行期でもあります。この時期に寝込んでしまうのは厳しいという判断から、学校を休む家庭も少なくありません。
小学校の先生には早めに相談しよう
中学受験をする子供が多い地域では、小学校の先生の対応も慣れたものです。二つ返事で了承してくれる学校もあるでしょう。しかし、中学受験をする子供が少ない学校だと、先生もよい顔をしないかもしれません。いずれにせよ、どうするかを決めたら早めに先生に相談しておきましょう。まずは「中学受験をする皆さんは例年どうしているんですか」と探りを入れてもよいでしょう。
学校を休んだ場合の子供への影響を考える
1月に学校を休むかどうかは、各家庭の判断で決めるべきことです。ただし、親の一存で決めるのは避けたほうがよいでしょう。学校に通いたい気持ちを強く持っている子供もいます。親がよかれと思っていても、一方的に休むと決めることで子供のメンタルに重大な影響が出ることもあります。
また、通学をやめて生活リズムが崩れることで、うまく学習に集中できなくなる子供もいます。子供とよく相談して、休む場合はどうやって勉強を進めていくかあらかじめビジョンを共有しておいてください。
塾や家庭教師のスケジュールを確認しよう
1月に休むと決めた場合は塾や家庭教師にどの程度フォローをお願いできるのか、確認しておくとよいです。朝何時から自習室を使ってよいのか、個別指導を追加してもらえるのか、家庭教師の回数を増やせるのかなどを聞いておきましょう。せっかく学校を休むのですから、効果的に勉強できる体制を整えておきたいものです。
中学受験直前期の保護者のサポートでNGなこと

中学受験直前には、保護者のサポート力も問われます。では、どのように子供を支えていくべきなのでしょうか。
「滑り止め」とは言わない
第一志望校のほかは「滑り止め校」という認識の家庭も多いことでしょう。しかし、子供と話す際に「滑り止め」という言葉を使うことはおすすめしません。万が一、その滑り止めに通うことになったとき、子供のプライドが傷つくためです。あくまで併願校という言葉を使うようにしましょう。
子供に睡眠時間を削らせない
受験直前期はどの家庭も焦っています。しかし、焦りから子供の無理を許すのはよくありません。就寝時間と起床時間を見て十分に睡眠をとれるようにしましょう。
よく受験前は「どんなに無理をさせても六時間」といいますが、これは六時間でうまくいく子供の場合です。六時間睡眠にした影響で、授業中に居眠ってしまうケースもたくさんあります。
睡眠時間が短いのではないかと感じたら、塾や家庭教師に子供がちゃんと集中できているかを確認するようにしましょう。
保護者の不安を子供にぶつけない
子供がプレッシャーから、不安定になることもよくあります。その場合は保護者が寄り添ってあげたいところです。逆に、親が自分の焦りを子供にぶつけてしまうケースも多いので、気をつけましょう。
他の子供と自分の子供を比べる言葉は避けて、自分の子供の成長に注目しましょう。比較対象は常に過去のその子です。子供の不安感が解消されないようであれば、塾や家庭教師の先生に伝えてポジティブな声かけをお願いしてください。
12月からが受験合格に向けた仕上げの本番
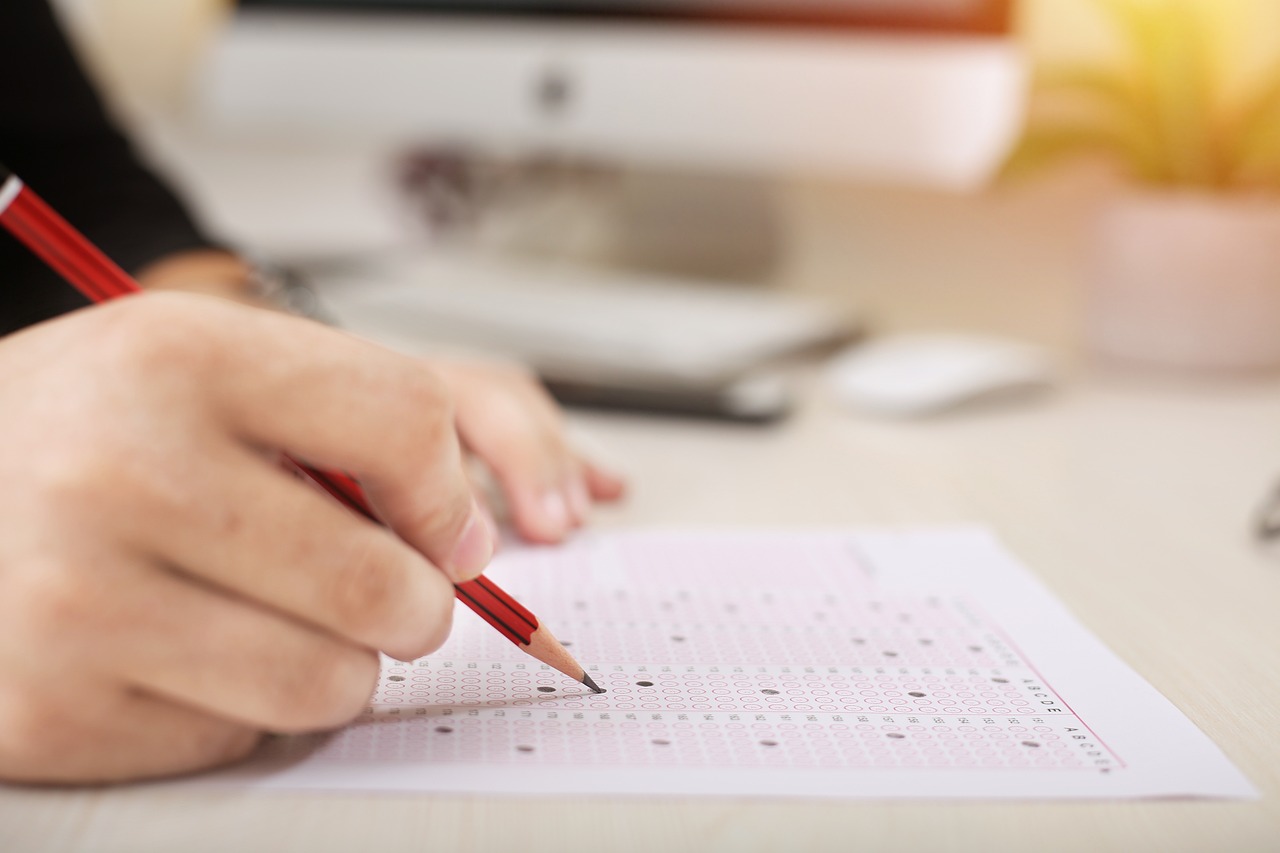
12月になって、模試で点数が伸びなくても焦る必要はありません。志望校に特化した勉強ができている子供ほど、模試に必要な網羅的な対策ができないためです。この時期は、模試で高い点数をとることより、過去問で点数がとれることのほうが重要になります。
そうはいっても、過去問で合格ラインに到達している子供はまだ限られているでしょう。どのぐらい点数が足りていないのかを分析し、その不足を残り期間で埋めるにはどうすればよいのかを整理しましょう。そのためには塾や家庭教師との綿密な連携が必要です。
1月に小学校に行くかどうかも早めに決めて学校に連絡しましょう。休むのも一長一短なので、子供と相談して決めてください。休むなら、その間の勉強をどう効率的に進めるか考え、利用できる教育サービスは利用しましょう。緊張感が高まり、家庭内もピリピリしがちですが、一番つらいのは本人です。できるだけ温かい目で見守ってあげてください。無理をしがちな時期ですから、体調管理にも気をつけてあげるとよいでしょう。